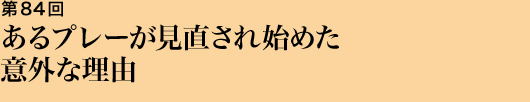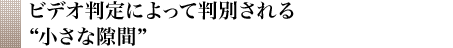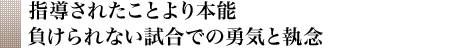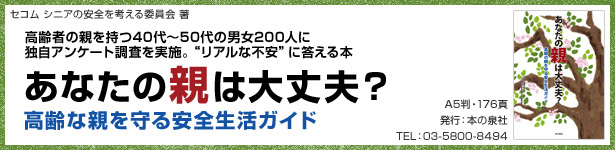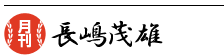防犯対策・セキュリティのセコム TOP
> ホームセキュリティ
> おとなの安心倶楽部
>
月刊 長嶋茂雄
> 第84回 あるプレーが見直され始めた意外な理由
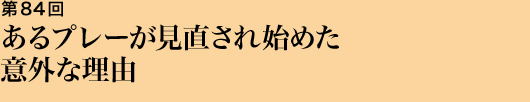
第84回
あるプレーが見直され始めた意外な理由
炎天下の甲子園の高校野球が終わり、残暑の中にも朝、夕は秋の気配が感じられます。これからは、プロ野球がポストシーズン試合に向けて熱くなります。「もう1試合も負けられない」そんな状況がやってきました。
絶体絶命の試合を象徴するプレーに「ヘッドスライディング」があります。高校野球を思い出してください。試合の最後の打者がゴロを打って一塁に走った場合は、かなりの確率で「ヘッドスライディング」をやっていました。
ところが、ご承知のようにプロ野球ではあまり見られません。なぜでしょうか。
頭から飛び込むヘッドスライドは、胸、腹、脚と体の大半が地面と接した摩擦の運動です。腰と脚だけが地面に接するスライディングより摩擦の部分が大きく、したがってスピードの減速率が高く、スローになるため不利、と考えられてきたのです。ところがいま、大リーグでは、ヘッドスライディングを見直す選手が増えているのだそうです。
興味を引いたので、教えられた情報の受け売りに私の考えをそえて話します。
大リーグの監督は、選手たちに「ヘッドスライドはするな」と伝えるのが普通と言います。見た目よりスローであるということよりも、怪我の危険が脚からの滑り込みより多いためです。2015年シーズンの統計では、ヘッドスライド249回につき1件の負傷事故。これに対して脚からのスライディングでは413回に1件の負傷です。
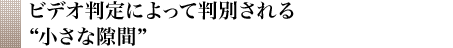
ビデオ判定によって判別される"小さな隙間"
しかし、今季は監督指令に反して、ヘッドスライドを強行する選手が増え始めたらしいのです。その理由は、ビデオ判定のため、というのです。
意外な話、と思いましたが、話を聞けば納得です。
脚から滑り込み「セーフ」の判定。チャレンジがあって精密画像の超スロー映像でスライディングした走者が立ち上がるまでの様々な角度から撮ったシーンが繰り返されます。すると目では判別出来ない、普通のスロー画面でも分からない、選手の体がベースから離れて"小さな隙間"が一瞬生まれ、そのときに野手のグラブがタッチされているのが、繰り返しの映像で見て取れます。そして判定は「アウト」にくつがえる・・・。
大リーグ中継をご覧のファンはこんなシーンを一度は見たことがあるはずです。
「うーん、なるほどね」と思うと同時に、まるで顕微鏡で検査するかのような時間をかけた判定には、「そこまでやるのか」と思ったりもします。
「この種のプレーにはビデオ判定を使わないようにすべき」という監督もいるのだとか。
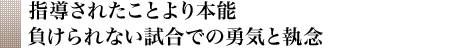
指導されたことより本能負けられない試合での勇気と執念
ヘッドスライドならこうした"問題"は起こらない、というのがヘッドスライド派の選手たちの主張です。
頭からの飛び込みで真っ先にベースにつくのは伸ばした手、そのタッチの手は、そのままベースを抱え込むように保持するので、スライディングが完了し、立ち上がるまで体のどこかは必ずベースについていて、体全体がベースから離れることはなくなります。
「突き指をしたり、手首を痛めたりの危険は分かる。しかし、オレたち選手は、負けられない試合のプレーでは指導(インストラクト)されたことより本能、直観(インスティンクト)に従う。ヘッドスライドの技術も今後向上していくさ」という選手の言葉には全面的に共感ですね。
それにしてもビデオ判定が危険視されたプレーを見直しさせた、というのが愉快ではありませんか。
私は現役時代にヘッドスライディングはしませんでしたが、観戦する側になると嫌いではありません。勇気、執念を観る者に直接訴えてくるからです。
ちなみに「ヘッドスライディング」は日本製の野球英語です。頭で滑るのではありませんから、「ヘッドファースト(頭を先にした)スライディング」がアメリカの英語です。ご存知でしたか?
クライマックス・シリーズに向けて、日本のプロ野球でも「ヘッドスライディング」が増えるでしょうか。
長嶋茂雄さん 看板豆知識・伝説・語録
歴代のセコムオリジナル長嶋茂雄さんの看板(ビッグボード)と、それにまつわる豆知識のご紹介や、1957年に通算8本塁打で東京六大学リーグ本塁打の新記録を達成してから現在にいたるまでの、長嶋茂雄さんの伝説「NAGASHIMA Living Legend」と、数々の名言を世の中に送りだしてきた長嶋茂雄さんの名言「伝説の長嶋茂雄“語録”」をご紹介します。