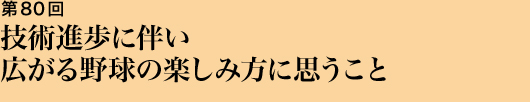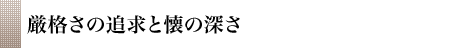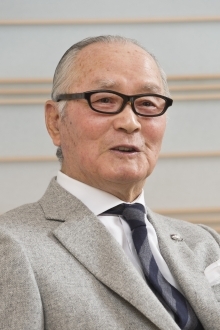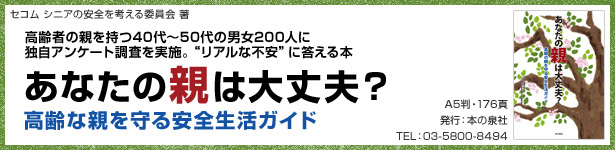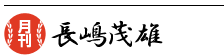防犯対策・セキュリティのセコム TOP
> ホームセキュリティ
> おとなの安心倶楽部
>
月刊 長嶋茂雄
> 第80回 技術進歩に伴い広がる野球の楽しみ方に思うこと
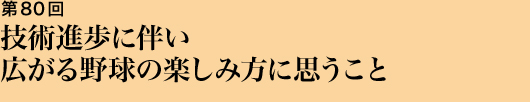
第80回
技術進歩に伴い広がる野球の楽しみ方に思うこと
大リーグ中継を拾い観していたら、画面の下に枠に囲まれた数字が出ました。「投手が投げたボールが捕手のミットにおさまるまでのボールの回転数」だといいます。「2000回転、すごいスピードです」、「1300回転、平均的なスピードといえるでしょう」などとやっている。
本塁打が出ると、打ちだされたときの打球の角度が「30度」だとか「45度」だった、とビデオに打球の飛んだ軌道を書き込み、高さの表示、滞空時間、飛距離などを伝えてくれこともあるといいます。盗塁での走者のスピード、外野手のバックホーム送球スピード、投げた距離...プレーに関わるすべてが数字で表示可能らしいのには驚きました。
大リーグ機構(MLB)がスマホ、パソコン、ゲーム機器になれた若い年齢層のファンを取り込もうと数年前から進めてきた"デジタル時代の野球の楽しみ"の提供、そのほんの一端を私は眼にしたわけです。

昔懐かしさを覚えたデジタル野球
何だか選手はデータ・数字を生み出すためにプレーしているようで、妙な気分になりました。その一方で、野球の楽しみ方の範囲を広げた計測技術、映像技術の進歩に感心もしましたけれど、「昔もこの種の楽しみはあったなあ」と思ったのも正直なところです。
投手の「浮き上がってくるような速球」は、2000回転クラスだったのでしょう。「2階から落ちてくる大きなカーブ」、「一度止まってストンと落ちるブレーキのある変化球」はずっと回転数が少ないのでしょう。数字ではなく印象、感覚で味わいました。ライナーで打ち込まれたホームランを「ロープを張り渡したような打球だ」と、どよめいたり、高々と打ち上げられた一発には「落ちるまでずいぶん時間がかかったな」と夜空を見上げ直して、どのあたりまで上がったのか想像した経験はファンの皆さんもお持ちではないでしょうか。
数字と映像で事実を確認して楽しむのがアメリカの"デジタル野球"なら、自分が観た感覚を頭の中で再生して楽しむのが日本の"アナログ野球"とでも言えるのかもしれません。楽しみ方ですから優劣はありませんね。
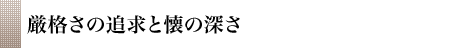
厳格さの追求と懐の深さ
ところが最近、アメリカの有力紙に「データと数字でベースボールを破壊させるな」という投書が掲載されたと教えられました。
タイトルだけでも投書の内容は想像できます。
「私たちは、データやキーボードやタッチ画面などにかこまれた、せわしない時間を日々過ごしている。そんな日常から離れ、持参のスコアカードに鉛筆でプレーを書き込んでいく面白さ。楽しい音楽のように時にスピーディに、時にスローに進行していく試合、打球音が響き、ボールを追う選手たちの動きは、まるで観客とかわすボディ・ランゲージのようだった。ところが、あふれかえる数字がそんな野球のニュアンスを破壊してしまい...」。
ロマンチックな"古き良き時代の大リーグ野球はどこへ行った"と言うのです。投書したのは高齢者だったのでしょう。
気持ちはよくわかります。けれども時代を押し戻すことはできません。
ちょっと考えてみると、野球は他のスポーツに比べ"デジタル化"は舞台裏での利用に限られ、ファン・サービスに使うという面ではスローだったように感じられます。オリンピック競技の計測機器の進歩を思い浮かべればわかります。勝負の正確さ、ジャッジの厳格さの追求は急速に進みました。
変な言い方になりますけれど、野球には"誤審"を認めるいい意味での寛容さがありました。しかし、時代はそんな懐の深さを許さなくなったようです。
さて、そこで日本の野球です。大リーグでやることは取り入れてきましたが、今度ばかりは機器を備えるだけでも大変そうです。個人的にはプレー以外のことですから、じっくり考えていけばいい、と思いますが、どうでしょうか・・・。
第80回 技術進歩に伴い広がる野球の楽しみ方に思うこと
長嶋茂雄さん 看板豆知識・伝説・語録
歴代のセコムオリジナル長嶋茂雄さんの看板(ビッグボード)と、それにまつわる豆知識のご紹介や、1957年に通算8本塁打で東京六大学リーグ本塁打の新記録を達成してから現在にいたるまでの、長嶋茂雄さんの伝説「NAGASHIMA Living Legend」と、数々の名言を世の中に送りだしてきた長嶋茂雄さんの名言「伝説の長嶋茂雄“語録”」をご紹介します。