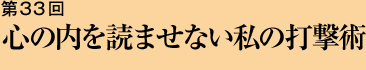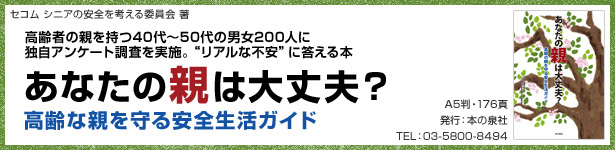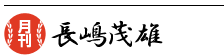防犯対策・セキュリティのセコム TOP
> ホームセキュリティ
> おとなの安心倶楽部
>
月刊 長嶋茂雄
> 第33回 心の内を読ませない私の打撃術
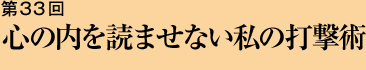
第33回
心の内を読ませない私の打撃術
「打席では何も考えていないのですか?」と私の現役時代を知らない記者が言い出しました。話のタネは、テレビ特番で私の昔のプレー・ドキュメントが再放映され、その中での稲尾(和久)さんのインタビューです。
「巨人に勝つには長嶋を抑えること。何を考え、何をねらっているか、マウンドから必死に観察するが、ボケーッと立っているだけで分からない。ようやく第3戦で、こいつは何も考えていないのだ、と気がついた・・・」と笑っていた、と言うのです。
「何も考えず、ボケーッと」には苦笑ですが、稲尾さんにわが心の内を読ませなかっただけなのです。それが私の"打撃術"でした。
稲尾和久さん、ご存知でしょう。話題にしていたのは西鉄が3連敗のあと4連勝で巨人を破った昭和33年(1958年)の日本シリーズ、私のルーキーイヤーです。
このシリーズで稲尾さんは6試合に投げ、4試合完投の鉄腕ぶりを発揮して、「神様、仏様、稲尾様」と称えられました。稲尾さんは「こちらが投げようとモーションを始めると、それに合わせて打ちにかかるバッターの微妙な動きで狙い球を察し、球をリリースする瞬間に、打者の狙いと逆の球を投げて打ちとる・・・」と高度な"投球術"の真髄も語っていたと言います。なるほど、とうなずきます。
これを打者の側から詰めると私の"打撃術"になります。
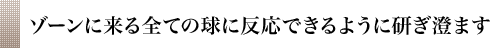
ゾーンに来る全ての球に反応できるように研ぎ澄ます
私は、今度はカーブがきそうだとか、外角に投げてくるだろうなどと、たいていの打者がやっている球種やコースの予測はしませんでした。この予測を「考える」というなら、確かに「考えて」いません。
ただし、全神経はストライクゾーンに来た球を打つ、ゾーンに来るすべての球に反応できるように研ぎ澄ましているのです。狙い球を絞る打者に慣れている投手にすれば、捉えどころがなく、何も考えていないように見えたことでしょう。
投手の手から離れた球は、レーダーのように網を張っている"自分のストライクゾーン"に入ってきます。この球の芯を思い切りたたきつぶす、これが私のバッティングでした。"自分のストライクゾーン"は、野球規則に規定されているストライクゾーンとは違います。よくボール球を安打にした、と言われるのも、私のストライク球だから打ったのです。
せっかちで攻撃型の性格なので、打席を外したりモジモジしたりの投手との駆け引き、腹の探り合いにも無縁でした。四球で歩くのはつまらない。打ちたい、だから早いカウントから打って出る、これは現役時代を通じて変わりませんでした。
稲尾さんは私の打撃を「球に身体が反応するバッティング」と評したとか。球が投げられてから手元に来るまでの1秒の何分の一かの一瞬の間に、球種、球筋を見極め、ストライク、ボールを判断し、スイング・・・この"我が打撃術"を上手く言い当ててくれたと思います。
稲尾さんが球をリリースする瞬間に勝負をかけたと同様、私は球が投手の手から離れた瞬間から勝負に入ったのです。投打の真髄はコインの表と裏でした。
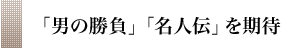
「男の勝負」「名人伝」を期待
「稲尾さんは、投げた後バットとボールが当たるところまで見極めるが、長嶋はスッとバットの握りを調節して打ってくる、と言いましたよ。剣豪伝、名人伝の世界ですね」と記者は嬉しがります。「そうだよ。投手と打者の決闘だ」と私は応じます。
稲尾さんは思い出を語った本の中でこうも言い残したそうです。「奇跡の逆転で日本一になったが、長嶋さんには嫌な思いをさせられたなあ。第1戦の最初の打席が三塁打、第7戦の最後の打席がランニングホームランなんだから」。チームは勝っても、投手として心残りがあったのです。チームが負け、鉄腕を打ち崩せなかった私には悔しさだけ、こうして互いに技術を高めあっていくのです。
「そういう対決、今はなさそうだ。見たかったですね」と記者は言います。確かに「男の戦い」の要素が薄味になっているのが最近の試合かもしれません。しかし、私は、新しい「男の勝負」、「名人伝」を期待し待ち続けています。野球はいつもその時代にふさわしいドラマを生む底力を持っているはずですから。
長嶋茂雄さん 看板豆知識・伝説・語録
歴代のセコムオリジナル長嶋茂雄さんの看板(ビッグボード)と、それにまつわる豆知識のご紹介や、1957年に通算8本塁打で東京六大学リーグ本塁打の新記録を達成してから現在にいたるまでの、長嶋茂雄さんの伝説「NAGASHIMA Living Legend」と、数々の名言を世の中に送りだしてきた長嶋茂雄さんの名言「伝説の長嶋茂雄“語録”」をご紹介します。