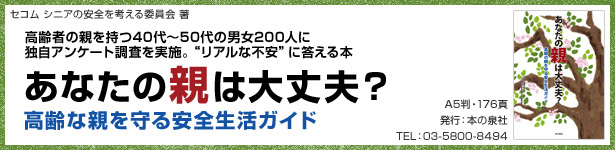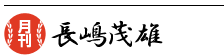防犯対策・セキュリティのセコム TOP
> ホームセキュリティ
> おとなの安心倶楽部
>
月刊 長嶋茂雄
> 第39回 勝負への執念

第39回
勝負への執念
あっという間の1年です。今年も良いこと、悪いこと、悲喜こもごもの12か月でしたが、「終わりよければすべてよし」とはなりませんでした。日本シリーズで巨人が楽天に敗れ、連続日本一になれなかったのが、心残りです。その日本シリーズの最中、1勝1敗のタイになり戦いの舞台が仙台から東京に変わる移動日に川上(哲治)さんが93歳で亡くなりました(これは数日後に明らかにされたことでしたが)。こうして1か月たった今、私は巨人の敗戦と川上さんの思い出とを重ねて考えてしまいました。
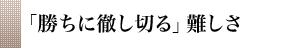
「勝ちに徹し切る」難しさ
と言っても巨人の敗戦分析ではありません。巨人の連覇は川上監督の下での1973年のV9達成が最後で、以後絶えてありません。そんな事実に「勝つことに徹する」難しさを思ったのです。川上さんは私情を消し去って「勝ちに徹し切る」ことができた稀有の監督でした。「勝負ならばそれが当たり前」と言うかもしれませんが、これが難しいのです。
試合の大事な場面で、選手のプライドや体面を傷つけ、チーム内での立ち位置や将来の選手生活にまで影響するかもしれない采配を冷徹に進めること。これは監督が選手を理解し、それぞれの背負ったものを知れば知るほど難しくなります。ましてその采配が裏目に出た時のリスクを考えると、どの監督もたじろいだ経験はあるはずです。
川上さんはそういう情緒的なことを断ち切れる監督でした。「哲のカーテン」がその証です。アメリカとソ連が争った冷戦時代、ソ連の厳しい情報管理は「鉄のカーテン」を引いている、と言われたそのモジリです。取材時間の制限や外部からの"雑音"を選手に入れないように川上さんは悪評覚悟で情報管理と監督を頂点とする統制管理を徹底しました。私と王さんには自由に打たせてくれましたが、戦法は手堅く「石橋を叩いて渡る、どころか、ハンマーでたたきまくって安全と分かってもまだ渡らない」と批判されもしました。
勝利と言う目的達成には「無私」になること「無心」になることを川上さんは禅を学ぶことで追及していました。その成果による私情を入れない勝負への姿勢、それが「哲のカーテン」でした。
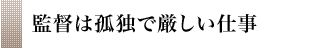
監督は孤独で厳しい仕事
ちょっと話が外れますが、「3番(私のことです)の勘」を話題にしていた記者たちに珍しく川上さんが講釈したことがあったそうです。これも禅に関わるのでしょうが「勘とは、頭に貯め込まれてきた知識と経験による瞬間的判断だろう。君たちみたいに貯め込んだ知見なしの勘は"山勘"にすぎない」と笑ったというのです。私には納得できる卓見です。
とにかく、川上さんは、世評は一切気にしなかった様に思います。「勝つだけ」に集中するそんな「非情」とも見られかねない姿に、私は監督とは何と孤独で厳しい仕事なのだろう、と思ったものです。
日本シリーズを振り返ると、巨人は楽天の熱さに押しまくられていた感じです。楽天は、大震災の痛手に苦しんでいる東北復興のシンボルです。日本一になれば地元の励ましになる・・・こんな気分が日本中の野球ファン大多数にあったようです。巨人もそういう空気は読んでいたに違いありません。しかし、それで相手をおもんばかった気持ちが戦う者の心に少しでもきざしたとしたら、"勝負の敵"になってしまうでしょう。
1勝1敗の後、東京ドーム初戦の第3戦には、私も観戦に行きました。試合前のサロンの雑談で「このドームの3連戦で決めてしまって欲しいですね。仙台に戻るとなるといやな予感がするなあ」とOB記者が言い出したのです。「地元の応援に加えて日本中の判官びいきの応援も加わるし」と言うのです。「そんなことは、思っていても、口にしてはいけないことだ」と皆が笑って雑談終了となったものの、確かにそんな思いは皆の心の隅にありましたね。
日本中の野球ファンの思いに押されて勢いに乗る楽天、巨人は逆に・・・と言うのが私の見立てです。
一言雑学を付け加えます。バットマンとしての川上さんは「ボールが止まって見える」の名言で知られますが、今でも良く使われる「球際=たまぎわ」という言葉を作ったのも川上さんでした。野球一筋の肥後モッコスの大往生に連覇をたむけたかった、とつくづく思いました。
長嶋茂雄さん 看板豆知識・伝説・語録
歴代のセコムオリジナル長嶋茂雄さんの看板(ビッグボード)と、それにまつわる豆知識のご紹介や、1957年に通算8本塁打で東京六大学リーグ本塁打の新記録を達成してから現在にいたるまでの、長嶋茂雄さんの伝説「NAGASHIMA Living Legend」と、数々の名言を世の中に送りだしてきた長嶋茂雄さんの名言「伝説の長嶋茂雄“語録”」をご紹介します。