新4年生のための留守番と放課後の安全
-
セコムの舟生です。
 そろそろ来年度の学童保育(いわゆる「学童」)の入所可否が決まる頃でしょうか。
そろそろ来年度の学童保育(いわゆる「学童」)の入所可否が決まる頃でしょうか。
学童の利用対象年齢は拡大されつつありますが、実際はまだ4年生以上は利用できないところが多いようです。
共働きのご家庭では、いわゆる「小4の壁」に直面することになります。
・学校が終わってから、保護者が帰ってくるまでの時間をどこでどう過ごさせればいいのか
・留守番をさせて大丈夫なのか
・鍵はどうやって持たせたらいいのか
・何かあったときの連絡方法は...?
いろいろな不安が浮かんでくるのではないでしょうか。
進級前にお子さんと話し合って、放課後の過ごし方や留守番のルールを決めておきたいですね。
今回は、学童保育がなくなる新4年生のお子さんのための安全ポイントをまとめます。
* * * * * * * * *
▼ 放課後を過ごす場所を決めましょう
学童保育がなくなって気がかりなのは、放課後の居場所。
これまでは学童に直行していたお子さんも、これからは一度自宅に戻ってランドセルを置いてから、次の行動をすることになりますね。
まず行っていい場所と行ってはいけない場所を決めておきましょう。
児童館や放課後の校庭開放、近所の公園など、お友達がたくさん集まり、親御さんが「ここなら大丈夫だろう」と思える場所を選びます。
親御さんが「ここなら大丈夫」と思えない場所には、行かないことを約束させるなど、お子さんがどこにいるかある程度は把握できるようにしておきましょう。
学童のない放課後に慣れるまでは、行動範囲を限って様子を見たほうが安心です。
ほかにも習いごとや塾をはじめたり、通う回数を増やしたりして、放課後を乗り切る親御さんも多いと聞きます。
同級生の保護者の方に、評判のいい習いごとを聞いたり、お子さん自身にやってみたいことはないか聞いたりしてみてもいいかもしれませんね。
4月の進級まで少し時間がありますので、今なら慌てずに情報収集ができますし、親子にとって安心できる放課後の過ごし方についてじっくり考えられると思います。
▼ 新4年生のための「鍵の持ち方」 家の鍵はとても大切です。
家の鍵はとても大切です。
もし鍵をなくすようなことがあれば、拾われた鍵で家の中に侵入される危険も考えられます。
また、子どもが鍵を持っていることが知られると、後ろをつけられて押し込みなどの犯罪にあう可能性があります。
これまで家の鍵を持ち歩いた経験がないお子さんには、まず「鍵の大切さ」をよく理解させてください。そして2つのことを約束させましょう。
<鍵を持つための約束>
(1) 鍵は誰にも見せない
(2) 鍵はいつも身につけておく
鍵を肌身離さず身につけておくには、キーチェーンを利用して、ベルトループなどで衣服につないでからポケットの内側にしまっておく方法がおすすめ。
玄関先でもたつかずにサッと取り出せ、紛失する可能性も低いと思います。
バッグにしまう場合も、キーチェーンにつないで内ポケットなどに入れ、他者から鍵を持っていることがわからないようにすること。
また、屋外でバッグを置きっぱなしにしないよう気をつけさせましょう。
万が一、鍵をなくしたときの対策も親子で話し合っておいてくださいね。
▼ 留守番のときの注意点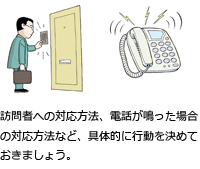 お子さんひとりでの留守番をお願いするなら、家で安全に過ごすためのルールを決めておきましょう。
お子さんひとりでの留守番をお願いするなら、家で安全に過ごすためのルールを決めておきましょう。
<新4年生のための「留守番のルール」>
(1) 家に帰ったらすぐに玄関の鍵をかける
家に入ったらすぐに鍵をかける習慣を今のうちからつけさせましょう。
ドアチェーンも忘れずに。
(2) 窓は開けない。施錠したままにする
居空きや忍び込みなどが頻繁に発生しています。
暑いときはエアコンや扇風機を使うなどして、窓を開けずに過ごすようにさせてください。
(3) インターホンが鳴ってもドアは開けない
たとえ荷物の受け取りでも、小学生のお子さんに対応させるのは避けましょう。
留守番中の子どもを狙い、緊急を装って家に押し入る悪質な犯罪が過去に何度も起きています。何を言われても絶対に開けてはいけないと教えてください。
また、電話やインターホンをお子さんがなるべく取らずに済むよう、ご家庭でも工夫してください。
(4) 火は使わない
お子さんに言い聞かせるだけでは不十分です。
ご家庭内のライターやマッチの置き場所、ガスの元栓など、火の元の管理は保護者の責任ですから、安全を十分に確認してから出かけるようにしましょう。
(5) 出かけるときは必ず鍵をかける
外出時に玄関の鍵をかけ忘れてしまうお子さんは多いようです。
鍵をかけたあと、ちゃんと閉まったか確認するところまでが戸締まりです。丁寧に行うことを習慣づけてください。
* * * * * * * * *
▼ 子どもに携帯・スマホを持たせる場合のルール
学童保育がなくなる小4進級のタイミングで、子どもに携帯電話を持たせるご家庭も多いと思います。
最近はいわゆるガラケーではなく、スマートフォンを持つ子も増えていますね。
お子さんの居場所を確かめたいときや、困ったことが起きたときの連絡手段として、携帯電話やスマホは、親子の強い味方。
けれども、お子さんに携帯電話やスマホを持たせるということにはリスクをともないますので、事前に使い方をお子さんとよく話し合ってください。
<お子さんにファーストケータイを持たせるときの基本ルール>
(1) インターネットやメールは自由に使わせない
たとえば、最初は通話機能のみ利用する、メールの相手は家族のみに制限するなど、お子さんの成長度合いに応じて、段階的に使わせましょう。
インターネットやアプリを使わせるのであれば、フィルタリングサービスを利用し、使用場所や使用時間を限定してください。
(2) お子さんのケータイ利用状況を常に監視し、注意する
誤った使い方をしていないかどうかは保護者が管理する必要があります。
子どもの通話・メールの履歴、よく利用しているサービスなどを定期的に確認して、適切かどうかチェックしましょう。
携帯電話やスマホは、持たせはじめが肝心です。
最初に「やっていいこと」「やってはいけないこと」の線引きをしっかりと行い、「わが家のルール」を明確にしておけば、成長してからも自制心を持って使えるようになるはずです。
* * * * * * * * *
携帯電話やスマホを購入するタイミングにある保護者の方からはよく「どんな機種を選べばいいのでしょうか?」という質問をされることがあります。
正しい使い方を身に付ける時期にあたる小学生のうちは、「子ども向け」「保護者が安心して持たせられる」という2つのポイントで、機種を絞り込んでみてください。
最近は、インターネットのリスク回避のための機能が充実しているだけではなく、GPS機能を利用した防犯性の高い機種も登場しはじめています。 たとえばauから先日発表された「miraie f(ミライエ フォルテ)」は、"親子で決めたルールを簡単に設定できる"新しいジュニア向けスマートフォンです。
たとえばauから先日発表された「miraie f(ミライエ フォルテ)」は、"親子で決めたルールを簡単に設定できる"新しいジュニア向けスマートフォンです。
お子さんの学齢に合わせてWEBサイトやアプリを自動で制限するフィルタリング機能や、スマホの使い方を目で見て確認できる「アプリ利用チェッカー」などの機能があり、インターネットトラブルや使いすぎのリスクを軽減できます。
また、本体の側面には防犯ブザーボタンを搭載。
作動すると位置情報を取得して、保護者にメールで自動送信されます。
さらに「ココセコム」にも対応しており、ご契約いただけば、万が一のとき保護者のご要請により、セコムの緊急対処員がお子さんのもとへ急行することが可能です。また、防犯ブザーの作動に対して、セコムのオペレーターが通報信号を受信し状況を確認する設定にもできます。
「お子さんが安全に使えるスマホを選びたい」という方はもちろん、「保護者の目が届かない時の安全」が気になる方にもおすすめです。→「miraie f(ミライエ フォルテ)」紹介ページへ
2017.01.23

































