子どもに携帯型ゲーム機を持たせるときの注意点
-
セコムの舟生です。
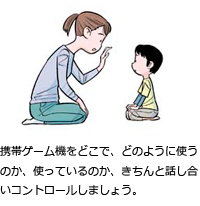 子どもに人気の携帯型ゲーム機。
子どもに人気の携帯型ゲーム機。
クリスマスにサンタさんからもらったお子さんや、お年玉で購入したというお子さんもいらっしゃるのではないでしょうか^^
子どもから大人まで、携帯型ゲーム機を持ち歩けば外出先でも楽しめます。
携帯型ゲーム機は、子どもにとっても身近な遊び道具です。
小学生でも所有している子どもが多く、気軽に買い与えてしまいがち。
しかし、携帯型ゲーム機をきっかけに、子どもがトラブルに巻き込まれることもあるのです。
携帯型ゲーム機にはどのようなリスクがあるのか。
子どもに持たせる場合は、何に注意すればいいのか。
保護者の方がしっかりと理解したうえで、安全に遊べるよう見守ることができるといいですね。
今回は、お子さんに携帯型ゲーム機を持たせるときの注意点をまとめます。
* * * * * * * * *
▼ 携帯型ゲーム機で何ができるのか?
携帯型ゲーム機では、ゲームソフトで遊ぶ以外にもいろいろなことができます。
インターネット接続機能はそのひとつで、オンラインでゲーム対戦をしたり、対戦相手とチャット機能で対話したりと、多様な楽しみ方が可能です。
パソコンやスマホと同様、WEBサイトを閲覧したり、SNSを利用したりすることもできます。
小学生は携帯型ゲーム機を使ってどのようなことをしているのでしょうか。
内閣府が発表した「平成27年度青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、携帯型ゲーム機を所有している小学生のうち、インターネットを利用しているのは49.2%。
ゲーム以外では、「動画視聴」(31.1%)がもっとも多く、「コミュニケーション(メール、メッセンジャー、ソーシャルメディアなど)」(10.2%)、「情報検索」(9.9%)、「音楽視聴」(8.5%)、さまざまな使い方がされていることがわかります。
わずかではありますが、「ショッピング・オークション」や「電子書籍閲覧」などに利用している小学生もいるようです。
携帯型ゲーム機は「ゲームに特化した端末」ではなく、「高度なインターネット端末」と考えましょう。
▼ 携帯型ゲーム機をお子さんに持たせるリスク
携帯型ゲーム機を利用した場合のリスクをいくつかあげてみます。
・考えられるリスク:1...知らない人との出会い、個人情報の流出
見知らぬ第三者と知り合い、名前や学校を知られたり、実際に会ってわいせつ被害にあったり、裸の写真を送ってしまったりといった被害が頻発しています。
「小学生なら簡単にだませる」という動機で子どもが利用するゲームの掲示板やSNSに登録する悪質な大人がいるのが実態です。
・考えられるリスク:2...有害サイトの閲覧
携帯ゲーム機から、小学生がアダルトサイトや有害な動画などを閲覧していた事案が報告されています。
・考えられるリスク:3...高額請求
携帯型ゲーム機では、オンライン機能を利用して簡単にゲームソフトのダウンロードができます。
保護者のクレジットカードで有料ゲームを購入したり、課金型のゲームの有料アイテムを購入したりして、高額請求トラブルになったケースが報告されています。
・考えられるリスク:4...ながら操作
携帯ゲーム機は持ち歩けるので、歩きながらプレイしていて事故や犯罪に巻き込まれる恐れを否定できません。
ゲームに夢中になっていると、周囲に意識が向かず、危険が近づいても気づけない可能性があります。
・考えられるリスク:5...のめり込み
携帯ゲーム機はどこにでも持ち歩けるため、保護者の目が届かない時間にもプレイすることが可能です。
深夜まで自室で使用して睡眠不足になるなど、健康上のリスクも考えられます。
▼ 携帯型ゲーム機を安全に使うには?
● 低学年編:まずは「ルールを守る」こと
低学年のうちは、インターネットには接続せず、純粋にゲームを楽しむような使い方からはじめることをおすすめします。
大事なのは、ともすればのめり込んでしまいがちな遊びを、どのように自制させるかということ。
親御さんもときどき一緒に遊んでみるなどして、お子さんの気持ちの理解に努めましょう。
遊んでいる子どもを放っておかないようにしてください。
~低学年のお子さんのためにできる対策~
(1) インターネット接続を禁止にする
(2) 取扱説明書をよく読み、ペアレンタルコントロールを適切におこなう
(3) 利用時間や利用場所を決める
(4) 子どものゲーム中は保護者が見守る
(5) 約束を破ったときには遊ばせない
● 高学年編:自ら考えさせる
いろいろなことに興味が広がる高学年になると、押さえつけるだけのペアレンタルコントロールは通用しなくなってきます。
友達から情報を聞いて、大人も知らないような使い方をしたり、勝手にゲーム機の端末設定を変更したりしてしまうことも。
所有している携帯ゲーム機でやってもいいこと、やってはいけないことは何か、お子さんに問いかけて考えさせ、一緒に安全な使い方を話し合いましょう。
~高学年のお子さんのためにできる対策~
(1) 取扱説明書を保護者がきちんと読み、その機種で何ができるのかを知る
(2) レーティングやフィルタリングなどのペアレンタルコントロール設定を適切におこなう
(3) 各種設定に必要な暗証番号、決済カードの番号などの重要情報を絶対に教えない
(4) お子さんの成長に応じて利用時間や利用場所を決める
(5) お子さんのゲーム機を定期的にチェックする
(6) 実際にあった事件をもとに、どうすればいいかを話し合う
* * * * * * * * *
買い与えた後、子ども任せにしないことが大切です。
ペアレンタルコントロールを適切に行って、安全で楽しい遊び方ができるようにしてあげてください。2017.01.12

































