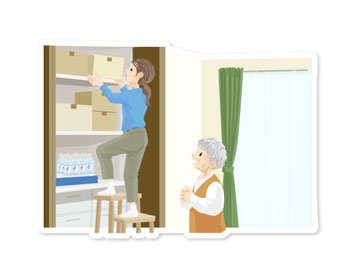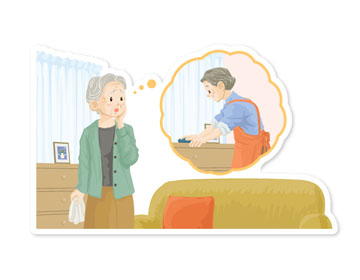こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 認知症と向きあう日々には、不安や戸惑いがつきもの。
認知症と向きあう日々には、不安や戸惑いがつきもの。
だからこそ、笑いあえる瞬間があると、心がふっと軽くなります。
介護を「完璧にやらなければ」と思い詰めすぎず、ときには笑って、グチをこぼして、誰かと分かちあえる関係を。
認知症とともに暮らす社会に必要なのは、そのような「ゆるやかな共生」かもしれません。
【あわせて読みたい!シリーズ「認知症と共に」】
・認知症と「共に生きる社会」とは
・「予防から共生へ」認知症基本法が示す新しい社会のかたち
・認知症になっても「わたしのことを、わたし抜きに決めないでください」
・認知症介護にポジティブプランの考え方を
・認知症の「2つの空白」とは?
・「私が大切にしたいこと」は何?自分の意思を残す意味
●深刻になりすぎず、「笑い」で人とつながる
認知症の人と暮らしていると、予想外のできごとに出会うものです。
たとえば、冷蔵庫に牛乳がぎっしり何本も入っている、犬用のごはん皿に食事をよそって出してくれた...そんなエピソードが多々あることでしょう。
もちろんご家族としては困ったこととうんざりすることでしょう。
でもちょっと視点を変えて「笑い話」にすると心がやわらぐもの。
「ちょっと聞いてよ...」と話せる相手がいると、困ったできごとでも笑いに変えることができるはずです。
家族だけでなく、ケアマネジャーやヘルパー、信頼できる友人など、笑いあえる相手に心当たりはありませんか?
●「当たり前じゃなくていい」認知症介護のあり方
「どうしてこうなるの?」と戸惑い続けるより、「今のこの人」をそのまま受け止める。
これも認知症の人との暮らし、共生には欠かせない視点です。
たとえば、入れ歯が炊飯器にある、廊下に靴が揃えて置かれている...そんな「不可解な行動」にも、意味があるのかもしれません。
「片付けたつもりだった」「忘れないようにここに置いた」というなど、その人なりの理由や背景があるものです。
「ダメじゃない!」「やめて!」と厳しく注意しても、認知症の方の症状や行動は改善しません。
本人を変えることはできなくても、「そうきたか!」と笑い飛ばしてしまうことはできます。
それならばイライラするのではなく、後日、誰かに話す「話題」のひとつとして心にメモを残す。
こんな視点の切り替えで、世の中の見え方はずいぶん変わるものです。
以前、幼かった姪にあんまんを「チンして食べなさい」とあげたところ、彼女は仏壇にあんまんを持っていき、仏具の鐘を「チーン」とリン棒で叩き合掌して食べました。
私は電子レンジで温めるよう言ったつもりが、彼女の「チン」は仏壇のご先祖様に感謝を伝えることでした。
このように、人には何歳でもどのような状況になっても、行動にはその人なりの意味があることを理解していきたいですね。
笑顔は、不安な気持ちでいることが多い認知症の方に安心をもたらします。
やさしい表情は、言葉以上に気持ちを届けてくれます。
困ったエピソードも笑いに変えることで、介護する側の心はもちろん、本人の気持ちもほぐしてくれるのです。
●共に笑えるから、共に暮らせる
認知症基本法には、「認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って暮らせる社会」という理念が明記されています。
「共生」は、どちらか一方が無理をして成立するものではありません。
本人も、家族も、介護者も、完璧じゃなくて良いのです。背負いすぎなくて良いのです。
困ったことでも笑えるユーモアや寛容さが共生につながると私は思います。
笑いあえる環境、社会こそが認知症と共にある未来のかたちなのかもしれません。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■認知症の方への対応で困っている介護家族に伝えたいこと?
いくら説明してもわかってもらえない、やってほしくないことを繰り返される。
認知症の方のお世話で息が詰まったときに気持ちを軽く、ラクにするコツを紹介しています。
■なぜそんなことをするの?「認知症」の方の行動と対応
認知症の方の不可解な行動や困った行動には、必ず本人なりの理由があります。
認知症の方が感じている不安や混乱を読み解き、穏やかな気持ちに導く方法をまとめています。
2025.07.22