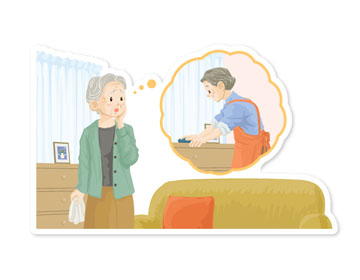こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 高齢者にとって、夜間のトイレは転倒事故のリスクが高い時間帯です。
高齢者にとって、夜間のトイレは転倒事故のリスクが高い時間帯です。
転倒のリスクをできるだけ減らすにはどうしたら良いのか?
家庭での安全対策について考えてみましょう。
●夜間のトイレは、なぜ危ない?
年齢を重ねると、ちょっとしたことで転びやすくなるもの。
特に夜中にトイレへ向かうときは、思っている以上に体がふらつきやすく危険です。
寝ていた体はすぐには動けません。
血圧や脳の働きが追いつかず、足腰もしっかり動かないまま立ち上がってしまうと、覚醒(かくせい)時より転倒リスクはさらに高まります。
そのうえ暗くて視界が悪く、通路やトイレにある小さな段差や障害物に気づきにくいのです。
「歩ける」と思っていても、寝起きの高齢者の体は、昼間とは違います。
夜のトイレは、転倒のリスクが特に高くなる時間帯。
だからこそ、家庭内でも「夜のトイレの安全」に目を向けることが大切なのです。
●家庭でできる「夜のトイレ」の転倒防止対策
高齢になると「夜間頻尿」といって、就寝中に何度もトイレに行きたくなる人が多くなります。
体内リズムの変化や膀胱(ぼうこう)の機能低下により、尿意を感じる回数が増えて、眠りが浅くなり、就寝中に何度も起きることが当たり前になっている方も少なくありません。
「誰の助けも借りずに夜中、ひとりでトイレに行きたい」という思いがあるなら、住環境を少しだけ見直してみましょう。
・寝室をトイレに近い部屋にする
移動距離が短ければ、足元のふらつきや転倒のリスクも少なくなります。
・トイレまでの動線上に障害物を置かない
足が引っかかりやすい絨毯やラグ、コード類など、つまずきの原因になりそうなものは撤去を。
・人感センサー付きの常夜灯や足元灯を設置する
暗がりでも目をこらさず歩け、眠気を妨げにくいやさしい光を選ぶのがおすすめです。
・ベッドの高さや位置を調整する
立ち上がりやすく、トイレに行きやすい位置関係を工夫しましょう。
ベッドにサイドレールがあると、つかまることで起き上がりや立ち上がりもスムーズです。
・手すりや、つかまれる家具を動線上に設置する
手すりに限らず家具などちょっとつかまれる場所があるだけで、歩行の安定感が違います。
ただし、キャスターの付いたものは容易に動くのでやめましょう。
・あらかじめトイレのドアや便座の「ふた」を開けておく
身体を引いたりかわしたりする動作は転倒リスクが高いです。
余計な動作をなるべく減らしましょう。
どれも特別な設備を用意しなくてもできる、「転ばないための工夫」です。
できることから取り入れてみてください。
●転倒後の「起き上がる力」も備えておく
注意していても、転倒のリスクをゼロにすることはできません。
だからこそ、「転ばないための工夫」とあわせて、「転んでも大きなけがにつながらない」ための備えも大切です。
そのひとつが寝返りや起き上がりの練習です。
高齢になると、布団やベッドから体をひねって起き上がる動作が難しくなります。
「自分だけで起き上がる力」を維持しておくには、手足の可動域の広さやバランスを崩したときに体を支える筋力が必要です。
手足の可動域を保つにはストレッチが効果的になります。
作業療法士や理学療法士など、専門職のアドバイスを受けながら取り組むのがおすすめです。
訪問リハビリのあるサービスや、通い慣れたデイサービスなどに相談すると、本人に合った「起き上がり」の方法を提案してもらえることもあります。
夜間のトイレを「ゼロリスク」にするのは難しいからこそ、「できることは対応した」と思える備えをしておくことが大切です。
本人と一緒に安全対策を重ねたうえで、あとは本人に任せる。
その安心感が、介護する人の心と体を守ることにもつながるはずです。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■転倒事故を防ぐために介護家族ができること
ひとくちに「高齢者の転倒」と言っても、転び方や転びやすい状況は人それぞれ違います。
転倒リスクを減らす生活スタイルについてまとめました。
■介護家族が知っておきたい、転倒事故が起きたときの対処
どれほど注意していても、転倒事故は起きてしまうもの。
大切なのは転倒後の対処です。
慌てないために、介護家族が知っておきたいポイントを紹介します。
2025.09.24