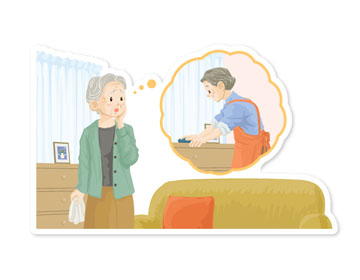こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 加齢とともにこれまでできていたことが「ちょっと難しい」「ちょっと億劫(おっくう)」に変わっていくものです。
加齢とともにこれまでできていたことが「ちょっと難しい」「ちょっと億劫(おっくう)」に変わっていくものです。
親の変化を目の当たりにすると手を貸してあげたくなります。
でも、その手助けが本人の「できる力」を奪ってしまうかもしれません。
「できなくなってきた親」の「まだできる力」を支えるためのかかわり方を考えましょう。
●「できない」「やらない」が増える高齢者のリアル
内閣府の「高齢者の健康に関する調査」によると、「できない」「できるがしていない」と答えた割合が多い活動として、「自分で食事を用意する」「15分くらい続けて歩く」「自分で食品・日用品の買い物をする」といった行為が並んでいます。
これまでは当たり前だった動作も加齢によって負担がかかるものです。
「転ぶのが怖い」「腕が上がらない」「すぐに疲れる」など、体力や身体機能の低下を実感するようになると「できる」ことも「やらない」という選択に変わっていきます。
かつては「毎日欠かさなかった」入浴や料理など、生活に必要だった行為でさえも、「今日はいいや」「買ってきたもので済ませよう」と頻度が減ったり、習慣自体がなくなってしまったりするケースも少なくありません。
怠けているのではありません。
「気力や体力の衰え」や「失敗への不安」といった高齢期特有の気持ちの変化です。
「まだまだ元気そう」に見えても、生活スタイルが変わりつつあるのかもしれません。
●「やってあげる」ことが、やる気を奪うこともある
加齢で体力が衰え、若いときのようにはできないことが増えるのは自然なことです。
でも、だからといって、家族が何でもやってあげるのが正解とは限りません。
たとえば、手先が少し不自由になっても、本人が自分で服のボタンをとめようとしている。
少し時間はかかっても、自分の手でできた達成感は、その人の自信や生活意欲につながります。
「やってあげるよ」と代わってしまえば、「自分で行う」という意欲が損なわれてしまうかもしれません。
安全面の配慮は欠かせません。
でも、まだできることまで「やってもらう」のが当たり前になると、やる気や自信は簡単に失われてしまうものです。
本人が少しずつ自信をなくし、「何もかもが億劫(おっくう)だ」と感じるようになると、生活全体が縮こまり、閉じこもりがちになってしまうこともあります。
体を動かさないだけでなく、気持ちまでふさがっていくことになりかねません。
家族に必要なのは「やってあげる」より、「やろうとしていることをそっと見守る」こと。
その姿勢が、親の「できる」を守り、「やる気」をつなぐ支えになるのではないでしょうか。
●高齢者が「できることを続ける」ためのかかわり方とは
親に対して、できる支援とは「何でもやってあげる」ことでも、「自分でやって」と突き放すことでもありません。
大切なのは、今の状態をよく観察しながら「できること」と「任せるのが危ないこと」を冷静に見極めること。
たとえば、重いものを持ち運んだり、高いところにあるものをおろしたりする動作は、転倒やけがのリスクがともないます。
一方で、台所に立って自分のペースで一品を仕上げるといった動作は、生活のなかでの役割や気力につながる大切な営みです。
「できるか」「誰かにやってもらいたいか」は本人にしかわからないことも多いもの。
「できること」と「任せることが危ないこと」の認識に違いがあるのもよくあること。
何かをやろうとしているときに、「手伝おうか?」のひと言を添えるだけでも、本人の意向やペースを尊重することができます。
最近は、家事や日常動作の負担を減らす便利グッズもたくさんあります。
たとえば、ペットボトルのふたを簡単に開けられるグッズや電子レンジで、魚や目玉焼きが焼ける調理器具など。
離れた場所のものをつかめるような「手」なども、高齢者や要介護者でよく使われているアイテムのひとつです。
「これを使えばまだ自分でできる」「ラクになった」と思える手段があれば、意欲や生活の自立性が保てます。
「支える」とは、前に出て主導することではなく、後ろからそっと力を添えること。
安心して「本人らしい暮らし」を続けられるよう、ちょうど良い距離でかかわっていきたいですね。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■高齢の親との同居は何が大変?よくある「すれ違い」の解消法
「できなくなってきた」親の暮らしぶりがもどかしく感じることもあります。
自立とサポートのちょうど良いかかわり方と、自分の心を守るヒントをまとめました。
■認知症介護にポジティブプランの考え方を
認知症になっても、本人にできることはたくさんあります。
失敗やできないことに目を向けるのではなく、できることを見つけて「意欲」を引き出す新しい考え方を紹介します。
2025.08.12