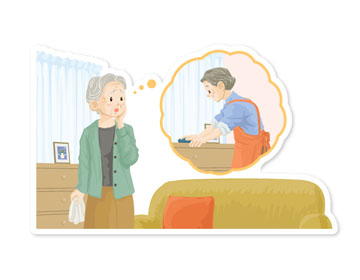こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 「認知症」は、どこか遠い世界の出来事ではありません。
「認知症」は、どこか遠い世界の出来事ではありません。
地域のなかで、家族のなかで、認知症と共に暮らす人たちが、私たちのすぐそばにいます。
いずれは自分自身や大切な家族が、認知症と向き合うことになるかもしれません。
認知症は「特別なこと」ではありません。
誰にとっても「かかわりのあること」「当たり前のこと」といえます。
実はこの「特別ではなく、当たり前」という視点こそが、これから安心して年を重ねていくために大切です。
認知症と共に生きる社会の姿を、少しずつ一緒に考えていきましょう。
●すぐそばにいる「認知症のある人」
スーパーで買い物をしている高齢の女性が、同じ棚を何度も行き来している。
レジが行列していると思ったら、支払いがうまくできずオロオロしている人がいた。
ベンチに座ってぼんやりしているおじいさん、何時間も経つのにまだ同じ場所にいる。
日常のひとコマです。
でも、もしかしたら、その方は認知症の症状と向き合いながら、日常生活を送っているのかもしれません。
認知症は、何か特別な人に起こる病気ではありません。
高齢化が進むいま、地域のなかで、職場で、家族のなかで、認知症のある人と自然に出会うことが、当たり前になっています。
厚生労働省の推計では、2040年には65歳以上の7人に1人が認知症になると言われています。
誰もが、認知症と「無関係ではない時代」がすぐそこまで来ているのです。
●「どう関われば良いのかわからない」、そんな気持ちも自然なこと
認知症のある人に出会ったとき、どのように接すれば良いのでしょうか。
積極的に手助けをすべきか、それとも静かに見守るべきか。
戸惑いやためらいを感じたことのある方も、多いのではないでしょうか。
おそらく多くの人は、「あの人は認知症だ」と確信できるわけではありません。
むしろ、「なんだか様子がおかしいな」と感じるだけかもしれません。
「もしかしたら認知症かも」「でも、違ったら失礼かも」そのように、心のなかで迷ってしまうこともあるでしょう。
また、「自分には何もできない」「面倒なことになったら困る」と、見て見ぬふりをしてしまうこともあるかもしれません。
そんなためらいや不安を抱くのは、当然のことだと思います。
でも、「うまくできなくても大丈夫」という気持ちで、少しだけ相手に歩み寄ってみてください。
声をかけること、手を差し伸べることには、確かに勇気がいります。
けれど、もし本当に困っている認知症のある人だったとしたら、その一声が、きっと大きな助けになります。
「大丈夫ですか?」
「なにかお手伝いしましょうか?」
そんなひと言に込められた思いやりの気持ちが伝わるだけで、救われることもあるのです。
もし、自宅に戻れなくて困っているようであれば、安全な場所へ移動し、その場から近くの交番や警察署に連絡して保護をして貰うなど。
小さな行動の一歩が、「共に生きる社会」へとつながっていくのだと思います。
●認知症を「私たち自身の未来」として考えてみる
認知症は、年齢を重ねる誰にとっても起こりうるものです。
体に変化が訪れるように、脳にも変化が訪れるのは、自然なこと。
「まだ大丈夫」と思っていても、ある日突然、道に迷ってしまったり、レジで財布のお金を出すのに戸惑ったりすることがあるかもしれません。
そんなとき、見知らぬ誰かが、さりげなく声をかけてくれたら。
「お手伝いしましょうか」と、手を差し伸べてくれたら。
きっと、心強く感じるはずです。
支える側も、支えられる側も、誰もが安心していられる社会をつくること。
それは、認知症のある人のためだけでなく、未来の自分自身のためでもあります。
* * * * * * * * *
認知症は、特別な誰かの問題ではありません。
すでに私たちの暮らしのなかにあり、これからますます身近なテーマになっていきます。
認知症のある人と、私たちはどのようにかかわっていけるのか。
そして、自分自身も安心して年を重ねていける社会とはどのようなものか。
誰も経験したことがない超高齢社会を迎えるにあたって、その正解はまだわかりません。
これから少しずつ、一緒に考えていきましょう。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■在宅介護のご家族が知っておきたい「認知症」のこと
認知症理解の入門編。
認知症のことが正しくわかると、いざというときの心構えや準備につながります。
■最近なんだかヘン...?加齢とともに訪れる「心の変化」とは
高齢期特有の「変化」に対して、周囲の理解がないと認知症の発症や進行のリスクを高めてしまう可能性があります。
誰もがいつか向き合うことですので、ぜひ一読ください。
2025.04.22