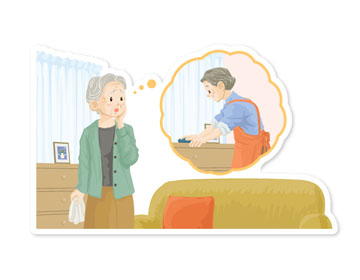こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 在宅介護をしていると親の愚痴や文句に付き合う場面も多くあるものです。
在宅介護をしていると親の愚痴や文句に付き合う場面も多くあるものです。
介護する身内に遠慮なくぶつけられる愚痴や文句が、大きな負担になります。
親に寄り添いながら、介護する側の心を守るためのかかわり方についてまとめました。
●親の愚痴や文句に疲れてしまう現実
「身体がしんどい」
「あの人が冷たい」
「自分ばかり苦労している」など
繰り返される愚痴や文句。
聞く側を疲弊します。
暗い気持ちになってしまうこともあるでしょう。
でも弱音を受け止めてくれる相手がいるから言えることでもあります。
少し言う側の立場で考えてみましょう。
●親の愚痴の裏にある本当の気持ち
高齢になると身体が思うように動かないことや、日常の不便さへの苛立ちから、不満を口にせずにはいられない場面が増えるものです。
高齢の親の愚痴は、一見ただの不平や文句に聞こえても、実はいくつかの種類があります。
「状況の改善・解決を求めているもの」「ただ聞いてほしいだけのもの」が代表例です。
【状況の改善・解決を求めているもの】
「痛みが強い」「生活に支障がある」など、具体的な対応が必要なケース。
要望が愚痴になってあらわれることがあります。繰り返されるときは改善や解決に至っていないと思われます。
実際の要望は何なのかわかりにくいこともしばしばありますが、なにかしら改善してほしいことが残されているのでしょう。
【ただ聞いてほしいだけのもの】
身体のつらさや人間関係のストレスを口にすることで、気持ちを整理しようとしているケース。
「不安が強い」「誰かに寄り添ってほしい」といった願望のようなサインであることが少なくありません。
私たち自身も、職場や家庭で「聞いてほしいだけ」の愚痴をこぼしたくなることがありますね。
高齢の親の愚痴も、それと同じ心理だと考えてみてください。
求めているのは共感と安心感なのかもしれません。
●聞き流す力を身につけて
愚痴や文句を聞き続けるのは負担です。
寄り添うことが大切とわかっていても、介護する側の身が持たないこともあるでしょう。
心を守りながら介護を続けるなら、大切なのは「どう聞くか」。
ちょっとした工夫で、相手を尊重しつつ自分の心も守る聞き方ができます。
・共感とリフレーズで返す
否定せず、そのまま言葉を返すことで共感を示すことができます。
たとえば、「腰が痛い」と言われたら、「痛いんだね、つらいね」とそのまま返す。
そのような受け答えがあると、相手は「わかってもらえた」と感じるものです。
・小さな質問で会話を終える
「ところで今日は薬を飲めた?」など、具体的で答えやすい質問を添えると、愚痴の堂々巡りを切り上げやすくなります。
・姿勢や態度で安心感を示す
体を少し相手に向ける、うなずく、柔らかい表情を心がけるなどの「姿勢」は、言葉を選ばなくても「聞いているよ」というサインになります。
スマホを見ながら聞くのとは大違いです。
・境界線を意識する
秘訣は一生懸命になり過ぎないこと。
「何とかしなければ」と思い過ぎる必要はありません。
適当に聞き流す。たまには聞いているフリだけでも構いません。その分こころやすくそばに居続けることが大切です。
「ただ聞くことが私の役割」と心のなかで線を引くと、無理に背負わずに済みます。
「聞き流す」とは冷たく突き放すことではなく、相手の気持ちを軽くする姿勢を選ぶこと。
親が「話してすっきりした」と感じ、介護者も心をすり減らさずに済む。
そんなバランスを見つけていきましょう。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■在宅介護家族のためのストレスコーピング
在宅介護にはイライラやモヤモヤがつきもの。
「ストレスを感じている自分」に気づいたら、意識的にため込んだストレスを解放する必要があります。具体的な方法をまとめました。
■在宅介護を続けていくための「心のバランスの取り方」
要介護者の「尊厳」や「意志」を尊重する大切さが語られる一方で、介護者の心や身体の不調は後回しにされがち。
「自分ファースト」で考え、行動する大切さを紹介しています。
2025.10.28