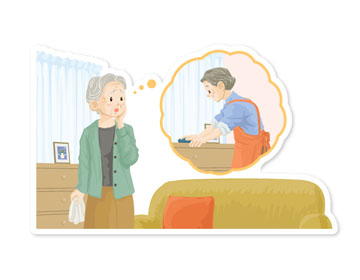こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 転倒をきっかけに、寝たきりや車いすの生活になると、「もう何もできない」「介護が大変になる」と考えがちです。「寝たきり=不幸」「歩けなくなる=介護負担が増える」と思い込んでいませんか?
転倒をきっかけに、寝たきりや車いすの生活になると、「もう何もできない」「介護が大変になる」と考えがちです。「寝たきり=不幸」「歩けなくなる=介護負担が増える」と思い込んでいませんか?
転倒は、予防しても完全に防げるものではありません。
そして、たとえ自分で歩けなくなったとしても、生活の質(QOL=クオリティ・オブ・ライフ)を向上させ、豊かに過ごす方法はあるものです。
今回は、転倒後の生活を前向きに考えるヒントをまとめます。
「歩けなくなっても、できること」は案外、多いものです。
● 「歩けなくなること」は人生の終わりではない
転倒による骨折や病気の影響で、歩行が困難になることは決してめずらしいことではありません。
車いすや寝たきりの生活になると、本人も家族も「もう今までのようには過ごせない」とつらい気持ちになると思います。
でも、「歩けなくなること=すべてを失うこと」ではありません。
実際に、寝たきりでも充実した時間を過ごしている方はたくさんいます。
大切なのは「できなくなったこと」ではなく、「今、できること」に目を向けることです。
たとえばレストランに行けなくなっても、おいしいものを食べる楽しみはなくなりません。
外食ができなくても、宅食サービスやフードデリバリー、地方のお取り寄せグルメなど、昨今はさまざまなサービスが充実しています。
「食べる楽しみ」について、あるご家族のエピソードをご紹介します。
その方のお父様は、病気の影響で寝たきりになり、食事も嚥下(えんげ)が難しくなり、普通の食事や飲み物は食べられなくなりました。
以前はお酒が大好きだったけれど、もう飲むことはできない...そう思っていたそうです。
でも、ご家族は考えました。
「大好きだったお酒をゼリーにしたら、食べられるのでは?」
お酒をゼリー状にしてみたところ、お父様は心から嬉しそうに召しあがったといいます。
「本人がまだできること」や「家族がやってあげたいこと」に目を向ければ、歩けなくなっても、その人らしい楽しみ方がきっと見つかるはずです。
● QOLを高めるためにできること
「歩けなくなったら、生活の質は下がる」と思われがちですが少しの工夫で、寝たきりでも、その人らしい暮らしを続けることができます。
・ケース1:食事の楽しみを大切にする
食べることは、日々の喜びに直結しています。
たとえ飲み込みが難しくなっても、ゼリーやムースなどにすれば、栄養には足りませんが好きな味を楽しむことは可能です。
ステキな器を使って盛り付けを工夫したり、懐かしい味を取り入れたりすれば、気持ちもあかるくなるかもしれません。
食卓につくのが難しければ、ベッドサイドで一緒に食事をすれば良いのです。
フードデリバリーや地方のお取り寄せグルメなどを利用して、たまに贅沢な食事を演出することもおススメです。
食事の時間を家族との楽しいひとときにすることで、食事が単なる栄養補給ではなく、生活の彩りのひとつになります。
・ケース2:文化的な楽しみを取り入れる
身体が動かなくても、心を豊かにする方法はあります。
好きな音楽を聴いたり、落語を楽しんだりすることは可能です。
読書が好きならオーディオブックや朗読も良いでしょう。
外出が難しくても、タブレットで映画や旅行番組を観たり、美術館や博物館のオンラインツアーを楽しんだりすることもできます。
好きなものに触れる時間を意識的につくれば、気持ちにハリが生まれ、日々の充実感につながるはずです。
・ケース3:人とのつながりを続ける
寝たきりになると、人と会う機会が減りがちですが、会話は心の健康を支える大切な要素です。
友人に来てもらったり、電話やオンラインツールを活用したりすることで、人との交流を保つことはできます。
たとえ短い時間でも、人と話すことで気持ちがあかるくなり、日々の楽しみが増えるでしょう。
・ケース4:部屋のなかで季節を楽しむ
環境を工夫することで、室内にいても季節の移り変わりや外の景色を感じることができます。
たとえば、ベッドの向きを変えて窓から外の風景が見えるようにするだけでも気分は変わるはず。
季節の花を飾ったり、好きな香りのアロマを取り入れたりすると、五感が刺激されます。
外出が難しくても、自然や四季を感じる工夫をすることで、日常に小さな喜びを見つけることができるでしょう。
● 「介護負担が増える」と思い込まないで
「歩けなくなると、家族の負担が増えてしまう」と思うかもしれません。
確かに、これまでできていたことが難しくなれば、介助が必要になる場面も増えます。
ですが、「負担が増える」という思い込みが、必要以上に不安を大きくしてしまうこともあります。
たとえば、トイレについて。
失敗が増えると、家族は介助しなければならなくなり、負担は増えます。
また、実はトイレ介助で一番大変なのは、トイレまでの移動や移乗、ズボンなどの上げ下げになります。
でも、おむつを使用すれば介護の負担は軽減されるはずです。
「できるだけ歩く力を保たせたい」「トイレまで行かせたい」と思う気持ちも大切ですが、無理をするよりも、今の身体の状態にあった方法を選ぶことで、介護する方もされる方もラクになることもあります。
また介護する側がすべてを抱え込まなくても良い方法を考えることも大切です。
公的な介護サービスが充実している今、介護負担を減らす方法はいろいろあります。
・訪問介護や訪問看護を活用し、専門家の手を借りる
・リフトや体位変換器などの福祉用具を取り入れる
・デイサービスやショートステイを増やす
「家族がすべてやらなければならない」という考えを手放せば、介護する側もされる側も、もっと前向きに暮らせるはずです。
無理をせず「どうすれば快適に過ごせるか」を考えることが、より良い介護につながるのではないでしょうか。
* * * * * * * * *
大切なのは、「できないこと」ではなく、「今、できること」に目を向けること。
介護する側も、本人が「何をしたいのか」を知り、「それはどのような方法でしてあげられるか」 を考えることで、前向きな気持ちになれるはずです。
「立てなくなる」「歩けなくなる」ことに絶望せず、自分たちなりの幸せの価値を見つけてください。
【あわせて読みたい!シリーズ「転倒」】
・高齢者の転倒と「老年症候群」とは
・介護家族が考えておきたい「転倒後」のこと
・転倒事例から考える「転ぶ意味」
【あわせて読みたい!関連コラム】
■寝たきりで意思疎通困難でも口から食べられるようになる、「胃ろうが介護家族にくれたもの」
「10年胃ろう栄養だけ」でも、再び口から食事を楽しめるようになったエピソード。
どんな状況になっても人生を楽しむためのヒントが詰まっています。
■外出することをあきらめない
どんな身体状態でも、どんな住環境でも外出することは可能です。
訪問看護師としてたくさんの外出支援をしてきた経験も交えながら、寝たきりの方の外出について紹介しています。
2025.04.08