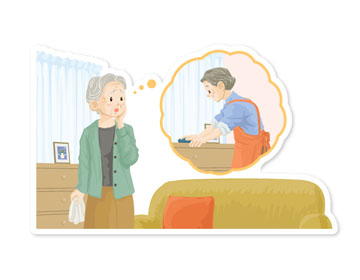こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 高齢者の転倒は「老年症候群」のひとつと言えます。
高齢者の転倒は「老年症候群」のひとつと言えます。
誰のせいでもなく、誰にでも起こりうることです。
高齢者の転倒は避けられないことですが、実際に転倒してしまったらどうするのか?
大切なのは「転倒後」のことです。
転倒後に備えておくべきポイントを具体的にまとめます。
● 転倒後に起こりうるリスクを知る
高齢者の転倒は、ただのすり傷や打撲だけでは済まない場合があります。
その後の生活や介護の負担に影響することも少なくありません。
特に注意したいのが、大腿(だいたい)骨(太ももの付け根の骨)の骨折や転倒時に頭を打つ頭部外傷です。
<大腿骨骨折のリスクについて>
・寝たきりのリスクが高まる
・手術が必要な場合が多いが、年齢や健康状態によっては難しいこともある
・回復までに時間がかかり、リハビリ必須
大腿(だいたい)骨の骨折は、高齢者の転倒による骨折のなかでも特に多く、そのまま寝たきりにつながることも少なくなくありません。
特に認知症があると術後の安静やリハビリの受け入れがうまくいかず、なかなか良い経過をたどれないことがあります。
また手術を受けるかどうかの判断には、年齢、持病、服薬状況などがかかわります。
事前にご本人と家族、かかりつけ医と話しあっておくことが大切です。
<頭部外傷のリスクについて>
・意識がはっきりしていて異常がなくても、時間が経ってから症状が出ることがある
・特に血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を服用している人は、脳出血のリスクが高まる
頭を強く打った場合、直後はなんともなくても、数時間後、数日後に脳内出血の症状がでるケースがあります。
特に抗凝固薬(ワーファリン、バイアスピリンなど)を服用している人は出血が止まりにくいので、危険な状態に陥る可能性も否定できません。
転倒時に頭を打ったら、平気そうに見えても、必ず医師に相談してください。
● 手術をするか否か?かかりつけ医と相談しておく
高齢者が転倒して骨折すると、ほとんどの場合は手術が必要になります。
ただし、すべての人が手術を受けられるわけではありません。
年齢や健康状態によっては、身体に負担がかかりすぎるため、手術が難しいこともあります。
<手術をするかどうかの判断基準>
・ご本人の身体の状態
年を重ねると、心臓や肺の働きが衰えて、麻酔や手術の負担に耐えられない場合があります。
また、持病があると手術後の回復に時間がかかることもあるため、慎重な検討が必要です。
・服薬の影響
特に血液をサラサラにする抗凝固薬を服用している場合、手術中に出血しやすくなる、出血が止まりにくいといったリスクがあります。医師と相談しながら進めると良いでしょう。
・ご本人の意思
骨折した場合、手術を望むのか、その後はどんな生活をしたいのかなど、ご本人の気持ちを確認しておく必要があります。
これらを踏まえて、手術の可否をかかりつけ医と話しあっておきましょう。
手術が難しい場合は、ギプス固定などの保存療法や痛みのケアを中心にする選択肢もあります。
手術しない場合、どんなリスクがあるのか、予後(病気・手術などの見通し)はどうなるのかなども聞いてみてください。
高齢者の骨折は、手術をするにしても、しないにしても、長い安静期間が必要です。
リハビリには根気と時間を要します。
かかりつけ医と話して状況を理解することで、転倒に対する心構えができるはすです。
「そうなったら嫌だから、もっと慎重になろう」とご本人の意識が変わることもあります。
大事なのは、転倒後に慌てずに判断できるように「今のうちから考えておく」ことなのです。
●転倒後の「生活の変化」にどう対応するのかを考えておく
転倒は、一度起こるとその後の生活が大きく変わることがあります。
骨折やケガによって、これまで当たり前にできていたことが難しくなるかもしれません。
「もう歩けないのか」「自宅での生活は続けられるのか」といった不安も出てくるでしょう。
だからこそ、「もしものときにどうするか?」を事前に考えておくことが大切です。
たとえば、退院後も自宅で暮らしたいなら、手すりの設置、歩行器や車いすの準備、訪問介護やリハビリが必要になるでしょう。
一時的に施設でリハビリを受ける選択や、将来的な介護施設の利用について情報を集めておくと安心です。
また、介護する家族の負担も増える可能性があります。
たとえば、トイレや入浴の介助、移動のサポートが必要になることも。
一方で骨折により動けなくなった分、介護負担が減ることもあります。
トイレで排泄介助するより、ベッド上でおむつ交換する方が楽といった場合です。
どちらにしても介護のパターンを変更する必要がでてきます。
誰がどのように介護にあたるのか、家族がその時間を捻出できるのかなど、今の生活状況に応じたシミュレーションが必要です。
すべてを家族だけで抱え込むのは大変なので、訪問介護やデイサービスの利用頻度を増やすことなども考えておきましょう。
そして何より大切なのは、本人の気持ちを尊重すること。
「どこで暮らしたいか?」
「どのように過ごしたいか?」
「どんな治療を希望するか?」
そんな話を今のうちにしておくことで、転倒後も本人らしい生活を続けるための選択ができるはずです。
* * * * * * * * *
「転ばないようにする」ことも大事ですが、「転倒後も、その人らしい生活を続けるための準備」 をしておくことが、本人にとっても家族にとっても安心につながります。
転倒による生活の変化を必要以上に怖がらず、今からできる備えをしておきましょう。
【あわせて読みたい!シリーズ「高齢者の転倒」】
・高齢者の転倒と「老年症候群」とは
【あわせて読みたい!関連コラム】
■介護家族が知っておきたい、転倒事故が起きたときの対処
いざ転倒事故が起きたとき、いちばん大切なのはその直後の対処です。
転倒事故が発生しても、慌てないために知っておきたいポイントを紹介します。
■高齢者の転倒事故は「転んだあとの備え」が肝心
「転んだあとに起きあがれない」「転んだことを誰にも気づいてもらえない」というリスクもあります。
こうした「悪い事態」を回避するためのポイントをまとめています。
2025.03.11