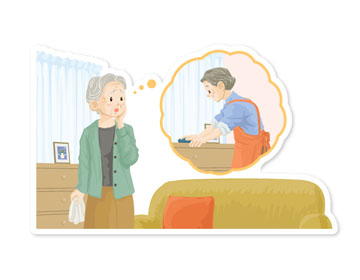こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 「転倒=危険」
「転倒=危険」
「転ばせてはいけない」
介護をするうえで、誰もがそう考えるものです。
もちろん、転倒によるケガや骨折を防ぐことは大切。
でも、転倒には意味があります。
転びやすくなった人に「危ないからひとりで歩き回るのはやめて」と言うのは簡単です。
でも、本当にそれで良いのでしょうか?
転倒をきっかけに、本人が自分の身体と向き合うようになることは少なくありません。
転倒に対して介護する家族は、どう向き合うべきか、どう受け止めるべきかをまとめます。
● 「転倒が増えた」そのとき、人は何を思うのか
「転倒してしまった」
「転倒が増えた」
そのとき本人は何を感じているのでしょうか?
どのように自覚しているのでしょうか?
ある高齢男性のケースです。
男性は、何度も転倒を繰り返していました。
男性はしっかり者です。
自分の身体が弱ってきていることを自覚していました。
それでも、周囲のサポートや介護サービスを強く拒みます。
できる限り自分の力で生活しようとしていました。
男性の介護にあたる家族からすれば「これ以上転んだら危ない」「もっとサポートを受けてほしい」と思うところです。
でも本人からすれば、自分の行動には意味があります。
「まだ自分でできる」ことの確認。それがこの男性がひとりで歩く意味でした。
「もう危ないから、誰かの手を借りたほうが良い」と言われても、すぐに受け入れられないものです。
人は、老いや衰えを少しずつ実感します。
自分で納得するには時間がかかるものです。
実際この男性は、何度か転倒を繰り返したあと「納得」して、介護サービスを受け入れました。
転倒を繰り返す自分と、老いと衰え。
「転倒」を肯定しているわけではありませんが、転倒が自分と向き合うための大切なプロセスになったということです。
介護する側は「転ばせたくない」と思う。
それは当然のこと。
でも、転倒という出来事にも意味があるかもしれないことを知っておいてほしいと思います。
● 本人の意思を尊重することの大切さ
在宅介護をしていると、「転ぶことが増えたから、そろそろ施設を考えたほうが良いのでは?」「デイサービスを増やしたほうが良いのでは?」と考えることがあるかもしれません。
でもその判断、誰のための検討でしょうか。
もちろん、危険を放置することはできません。
でも転倒を繰り返してでも「自分の力で動きたい」と思う人もいます。
転ぶことが増えたので「もう限界だ」と納得する人もいます。
「転ぶと大変なことになるよ」と介護する側は思うものです。
でも転ぶ前に「歩いていきたい」という気持ちに意味があるのかもしれません。
転倒しそうになっても歩きたい、動きたいという意思にどんな意味があるのか考えてみてください。
本人にとって転倒することは、自分の身体との対話かもしれないし、転倒してもひとりで頑張っている勲章かもしれません。
少し想像してみると、別の視点で転倒と向き合えると思います。
「誰にとっての安心なのか?」
「本当にそれを本人が望んでいるのか?」
こんな視点を持つことが大切です。
● 「自分で歩く権利」と「転倒」
転倒を防ぎたいと思うのは、介護する側として当然の気持ちです。
でも、それが本人の気持ちと一致しているとは限りません。
手厚いケアやサポートが、必ずしも本人の望むものではないこともあります。
転倒を繰り返してでも、自分の力で動き続けたいと考える人もいれば、「まだ大丈夫」と自分を励ましながら、これまでと同じように過ごしたいと願う人もいます。
ぜひ本人が「どうしたいのか」に耳を傾けてあげてください。
「どうしたいの?」と問いかけることが大切です。
今の自分の精一杯を使って歩くなかで、「そろそろ支えが必要かもしれない」と本人が感じるタイミングがあるかもしれません。
そうなってはじめて、介護サービスを受け入れる気持ちになることもあります。
まずは、安全対策を整えつつ、できる範囲で本人の「まだやりたい」という意欲を支えることが大切です。
手すり、歩行器や杖、転倒時の衝撃を軽減するズボンなど、歩行の安全性を高める福祉用具も介護サービスの一つとして活用ができます。
「これを使ったほうが良い」と押しつけるのではなく、「歩くときにラクみたいだから、ちょっと試してみる?」と声をかければ受け入れてくれるかもしれません。
福祉用具業者も事前に相談すると、杖などをお試し期間を設けて貸してくれるところもあります。
転倒を防ぐことは大切です。
でも転倒を避けることだけを優先すると、本人の気持ちとのギャップが生じます。
介護する側の「転ばせたくない」、本人の「まだ自分でやりたい」「人の手を借りたくない」。
そのバランスをどう取るかが、在宅介護ではとても大切な視点です。
* * * * * * * * *
「危ないから」「時間がかかるから」という理由で行動や生活を制限したり、先回りしてやってしまったりすることで、本人らしさやできる意欲、やれる自信を奪ってしまうことがあります。
これは「歩く自由」に限ったことではありません。
着替えの手伝いや、食事介助など、日常のさまざま場面にあてはまることです。
「危険を防ぐ」ことと「その人らしい生活を守る」こと。
どちらも大切だからこそ試行錯誤しながら考えていけたらと思います。
日々の介護を見つめ直すきっかけになれば幸いです。
【あわせて読みたい!シリーズ「高齢者の転倒」】
・高齢者の転倒と「老年症候群」とは
・介護家族が考えておきたい「転倒後」のこと
【あわせて読みたい!関連コラム】
■転倒事故は誰のせいでもない!在宅介護で「歩く自由」を奪わないために
もしあなたが、「転んだら大変」といちいち手を出されたり、外に出るのをとがめられたりしたら、どう感じますか?
介助や声かけがどうすべきか、考えるきっかけになるコラムです。
■車いすは使うべき?移動や歩行をサポートする福祉用具との付き合い方
必要に応じて車いすを使うことで、移動の自由や自立度が広がることもあります。
「今はまだ歩けているけれど」という方も、いずれ来るかもしれない日のためにぜひ読んでみてください。
2025.03.25