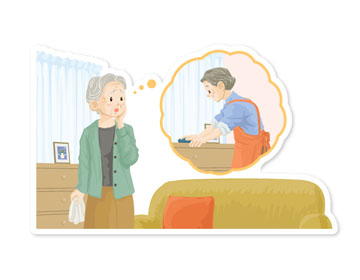こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 3年ごとにおこなわれる介護報酬改定。
3年ごとにおこなわれる介護報酬改定。
「介護報酬」は介護サービス事業者にとっての指針です。
介護報酬の改定でサービス内容や提供体制が変わることもあります。
日々の介護の質や利用者の生活に影響を及ぼすこともあるでしょう。
介護報酬改定は、ご本人や介護家族にも大きくかかわるものなのです。
今回は、2024年度の介護報酬改定のポイントをまとめました。
介護報酬の改定内容を大まかにでも理解できると、これからの社会や在宅介護がどのように変わっていくかが見えてきます。
● 介護報酬改定はなぜ必要なのか
急速に高齢者人口が増加している日本。
団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」が社会的な課題になっています。
労働人口が減少するなか、高齢者の増加により、医療や介護の需要は高まる一方。
社会保障費の増大や医療・介護人材の不足により、需要と供給のバランス具合は国民全体に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
介護報酬の改定が3年ごとにおこなわれているのは、こうした社会背景の変化に対応するため。
高齢化が進むだけではなく、技術の進化や物価の変化、介護ニーズの多様化など、社会環境や需要が変わるスピードは急速です。
介護にかかる費用や必要とされる介護サービスも変化しています。
これらに対応するために、3年という短い間隔で「介護報酬」の見直しがおこなわれます。
世の中の変化にあわせて介護報酬を適切に設定し、持続可能な体制づくりや財政運営を確保しているのです。
定期的に介護報酬を見直すことによって、限られた国の予算をうまく使い、誰もが安心して年を重ねていける社会をつくる。これが介護報酬改定の狙いです。
介護保険は民間のサービスではありません。
保険料・公費・利用者負担で支えあい、高齢社会を維持するための制度です。
介護サービスの利用者も、介護保険制度を支える一員であることを理解しましょう。
● 2024年度の介護報酬改定はどこが変わった?
3年ごとの介護報酬の改定では、介護保険の趣旨や社会状況にあわせて、「加算」と「減算」の対象が調整されます。
「使っているサービスは同じなのに、自己負担額が増えた」というケースのほとんどは、介護報酬の改定によるものです。
介護報酬がどのような方針で改定されているのかを知ると、自己負担増の理由や、今後の在宅介護がどう変わっていくのかが見えてきます。
2024年度の介護報酬改定は、2021年度の改定から大きな変化はありません。
今回の改定は、前回の改定で示された課題への対応を、さらに強化するものになっています。
改定で示された「4つの柱」に沿って、主な変更点をまとめます。
(1)地域包括ケアシステムの深化と拡充
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で疾病を抱えても最後まで安心して暮らせるよう、認知症に対応できる人材の育成や、自宅での看取りについて、自助、互助、公助、すべての面から町ぐるみで充実を図るもの。
2021年の改定では、そのために必要な医療と介護サービスの連携強化が図られました。
・ココがポイント!2024年度改定の変更点
地域での支えあいをさらに強化するための施策が拡充されています。
認知症や単身高齢者、医療ニーズの高い中重度の高齢者も含め、地域のニーズにあわせた柔軟なサービス提供の取り組みなど、住み慣れた地域で安心して暮らせる体制が強化されました。
(2)自立支援と重度化防止に向けた対応
住み慣れた家で自分らしく生活するため、自立支援や健康寿命の延伸に注力しています。2021年の改定では、データベースシステム(科学的介護情報システム)へのデータ提供やデータ活用の取り組み、リハビリ・機能訓練、口腔(こうくう)ケア、栄養管理の取り組みが提示されました。
・ココがポイント!2024年度改定の変更点
自立支援に加えて、重度化防止に向けた対応がより強化されました。
より具体的な自立支援プログラムの導入や、状態悪化を防ぐための新しい取り組みも加わっています。
特に「リハビリ・口腔(こうくう)・栄養」の一体的な取り組みのために、通所リハビリテーションや口腔(こうくう)管理、栄養指導などの取り組みを評価する指標が改善され、報酬改定に反映されています。
(3)働きやすい職場づくりの推進
人手不足が著しい介護業界で介護サービスのさらなる充実を図るため、介護職員の処遇改善や業務効率化が喫緊の課題になっています。
2021年の改定では、介護職員の働きやすさ向上や人材確保の実現に向けて、賃金改善のための加算や、業務負担軽減のためのICT(情報通信技術)活用の推進などが提示されました。
・ココがポイント!2024年度改定の変更点
「働きやすい職場づくり」に向けた施策がさらに進化しました。
特に長年の課題である介護職員の賃金引き上げについては、確実にベースアップにつながるよう加算条件の整理や加算率の引き上げがおこなわれ、介護職員の負担軽減策を検討するための委員会の設置も義務付けられました。
介護ロボットやICTの活用についての新たな加算も設けられ、介護職員が長く働き続けられる環境を整えようとしています。
(4)制度の安定性と持続可能性の確保
少子高齢化で今後ますます介護保険の維持が難しくなることが見込まれるため、必要なサービスを確保しつつ、ムダを減らしていくことが重視されています。
2021年度の改定では、利用者の公平性やサービスの機能強化を図る観点から基本報酬や加算の見直しなどがおこなわれました。
・ココがポイント!2024年度改定の変更点
介護保険制度の安定性と持続可能性の確保のため、介護業務の手間やコストに対する評価の適性化や重点化がおこなわれています。
報酬が整理・簡素化されたことで、国が力を入れたい項目がよりクリアになり、介護保険が今後も持続するための基盤が強化されています。
● 介護報酬改定から見える日本の未来
介護報酬改定は、介護サービスの向上や介護保険制度の維持を目的におこなわれますが、そこにはいろいろな意味が込められています。
俯瞰してみると、日本という国が目指す「未来」の姿が描かれているようにも見えます。
たとえば、自立支援や重度化防止の取り組み強化は、心身の健康に直結するものです。
高齢者のADL(日常生活動作)はもちろん、QOL(生活の質)も底上げしていくことが狙いでしょう。
特に、今回の改定の重点ポイントのひとつである「リハビリ(運動)・口腔(こうくう)ケア・栄養管理」の一連の取り組みは、フレイル予防や健康長寿を伸ばすために若いときから意識すべきこと。
元気なときからこの意識が定着すれば、好きなものを口から食べられて、栄養が取れて、自分の足で行きたいところにも行ける、そんな健康で活動的な老後を長く過ごし、介護が必要な期間を短縮することもかなうはず。
「健康長寿」は、これから日本が目指すべき理想の老後だと言えるでしょう。
また、地域包括ケアシステムの推進は、2012年の介護報酬改定から取り組んでいる重点課題です。
地域のなかで高齢者を支える概念から生まれた考え方ですが、近年は年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が安心して暮らせる「共生社会」へと考え方がシフトしてきています。
高齢者の増加とともに認知症の問題も深刻化していますが、「面倒をみなくてはいけない存在」ではなく、共に暮らし、共に社会を動かすことを前提とした社会基盤を整えていかねばなりません。
介護医療の専門職でなくても、認知症への理解やサポートが当たり前にできるような世の中になって欲しいと思います。
私たちは誰もが介護保険と無関係ではありません。
介護保険料を納めるだけではなく、自分たちが納めたお金がどんな方針で運用されているのか、今後どうなっていくのかを見守る責任もあると思います。
将来の自分や家族のためにも、今後もぜひ関心を持って理解を深めてくださいね。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■充実した介護生活のために知っておくべき「介護保険制度」のポイント
介護保険制度は「介護サービスにかかるお金を一部負担してくれる制度」というだけではありません。
介護保険制度の基本的な概念を理解するなら、こちらがおすすめです。
■介護保険のマメ知識:利用者が知っておくべき介護報酬の「加算」とは?
介護報酬の理解は難しいものですが、「わが家の在宅介護」を考えるうえでとても役に立ちます。
サービス利用票でも、よく目にする「加算」についてまとめました。
2024.09.24