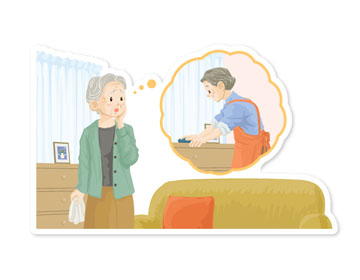こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 在宅介護に携わっている方なら、なじみのある「介護保険制度」。
在宅介護に携わっている方なら、なじみのある「介護保険制度」。
ご自身が利用していなくても、40歳以上なら毎月保険料を支払っていますよね。
しかし、具体的にどのようなものかを説明できる方は少ないと思います。
「介護が必要になったときに補助してもらえるもの」
「老後の生活をサポートしてくれるもの」
このような漠然としたイメージを持っているのではないでしょうか。
介護保険制度とは、いったい何なのか。
介護保険制度の意味を理解しておくと制度の有効活用につながります。
今回は、介護保険制度の本質を掘り下げてみましょう。
介護保険制度による「自立した生活」を手に入れるヒントが詰まっていますので、ぜひご一読ください。
● 「介護保険制度の理念」をご存じですか?
介護保険制度を「介護サービスにかかるお金を一部負担してくれる制度」と考えてしまいがちですが、それはあくまで表面的なこと。
要介護状態になった方が、残された機能・能力に応じて自立した生活を営むことができようにサポートすることが、介護保険制度の理念です。
介護保険料を払っていればどんなサービスでも受けられる、というわけではありません。
ご本人にとって便利でも、「自立した生活」につながらなければ対象にならないこともあるということです。
「できないこと、面倒なことを助けてもらいたい」という目的であれば、場合によって介護保険ではなく自費のサービスを利用することもあります。
体が不自由になっても、人からの助けを最小限にして暮らす方法を見つける。
それが要介護の方にとっての「自立」です。
自立のために専門家の知識や金銭で支援するのが「介護保険制度」と言い換えられます。
介護保険の財源は、40歳以上の被保険者から集められた保険料です。
みんなが負担して支えあう制度ですから、無駄遣いはできません。
現在、介護保険から給付を受けている方も、このことをよく理解して、本当に必要なサービスを取捨選択することが求められています。今は保険料を支払っているだけの人も、将来できるだけ要介護状態にならないよう、健康維持を心がけなくてはなりません。
このことは介護保険制度のなかで「国民の努力および義務」として明記されています。
● 要介護になっても自分がしたい暮らし方ができる
介護保険制度の本質を掘り下げていくと、なんだか厳しい制度のように感じられるかもしれませんね。
実際のところ、「要介護状態になって大変なのだから、国から助けてもらうのが当然」という考え方では、介護保険制度を利用しても、自分らしい生活をつくっていくのは難しいと思います。
何かをあきらめるのではなく、何も失わないために、介護保険制度はあるのだと考えてみてください。適切な介護サービスを受ければ、ご本人が望む生活を実現することも可能です。
想像してみましょう。
要介護になったら、どんな生活になると思いますか?
食事やトイレも人の手を借りなければならず、自分の意志で行きたいところにも行けない。
そのような暮らしでは、「自分らしい生活」とは言えませんよね。
でも、「自分のことは自分でできるようになりたい」「好きなときに出かけられるようになりたい」など、あきらめたくない思いがひとつでもあれば、介護保険制度のケアプランの方向性が見えてきます。
「人の世話になりたくない」「他人に干渉されずに暮らしたい」といったことでも充分です。
ご本人が望む生活を実現することが、尊厳を守ることであり、介護保険制度が目指すところと言えます。
自分はどんな生活を送りたいのか。
これから先、自分はどうありたいのか。
この問いかけに明確な答えがあれば、介護保険制度を有効に活用することができるはずです。
● 「何がしたい?」を前向きに考えてみる
自分はどんな生活を送りたいのか。
これから先、自分はどうありたいのか。
要介護状態になってからでは、そう簡単に答えは出ないかもしれません。
介護するご家族の方も、ご本人が何を望んでいるかイメージできないかもしれませんね。
決して難しく考える必要はありません。
もっとずっとシンプルです。
問いかけは、「何がしてみたい?」「やってみたいことはある?」など、簡単なもののほうが良いと思います。
「〇〇が好きだったけど、体がもう言うことを聞かないから...」「できれば〇〇がしたいけど、もう無理よねぇ」といった返答があるのではないでしょうか。
ご本人の意思を尊重し、実現するために支援するのが介護保険制度なのですから、どんな願いもあきらめることはありません。
もし今の介護生活に不満があるなら、「何がしたい?」を問いかけるところからもう一度スタートしてみましょう。
ケアマネジャーに相談すれば、きっと親身になって、一緒に考えてくれるはずです。
介護保険制度をより有効に活用して、いきいきした介護生活を手に入れてくださいね。
2019.10.08