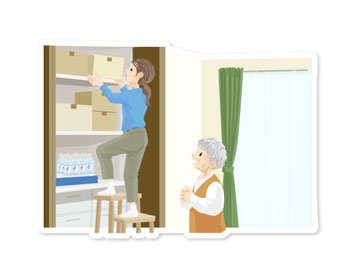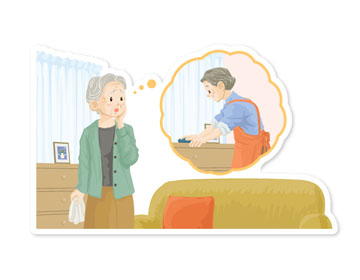こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 高齢の親の暮らしぶりに「もっとちゃんとしてほしい」と感じることもあると思います。
高齢の親の暮らしぶりに「もっとちゃんとしてほしい」と感じることもあると思います。
手を貸すうちにおせっかいになることも少なくないでしょう。
その人「らしい」暮らしを支えるにはどうしたら良いか?
自立した暮らしのためにはどうしたら良いのか?
考え方を少し変えるのがポイントです。
●高齢の親の「できていない」にとらわれすぎないで
高齢の親と接していると「できなくなったこと」や「やらなくなったこと」が気になることがあります。
たとえば、掃除が行き届いていない、料理をしなくなった、外出が減ったなど。
加齢とともに少しずつ「省略される暮らし」が増えてきます。
「もっとちゃんとしてほしい」
「昔のようにしていてほしい」
そのように思う気持ちもわかります。
しかしそれは、本当に本人が望んでいることでしょうか?
自分の価値観を押し付けていないでしょうか?
たとえ家中散らかっていたとしても、生活する部屋が整っていれば支障ありませんよね。
たとえ食卓に市販の惣菜が並び、料理の機会が減ったとしてもお味噌汁だけは自分で作ってたいるなどの意欲があれば問題ないですよね。
なんでも完璧でなくても、その人「らしい」部分が残っていれば良いではありませんか。
本人がどのように暮らしたいのかに目を向けてみることが自立した暮らしを尊重する第一歩です。
●何を維持する?何を省略する?何を優先する?
年齢とともに、体力や気力が落ちてくるのは自然なこと。
「これだけは自分でやりたい」
「ここはもう手放しても良い」
これは十人十色。
人によって大きく異なります。
「食事に手間をかけたくない。好きなドラマを観ながらのんびり過ごせればそれで良い」
「部屋の汚れは気にしない。でも仏壇の花は欠かさず替えたい」
「入浴は週に2回でじゅうぶん。でも入るからにはゆっくり長風呂がしたい」
「自分のことを、自分でする」ことが自立とは限りません。
「自分はどうありたいか」「どのように暮らしたいか」という人生のハンドルを自分で持ち続けることが大切です。
何を維持するのか、何を省略するのか、何を助けてもらいたいのか、何を優先するのか、それを自分自身で決める権利があります。それは尊重されるべきものです。
自立支援の目的は、「昔と同じ暮らしを取り戻す」ことではなく、年齢を重ねて変わっていく心身と共に「これから」の暮らしに、どう折り合いをつけていくかを一緒に考えること。
この視点で接していけば、「やらせなきゃ」「やってあげなきゃ」という思いからも、少し自由になれるのではないでしょうか。
●納得できる暮らし方を一緒に探す
「これからどのように暮らしたいか」「どうありたいか」。
本人と話す機会がとても大切です。
本人の希望がわかればサポートもしやすくなります。
たとえば、友達とのおしゃべりを「大切」にしてきた方がいます。
おしゃべりは楽しいけど、もう遠出するのが億劫になってきた。
さて、どのようなサポートが考えられますか?
家に遊びに来てもらうのはいかがでしょう。
来てもらう段取りをつければ、おしゃべりを楽しむ時間を維持できます。
本人の希望にあわせるために、「今までとは少し違う選択肢」を提示するのがポイントです。
「ずっと元気でいてほしい」と願う家族と、「もうこれで、じゅうぶん」と感じている本人。
ゴールが異なるためすれ違いがうまれるものです。
本人の価値観に耳を傾け、一緒に選び、一緒に整えていくとうまくいくと思います。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■訪問介護員に何が頼める?「自立支援」の意味を考える
「自立した生活」とは、本人が本人らしくいられること。
訪問ヘルパーやケアマネに相談すれば、そのためのサポート方法も一緒に考えてくれます。
■世間や常識にとらわれない「幸せ」な介護とは?
「幸せな老後」の価値観は人それぞれですが、親に対して、知らず知らず自分の価値観を押し付けてしまうことがあります。「さまざまな幸せのカタチ」を知る一助に。
2025.08.26