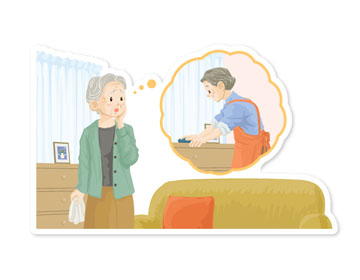こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 車いす移乗にはコツがあります。
車いす移乗にはコツがあります。
力任せに持ち上げようとしてもなかなかうまくいかないもの。
力に頼らない車いす移乗の方法があります。
● 人間の動きを利用した車いす移乗のコツ
車いす移乗は、難しい介助のひとつにあげられ、在宅介護では苦労するもの。
立つこと、腰を下ろすことを支えるのは大変な労力です。
必要以上に力が入ってしまい、腰を痛める介護家族も少なくありません。
上手に移乗させるには、残された身体機能や、人間の身体の動きをうまく利用することです。
たとえば、立ち上がりの動作。
まず、ご自身がいすから立ち上がるときの身体の動きをイメージしてみてください。
お辞儀するように頭から背中の上半身を前に倒し、腰を浮かせてから立ち上がりますよね。
その際、床に着いた足は少し後ろ、膝より後ろに引くはずです。
無意識でおこなっている動作ですが、立ち上がりの動作にはお尻側に集まった体重を前かがみになって足のほうに移動させるために欠かせない動きです。
ためしに、座ってお尻側に体重がかかった状態から、足を後ろに引かず上半身を前に倒さず、垂直にしたまま立ち上がることができるか、やってみてください。
おそらくほとんどの人が、立ち上がれないと思います。
ご自身の動きをイメージすると車いす移乗のコツが理解しやすいです。
● 力に頼らない車いす移乗の手順
(1)足を肩幅くらいに広げてもらい、床面に足底をしっかり着ける
(2)床に着いた足を膝よりに引いてもらう
(3)立ち上がりに備え、介助者は要介護者の腰のあたりをしっかり持つ
(4)要介護者にお辞儀をするように上半身を前方に倒してもらう(このとき反動で腰が浮くはずです)
(5)介助者は体を密着させて要介護者の腰を支え、立ち上がりを誘導しながら一緒に動く
(6)そのまま相手と一緒に車いすの向きに回転し、車いすにゆっくり座らせる
本人の動きを利用すれば、負担を軽減できます。
強引に持ち上げたり、力任せに動かしたりする必要はありません。
あくまでも本人の動きが主体で、介助者はその動きをサポートする支え手です。
移乗の際に腰や手に過度な負担がかかっているなら、自分の力だけで相手を動かそうとしている証拠。本人の動きや残された身体能力をうまく使ってくださいね。
● 車いす移乗で気を付けたいポイント
本人の動きを利用する介助では大きな力は必要ありませんが、ちょっとしたコツも必要です。
次のようなことに注意しましょう。
(1)事前にしっかり準備
スムーズに介助をおこなうために、事故がないようにするためには、そのための環境をしっかり整えてから介助にあたることが大切。
フットレストを上げておく、ブレーキをかけておくなど。
車いすは、立ち上がりの邪魔にならない範囲でなるべく近づけておきましょう。
ベッドからの移乗なら、立ち上がりやすいよう足底がしっかり着く高さにベッドを調整してください。
(2)声をかける
お互いに息をあわせなくてはうまくいきません。
次におこなう動作や目的をしっかり教えてあげると、身体がそれに備えて準備できます。
「今からリビングに行くから車いすに移るよ」
「立ち上がるよ」
「足を少し後ろに引いて」
このように、次の動作を言葉にして伝えましょう。
実際に動くときは「せーの」と声をかけて息をあわせると良いですよ。
(3)相手の様子をよく見る
要介護状態の高齢者は、言葉を理解するのに時間がかかったり、すぐに反応できなかったりします。
声かけだけしてどんどん進めるのではなく、本人の様子をよく見て、ときには少し待つことも必要。
返事がない、ぼんやりしている、といったときは特に気を付けて様子見を。
強引に介助しようとすると、けがにつながる恐れもあります。
(4)介助者の立ち位置を工夫する
何事も重いものを小さな力で持ち上げるには、対象物を自分の身体に近づけるのがコツ。
介助も同じです。本人の動きを妨げない範囲で、なるべく近づきましょう。
立ち上がりや移乗の際は、身体をしっかり密着させると上半身でしっかり受け止められ、腰や腕への負担も少なくなります。
支える側の安定感を図るため足を肩幅くらいに広げ、膝を曲げて腰はなるべく曲げないことも大事なポイント。
これらを踏まえて、ご自身がやりやすい立ち位置を工夫してみましょう。
●「身体の動き」と「体重移動」を意識する
立つ、座る、歩く、寝返りを打つなどの動作は、関節の動きだけではなく体重移動によって成り立っています。
立ち上がるときは、後方から前方へ、座るときはその逆。
歩くときには、左右の足へ交互に体重が移動しています。
寝返りを打つときは、まず顔を動きたい方向に向け、腕や足を動かして体重移動させることが多いでしょう。
今回は車いす移乗を中心にまとめていますが、立ち上がりや方向転換の介助は、トイレでの排泄(はいせつ)介助にも応用できます。
介助では、次の動きと体重移動の方向を予測すると、どのようなサポートが必要なのか理解しやすくなるものです。
本人の動きを妨げないこと。
体重の移動を意識しながら支えること。
この2つを意識しながら、あくまで本人の力を利用したサポートに徹すると、介助が力任せにならないはずです。
すぐにはできなくても、何度も繰り返しているときっとコツがつかめます。
ぜひ試してみてくださいね。
【あわせて読みたい!関連コラム】
■歩行介助のコツと大事なポイント
歩行は体重移動の連続で成り立つ動作。
本人の動きを妨げない立ち位置や支え方のコツをまとめました。
■介助者のカラダを守る介護のコツ
介助者の負担を減らせる、「本人の力を引き出す介助」を紹介しています。
車いす移乗以外の介助でもご苦労されている方はぜひご一読ください。
2024.02.27