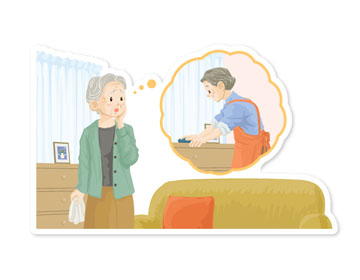こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。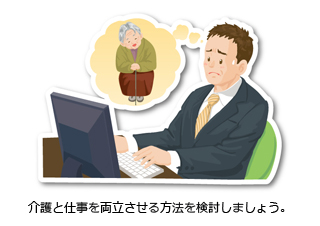 仕事をしながら、親御さんやパートナーの介護にあたっている方は少なくありません。
仕事をしながら、親御さんやパートナーの介護にあたっている方は少なくありません。
一方で、仕事と介護の両立が難しく、離職せざるを得なくなる方もいらっしゃいます。
いわゆる介護離職をする方は年間で10万人とも言われており、社会問題のひとつとなっています。
「仕事と介護の両立」がしやすい社会をめざして、さまざまな対策が行われていますが、実際は簡単ではない事情もよくわかります。
介護の現場では、仕事をしながらの介護で苦労されているご家族の姿をたくさん見てきました。
仕事と介護の両立は、大変です。
けれども、仕事を辞めてしまって後悔する方も少なくありません。
今回は、仕事を辞める前にちょっと考えていただきたいこと、知っておくとラクになるかもしれないことについてまとめます。
● 働きながらの介護はなぜ大変?
仕事を持つ介護者の方の大変さは、それぞれ違います。
・夜、介護を受ける方が暴れたり落ち着かなくなったりするため、目を離せず、睡眠不足になる。
・遠方に住んでいるために、仕事の休日を返上して介護のために通わなくてはならない。
...など。
ご自分の休みの時間を介護にあてなくてはならないことは、精神的にも肉体的にも本当に厳しいことでしょう。
ご家庭ごとにいろいろな事情があり、ご苦労もさまざまですから、一様には申し上げられないのですが、介護生活を送りながら仕事を続けるかどうか迷われているような方には、私は「できれば仕事は辞めないほうが良いですよ」とお伝えするようにしています。
介護にすべてを捧げる生活、介護だけの生活になることは、ご自身を追い詰めてしまうことになりがちです。
仕事をすることで、介護から離れて過ごせる時間を持つことができ、ご自分を保つことができるのではないかと思います。
介護から離れられる時間は、長く介護を続けていくために欠かせないものです。
そして何より、働くことで得られていた収入や社会とのつながりも途切れてしまうことになります。
介護が終わったあとも、ご自身の人生は続くわけですから、「できれば仕事を続けていただきたい」と考えます。
仕事を通じて得られた経験や人間関係は、退職し介護に専念した後に再び働き始めるとして、それまでと同様に得られるとは限りませんし、再就職すること自体が難しい場合もあるかもしれません。
仕事を「続ける」のか「辞める」のかについては、金銭面や老後の生活までもイメージして冷静に考えてみる必要があると思います。
もしかしたら今、「仕事を辞めざるを得ない」くらい大変な状況だと感じている方も少なからずいらっしゃるかもしれませんが、いったん立ち止まっていただければと思います。
仕事と介護、どちらかをペースダウンして、ご自身の体力や労力を温存する方法を、まずは探してみましょう。
● 介護の相談窓口「地域包括支援センター」に相談しましょう
以前、「元気なときから頼りになる「地域包括支援センター」ってどんなところ?」でもお話しましたが、お住まいの市町村に設置されている地域包括支援センターは、要介護認定の申請だけでなく、介護に関するさまざまな相談にのってくれるところでもあります。
相談してすぐ介護サービスの利用につながらないとしても、何か困ったら相談にのってくれる場所があるというだけでも、安心できるのではないでしょうか。
地域包括支援センターには、主任ケアマネジャーと保健師、社会福祉士が各センターに必ずいて、それぞれ専門的な対応を行ってくれることになっています。介護と仕事を両立していくうえでの悩みや心配ごとをぜひ相談してみてください。
前にもお伝えしましたが、地域包括支援センターを訪れるときは、事前に電話をして面談の予約をされることをおすすめします。
突然訪問すると、先約で埋まっていて対応が難しい場合もあります。ご注意ください。
● 第三者の手を積極的に活用しましょう
相談できるケアマネジャーさんがいる場合は、今の状態が「つらい」のだということを早めに相談されることをおすすめします。一番困っていることは何か、仕事を続けるためにどんな助けがほしいのか、整理して伝えるといいでしょう。
今、介護の負担が重い・つらいと感じている方の中には、「第三者には任せられない、私でないとできない。」とか「ほかの誰かに任せるのは申し訳ない」と考えていらっしゃる方がいるかもしれません。
介護を上手に長続きさせるコツは、ひとりで抱えこまないこと、そして、上手に人に頼ることです。最初は介護を受ける方も介護する方も抵抗があるかもしれませんが、先のことを考えて、ぜひ第三者の手をかりることを試して、受け入れてもらえたらと思います。
また、すでに介護サービスを利用している方は、その組み合わせをよりご自身の負担軽減につながる方向へと見直されるのも一つの方法です。介護を受ける方の身体の状態やご希望もあるかもしれませんので、やはりケアマネジャーさんに相談することで、改善に向けた提案をしてもらえると思います。
介護を続けるうえで、第三者を頼ることは決して悪いことではありません。
「仕事を辞める」のではなく「仕事を続ける」選択肢を優先するためには、どうすれば良いかをぜひ考えてみてくださいね。
● 介護休業を上手に使っていますか?
今後、働き盛りの世代の人口が減少すると見られていますし、働き手が介護を理由に仕事から離れてしまうことは、社会にとっても大きな損失です。
厚生労働省では「仕事と介護を両立できる社会」をめざして、さまざまな施策を行っていて、企業では介護休業制度や介護のための短時間勤務制度の導入が法律で義務付けられています。
介護休業制度は、要介護状態にある家族が常時介護を必要とする状態のときに、休暇を取得できるもので、期間は要介護状態になるごとに1回、通算93日までとなっています。また、通院や付き添いのときにも休暇を取得できることになっています。
さらに、福利厚生として独自の制度を導入し、介護をしながら働きやすい職場環境を整えている企業も増えているようです。
介護生活は終わりが見えないことから、介護休業を取りにくく感じる方も多いようですが、仕事も介護もフル回転で満点をめざそうとしては、どちらも行きづまってしまいます。
ある程度収入が減ってしまうことや、思うように働けないことは、仕事と介護を両立する上では仕方のないことと割り切ることも必要かもしれません。
仕事や社会とのつながりを途絶えさせないことは、その後のご自分の人生にとってはきっとプラスに働くことと思います。
● 介護をしながらの「働き方」はひとつではない
仕事をされている介護者ご本人が、会社に対して「迷惑をかけている」という思いが強すぎて、「申し訳ない」「いたたまれない」と感じて会社を辞めてしまうケースも多いようです。
けれども、仕事をしながら介護を続けていくためには、ある程度の割り切りも必要ではないかと思います。
就業している方の権利として、介護休業の取得が認められているのですから、ご自分を責めたりせずに「働きながら介護に使える休み」を活用しましょう。
もしかしたら理解してくれない人もいるかもしれませんが、中には励ましてくれる人もいるはずです。
介護で大変だったことも、ひとりで抱え込まずに職場で同僚に話してみてはいかがでしょうか。
いろいろな意見が聞けたり、気持ちが楽になったりすることもあると思いますよ。
その行動が、介護への理解を深めていくことにつながり、会社で介護者をサポートする雰囲気や体制づくりにもつながるかもしれません。
働きながら介護をする仲間が増えていけば、より両立がしやすい社会になっていくかもしれませんね。
ある女性のエピソードをご紹介します。
親御さんの介護のため、今のような働き方が難しくなることを上司に相談したところ、短時間勤務が可能な職種に変更することを提案してもらえたそうです。
思い切って会社に相談したことで、彼女には働きながら介護を続ける道が開けたのです。
介護人口が増え続ける今の社会では、多彩な働き方が認められつつあります。
「辞める」か「続ける」かの二択だけではない場合がありますから、これまでの働き方にとらわれないことも、大切かもしれません。
2017.06.27