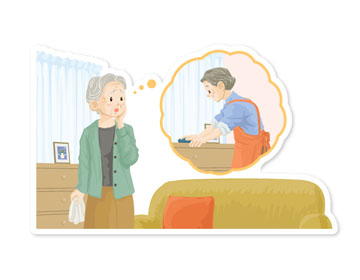こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 年も改まり、新たな気持ちでお過ごしのことと思います。
年も改まり、新たな気持ちでお過ごしのことと思います。
寒の入りを迎えていよいよ寒さも本格的になり、在宅介護のご家庭では体調管理にも気を遣う時期ですね。
食事の介助もまた、介護家族が気を遣うことのひとつ。
要介護のご高齢者は、嚥下(えんげ)機能が低下していることが多く、頻繁に誤嚥(ごえん)するなど介護家族の苦労は尽きません。
誤嚥(ごえん)性肺炎での入退院を繰り返すと医師から「胃ろう」の造設を提案されることもあります。
胃ろうというと、「自然な死に逆らう延命治療」「もう口から食べられない」などネガティブな意見を聞くことが少なくありません。
胃ろうにするか否かで迷うケースでは、このマイナスのイメージが先行している方もいらっしゃるようです。
今回は、胃ろうをより詳しく知っていただくため、「在宅介護で胃ろうにするとどうなるのか」を具体的にまとめます。
胃ろうを「良くないもの」と決めつけるのではなく、正しく理解したうえで判断することが大切。
今は胃ろうと無縁の方も、もしものときの判断材料として役立てていただけると思いますので、ぜひご一読ください。
● 胃ろうについてのよくある誤解
胃ろうとは、おなかに穴をあけてチューブを通し、胃に直接栄養を送り込むものです。
嚥下(えんげ)機能が低下して、口から食事をすることが困難な人でも、効率よく栄養を摂ることができます。
誤嚥(ごえん)のリスクがなく、安全に必要な栄養、必要なカロリーを摂取することができるという利点があります。
よく、「胃ろうにしてしまったら、もう口から食べることができなくなる」と誤解している方がいますが、そんなことはありません。
口腔(こうくう)からの摂食も継続できるのは、胃ろうのメリットのひとつ。
誤嚥(ごえん)しない範囲で好物を食べたり、口から食べる訓練をしたりすることも可能です。
栄養やカロリー摂取のための食事と、楽しみのための食事は別のもの。
胃ろうなら、食の楽しみを残しながら、必要な栄養を摂ることができます。
また咀嚼(そしゃく)や、嚥下(えんげ)にはさまざまな筋肉がかかわっているので、身体や脳にも良い影響を与えます。
「口からも食べられる」ことには、大きな意義があるのです。
また、胃ろうで摂取する食事は、「管理された特別な栄養剤」「味もそっけもない人工的なもの」というイメージはありませんか。
もちろん胃ろう用の栄養剤もありますが、それしか摂取できないわけではありません。
ご本人の健康状態や医師の判断にもよりますが、チューブに詰まらないように調理されたものなら、基本的には何を入れても大丈夫。
市販のものを利用したり、普通の食事と同じ材料で手作りしたりすることもできます。
ビタミンや水分をしっかり補給するために、野菜ジュースやスポーツドリンクを入れる方もいます。
娘さんが毎日手作りする、コラーゲンたっぷりの鳥スープを胃ろうで入れてもらっているご婦人は、うらやましいほどお肌がつやつやでした。
介護家族が「してあげたい食事」を提供できるのも胃ろうの良さのひとつです。
● 胃ろうにすると介護がラクになる?
胃ろうからの経管栄養は医療処置なので、医師や看護師、一定の研修を受けた介護職、そしてご家族しか実施できません。
毎日3食をすべて専門職に頼ることは現実的に難しく、ご家族が実施することがほとんどです。
「難しそう」「家族だけでは管理しきれない」という不安の声もよく聞かれます。
実際は、慣れればそれほど難しいわけではありません。
かかりつけ医や訪問看護師に手技を確認してもらいながら少しずつ慣れていけば、さほど不安に感じることはないはずです。
むしろ、食事のたびにむせたり、誤嚥(ごえん)したりするリスクと戦いながら、時間をかけて食事介助をするほうが、介護する方の苦労が多いかもしれません。
胃ろうなら、必要な栄養やカロリーを短時間で安全に摂取することができ、食事の時間がラクになった...という介護家族もいるほどです。
また、お薬を砕いたり溶かしたりして胃ろうに入れることで、与薬*もしやすくなったという方もいらっしゃいます。(*薬の種類にもよりますので、胃ろうからの投薬は医師や薬剤師への相談が必要です)
胃ろうによる経管栄養は、私たちが食事を摂る感覚と変わりありません。
私たちもときには朝と昼が一緒になることもあれば、忙しくて食事の時間が遅くなってしまうこともありますよね。
汗をかいた日はたくさん水分を摂ったり、前の食事からの時間があきすぎていたらしっかり目に食べたり。
胃ろうも同じで、ご本人の健康に影響しない範囲で割愛したり、調整したりすればよく、あまり堅苦しく考える必要はありません。
介護する方が臨機応変にうまく付き合っていけば、胃ろうをそれほど負担に感じることはないのではないでしょうか。
食事介助にかけていた時間を胃ろうで短縮できれば、あいた時間を別の用事にあてたり、介護する方とされる方がのんびり話をする時間をつくったりすることもできるかもしれません。
● 胃ろうは自然な死に逆らう延命措置?
「口から食べられなくなったら人は終わり」
「胃ろうには絶対しないでね」
元気なときにご本人からこのように言われているという介護家族は少なくありません。
では、実際に口からの食事が難しくなったとき、「本人がそう言っていたから」とあっさり諦められるでしょうか。
なんとか食べてもらおうと食事内容や介助を工夫し、食事のたびにどうしたら良いのか悩み苦しむはずです。
しかし、嚥下(えんげ)機能が衰えた高齢の要介護者に、生命維持に必要な栄養量や水分量を、安全に摂っていただくのは、並大抵の苦労ではありません。
少し体調が悪いだけで、ごはんが食べられなくなる。
無理に食べさせようとすると、誤嚥(ごえん)してしまう。
でもどうにか食べてもらわないと、どんどん体力が落ちていってしまう......。
高齢者の場合、コップ1杯分の水が足りないだけでも、命に危険が及ぶ状態になることがあります。
ひと匙ひと匙に命がかかっていることに、自分に課せられた責任に、介護する方は食事のたびに向き合うことになるのです。
大切な人の生死にかかわることを「自然に任せる」のは、それほど簡単な決断ではありません。
胃ろうをイメージだけで悪いものと判断するのではなく、良い点もあるということを知り、正しい知識に基づいて判断することが大切です。
ベッドから起き上がることもできなくなっていた方が、胃ろうからの栄養注入をして体力が回復し、少しずつ口からの食事が摂れるようになることもあります。
ご本人にまだ生きる力が残されているのであれば、胃ろうがそのサポートをする役目を果たすこともあるのです。
胃ろうについて、改めてご本人も交えて話し合ってみてはいかがでしょうか。
「基本的に自然に任せたいけれど、こういう状態のときは胃ろうも検討する」など、別の考え方も出てくるかもしれません。
在宅介護では「胃ろう問題」はよくあるお悩みのひとつですから、一方的な拒絶にとどまらず、折に触れて「どうするか」を話し合っておくことをおすすめします。
2021.01.12