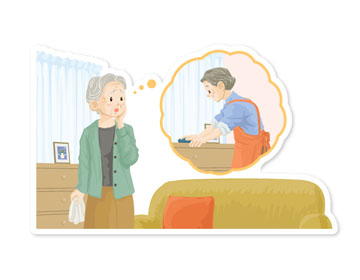こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。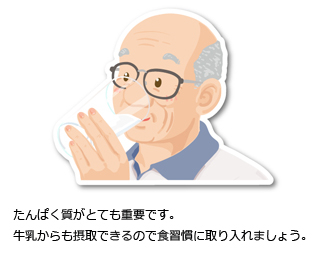 「食べることは、生きること」というように、人生の楽しみのひとつでもありますね。
「食べることは、生きること」というように、人生の楽しみのひとつでもありますね。
けれども年齢を重ねることで、以前のような食欲がなくなったり、毎食きちんと準備することが大変になったりするのはよくあることです。
こうした傾向から、「高齢の方は『低栄養』になりやすい」とよく言われます。
国立長寿医療研究センターの資料によると、在宅高齢者の約8割に低栄養の傾向が見られたそうです。
低栄養状態になると、体力が低下するだけではなく、感染症にかかりやすくなったり、持病が悪化したりと、さまざまな弊害が起きます。
要介護の方の場合、ちょっとしたケガや病気がきっかけで要介護度があがってしまうこともありますので、栄養状態にはしっかりと目を向けておきたいですね。
今回は、「低栄養」についての正しい知識をお伝えするとともに、在宅介護生活の中で栄養状態を改善する方法などをまとめます。
● 高齢者の食生活は「たんぱく質」が不足しがち
「低栄養」の原因として、食事の量が不十分なことがあげられます。
年齢を重ねるとどうしても食事量が減ってきますので、誰もが低栄養になる可能性を持っていると言えます。
低栄養で特に問題になる栄養素は「たんぱく質」。
肉類や大豆製品などに含まれている栄養素です。
高齢の方は、普段の食事でたんぱく質を十分に摂取できていないと考えられています。
訪問介護で高齢者の方だけの世帯に伺った際、同じものばかり繰り返し食べる習慣が定着しているケースを目にすることがありました。
食習慣にはさまざまな理由や事情があるかと思います。
けれども、「自分一人だけだから」「夫婦2人だけだから」などの理由で、栄養素について考えることなく簡単に済ませてしまったり、パンやおにぎりなどの主食(炭水化物)だけをとって満腹になってしまったりといった食生活が続くと、低栄養を引き起こしかねません。
特にリハビリに取り組んでいる方は、低栄養にいっそう注意が必要です。
運動でたんぱく質を消費するため、意識的に補給する必要があります。
● 「低栄養」を見極めるポイントは?
高齢者の方のたんぱく質不足は、健康問題に直結します。
以下のようなことが該当するときは、ひょっとすると「低栄養」が原因かもしれません。
<低栄養のサイン>
□ 体重が急に減少した
□ 疲れやすくなった
□ 風邪などの感染症にかかりやすく、一度かかるとなかなか回復しない
□ すり傷や床ずれがなかなか治らない
疲れやすさや活動量の低下は、老化による身体の変化とも言えますが、低栄養を疑ってみることも大切です。
前述の「低栄養のサイン」に該当するものがあるときは、かかりつけ医に現状を伝え、血液検査を受けるようにしましょう。
低栄養は、血液検査で簡単にわかります。
「総たんぱく(TP)」と「アルブミン(Alb)」の値が基準値を下回っている場合は低栄養状態です。
● 「低栄養」を改善するちょっとした工夫
日ごろの食事に少し工夫を加えることで、不足しがちな栄養を補うことができます。ぜひ実践してみてください。
>いつもの食事にプラスアルファ
たとえば、白いご飯に生卵をかけたり、みそ汁に豆腐を入れたりと、いつも食べているものに良質なたんぱく質を豊富に含む食材を加える工夫をしてみましょう。
ツナやサバなどは、缶詰でも手軽にたんぱく質が取れますし、きなこや豆類をおやつに取り入れたり、朝晩に牛乳を飲むことを習慣化したりするのも、簡単でおすすめです。
>「食べやすさ」を工夫する
食事は、好き嫌いのほかにも、食べやすいかどうかの感じ方も人それぞれ違います。
介護されている方の食事があまり進まないときは、ご本人に聞いてみてください。
「飲み込みにくいから(食べたくない)」「噛みにくいから(食べたくない)」など、理由があるかもしれません。
とろみをつけたり切れ目を入れたりと、ちょっとしたひと手間で食べやすくなって、食事量が増えることもあります。
>宅配サービスなどを利用する
高齢者向けのお弁当宅配サービスでは、栄養バランスの良いメニューが提供され、食べやすさも工夫されています。
毎食宅配を頼むのは経済的な負担が大きいかもしれませんが、食事をつくるのが大変なときに利用したり、1日のうち1食だけお弁当にしてみたりと、できる範囲で活用するのもおすすめです。
>食事を楽しむ環境づくりを意識する
ひとりきりでの食事は、食が進みにくく、栄養も偏りがちなため、低栄養になる原因のひとつと言われています。他の人と一緒に食事を取れる環境だと、食欲も増すでしょうし、食べることを楽しむ気持ちにもなれるのではないでしょうか。
ご家族が一緒に食事ができない場合は、デイサービスを利用したり、福祉会館などで実施している会食会に参加したりして、食事をする環境をときどき変えてみるのも気分が変わり、食事が進むことにつながるかもしれませんね。
食事の問題は、経済事情や家庭事情で二の次になってしまう場合もありますし、決まったメニューでないと安心して口にできないという方もいらっしゃいますので、改善するのが難しい場合もあるかもしれません。
それでも、低栄養についての知識と自覚を、ご本人や介護するご家族が持っておくことは、とても大事だと思いますので、まずは食生活や健康状態を把握して、栄養状態を悪化させないための"ちょっとした工夫"を重ねていけると良いですね。
2017.06.13