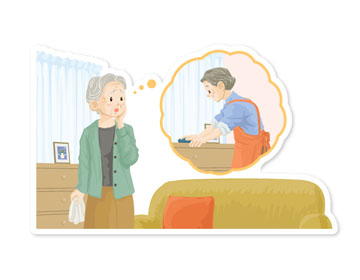こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 在宅介護の大変さは多種多様です。
在宅介護の大変さは多種多様です。
なかでも「介護用おむつの交換」で苦労している方は多いのではないでしょうか。
ご家族から介護用おむつに関するお悩みを聞くことがありますが、特に多いのが「もれてしまう」というお悩み。
介護用おむつで起こる「もれ」は、介護される方が不快なばかりでなく、交換に手間がかかり、汚れ物の後始末もともなうので、介護する方の疲労も増大します。
介護する方、される方、双方のためにも、できるだけ失敗がなく、上手に介護用おむつを使いたいですね。
介護用おむつの交換で起こる「もれ」の防止や、介護用おむつを利用するうえでのお悩みについて、アドバイスをまとめましたのでご覧ください。
● 手早く、丁寧に「介護用おむつを交換」するには?
介護用おむつの交換では、手早く済ませようとしてしまいがちですが、きちんとあてないと「もれ」の原因になります。手早く、丁寧に交換するのが理想です。
大切なのは「事前の準備」です。
おむつを交換するときの手順をイメージして、必要物品も考えてみましょう。
環境を整えておくことで、より落ち着いて確実にできるようになります。
おむつ交換に必要なものを整理してみましょう。
・替えのおむつ
・使い捨ての手袋
・身体をきれいに拭くための温水(シャワーボトル入り)や布
・交換後のおむつを捨てるビニールやバケツ
一例をあげましたが、ほかにもあると思います。
使いやすいものや欠かせないものを整理して、用意しておきましょう。
交換をはじめるまえに、用意したものが手の届くところに順序よく配置されているかを確認してくださいね。準備万端整えてからおむつ交換をはじめましょう。
さて、介護用おむつを交換するうえで、注意したいのが介護される方への気配りです。
本来であれば、人に手を掛けてもらいたくないところに手を借りるわけですから
交換する側のペースでどんどん進めてしまうと、されている方は恥ずかしさや不安があるものです。
必ず声をかけて何をするかを伝え、相手の承認を得たうえで進め、身体の向きを変えるときなどはご本人ができる範囲で協力してもらいましょう。
カーテンやドアは閉める、汚れた介護用おむつは置きっぱなしにせず手早く始末するなど、介護される方の気持ちへの配慮も忘れないようにしてください。
● 介護用おむつの「もれ」を防ぐ3つのポイント
介護用おむつは、単独で使うよりも「尿とりパッド」とセットで使用するのが一般的です。
尿とりパッドはフラットな形状の吸収シートで、おむつの内側に装着します。
正しく使えばおしっこをパッドでほとんど吸収してくれますので、外側のおむつを毎回変える必要がなく、手間もコストも軽減できます。
介護用おむつの悩みである「もれ」を防ぐためにも、尿とりパッドをうまく活用したいですね。
押さえておきたい大事なポイントは以下の3つです。
(1)尿とりパッドを尿の出る場所に密着させる
尿とりパッドを平らなままあてるのではなく、出る場所にぴったり沿わせるようにあてるのがコツです。
女性の場合は、パッドの中央を山折りして縦のスジをつくると密着します。
男性の場合は、パッドの広い方をおなか側にして、谷折りして性器を包み込むようにあてましょう。
(2)介護用おむつと尿とりパッドのギャザーをしっかり立てる
介護用おむつやパッドは折りたたんであるため、広げたときにギャザーが寝た状態になっていることがあります。指を使ってしっかりと立てておきましょう。
パッドは介護用おむつのギャザーの内側に収まるようにセットすると、おしっこが広がったり流れ出たりするのを防げます。
(3)足の付け根に隙間ができないようにテープを貼る位置を調節する
介護用おむつと身体の間に隙間ができると、そこからもれやすくなってしまいます。
介護用おむつを足の付け根に合わせるには、テープをとめる位置がポイントです。
ギャザーを立てて身体のラインに丁寧に沿わせるようにしてあてた状態で、下のテープからとめましょう。
肝心なのは尿とりパッドのあて方とギャザーの使い方。
尿とりパッドを重ねて使ったり、お尻側にずらしたりすると、隙間ができて「もれ」の原因になります。
また、大きめのサイズのパッドを使うことも、あまり意味がありません。
介護用おむつのサイズと合っていないと、ギャザーの中に収まらずに流れ出してしまうからです。
尿とりパッドはたくさん使えば吸収力がアップするわけではありません。
確実にあてることが「もれ」を防ぐコツです。
● 介護用おむつでの「かぶれ」や「床ずれ」を防ぐには?
介護用おむつは防水性が高いため、蒸れやすいのが難点ですね。
かぶれなどの肌トラブルが起きやすく、ちょっとした摩擦や刺激で床ずれになってしまうことがあります。
こまめに交換して清潔に保つことが何よりですが、陰部を洗ったり拭いたりしたあとのケアも重要です。
大事なのは、「乾かす」ことと「保湿」です。
矛盾しているようですが、「かぶれ」や「床ずれ」予防には皮膚の保護が大切です。
肌が湿ったままの状態で介護用おむつをつけると雑菌が繁殖して肌トラブルに直結します。
シャワーボトルで洗浄したり、濡らした布で拭いたりしたあとは、必ず乾いた布で水分をしっかりとるのを忘れないでくださいね。
肌をしっかり乾かした後は、保湿対策を行いましょう。
乾燥は皮膚にとって守られていない状態になるため、「ずれ」などで皮膚が傷つきやすくなります。
オリーブオイルやワセリンなどを薄く塗るのがおすすめです。
皮膜の役割をして肌への負担を和らげてくれますし、摩擦も軽減してくれます。
「もれ」や「かぶれ」など、介護用おむつの不快を軽減すれば、介護される方の気分もずいぶん変わります。
お互いのストレスや負担を軽減するためにも、上手におむつの交換ができるといいですね。
2017.04.11