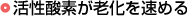
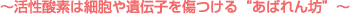
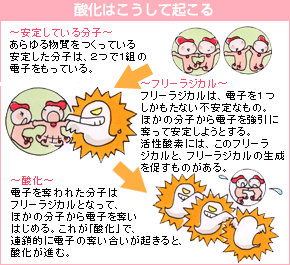 なぜ人は老いるのか。老化をもたらすメカニズムにはいろいろな説がありますが、ひとつだけで説明がつくものではなく、いくつもが重なり合って老化を進めると考えられています。老化のプログラムが予め遺伝子にセットされているともいわれますが、老化をもたらしたり進行させる要因は多様で、生活環境やライフスタイルの影響を大きく受けます。 なぜ人は老いるのか。老化をもたらすメカニズムにはいろいろな説がありますが、ひとつだけで説明がつくものではなく、いくつもが重なり合って老化を進めると考えられています。老化のプログラムが予め遺伝子にセットされているともいわれますが、老化をもたらしたり進行させる要因は多様で、生活環境やライフスタイルの影響を大きく受けます。
そうしたいくつもの老化のメカニズムに共通して登場するものが、最近よく話題にのぼる「活性酸素」です。活性酸素は、体を構成しているたんぱく質や脂質などと結びつこうとする性質が強く、活性酸素と結合したたんぱく質や脂質は、本来の働きができなくなったり、異常な作用をもつようになります。このような性質は、よく鉄サビにたとえられます。丈夫な鉄も、空気中の酸素と反応して酸化されると、ボロボロにもろくなってしまいます。活性酸素はこれと似たようなことを体内で起こし、細胞や組織、遺伝子にも害をおよぼすというのです。
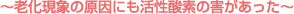
活性酸素は、体に害になるばかりではなく、もともと体内に侵入してきた病原菌などの異物をやっつけるという大切な役割もしています。必要だけれども多すぎると困るというものなのです。そのため私たちの体には、活性酸素の量をコントロールするしくみが備わっています。さまざまな酵素が、余分な活性酸素を除去するように働いているのです。
しかし、活性酸素は、私たちが呼吸をしたり食事をしたりするときにも発生します。紫外線に当たるのも活性酸素を生む原因になります。喫煙の習慣があるとか、排ガスや化学物質にさらされた生活をしていると、さらに活性酸素が増えがち。酵素の力だけでは対処しきれなくなれば、細胞や遺伝子を徐々に傷めていきます。これが老化を進めたり、病気を引き起こしたりするというのです。
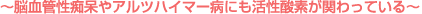
 脳の老年病ともいえる脳血管性痴呆やアルツハイマー病の起こる背景にも、活性酸素の関わりが考えられています。脳が働くには大量の酸素が必要で、そのため、私たちの体には、取り入れた酸素をどんどん脳へ送るしくみがあります。それだけに脳は活性酸素の影響を受けやすいところでもあるのです。また、脳は脂質に富んだ臓器で、この脂質が酸化されると有害な過酸化脂質に変わります。 脳の老年病ともいえる脳血管性痴呆やアルツハイマー病の起こる背景にも、活性酸素の関わりが考えられています。脳が働くには大量の酸素が必要で、そのため、私たちの体には、取り入れた酸素をどんどん脳へ送るしくみがあります。それだけに脳は活性酸素の影響を受けやすいところでもあるのです。また、脳は脂質に富んだ臓器で、この脂質が酸化されると有害な過酸化脂質に変わります。
老化は避けられなくても、病気に至る前にぜひブレーキをかけたいものです。 |