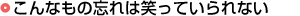
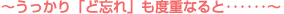
年をとれば誰だって、若いときより記憶力も衰え、もの忘れもしやすくなります。ひょいと置いたものの置き場所を忘れて探し回ったりするのは、ほかのことに気を取られていれば、誰でもやりかねない、いわば「不注意」といえます。
よく知っている人の名前が出てこない、前日の夕食のおかずが思い出せないなどという「ど忘れ」も、誰しも経験のあることでしょう。しかし、ど忘れとは本来、ふだんはすぐに出てくることが思い出せない"まれなこと"をいうものです。「この頃、ど忘れが多くなった」「何度も同じことを忘れている」・・・・・・これは、本当にど忘れと片づけてよいのでしょうか。
ど忘れも「記憶のエラー」。エラーを繰り返す脳は、どこかに問題を抱えているのかもしれません。たかがど忘れといっても、脳の機能低下のサインの場合もあります。
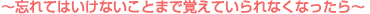
|
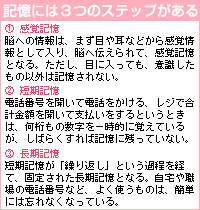 私たちはどうして忘れてしまうのでしょう。記憶には三つの段階があります。(1)感覚記憶、(2)短期記憶、(3)長期記憶です。 私たちはどうして忘れてしまうのでしょう。記憶には三つの段階があります。(1)感覚記憶、(2)短期記憶、(3)長期記憶です。
脳への情報は、目や耳などの感覚器から入り、脳へ伝えられて、まず感覚記憶となります。もちろん目に映ったものすべてが記憶されるわけではなく、そのとき意識したものだけが記憶となるのです。
こうして新しく得た情報は一時的に記憶されています。初めて聞く電話番号でも、すぐに電話をかける必要があるなら覚えていられるでしょう。これが短期記憶です。
これを長期記憶としてずっと覚えているには繰り返しの過程が必要です。努力しなければ、人は忘れてしまうのです。
自分には関係ないと思えば、耳に入っても記憶にはとどまりません。繰り返し覚えた大事なことでも、長く思い出すことがなければいつかは忘れてしまいます。これは普通のことです。しかし、忘れてはいけない大事なことを頻繁に忘れてしまうようになったら、それは"病的なもの忘れ"かもしれません。
|
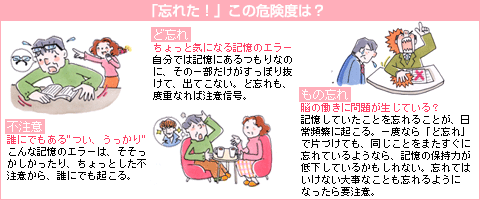
|
|