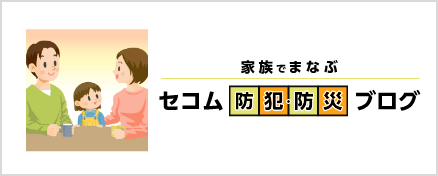第79回 消火器の使い方って?いざというときに備えて、
ポイントを確認しよう!

こんにちは。今年は、冬らしい気候の日が多く、太平洋側では記録的な乾燥注意報が出ていますが、皆さんは乾燥対策をしていますか?お肌はもちろん、インフルエンザや風邪対策としても、潤いチャージが大切ですよね。潤うために、スプレーなどで水を顔や手にかけている人もいますが、逆に、その水のせいでお肌の水分を奪ってしまうそうですよ。化粧水など、潤い成分が入ったものを、こまめにチャージするのがいいのだとか。仕事中でも休憩時間を利用してちょっと気を付けてみようと思います。
2012.1.23更新
空気が乾燥するこの時期は、火の元にも普段以上に気を使わなければいけません。2010年に発生した火災の件数は、46,620件。1日に130件近くも起きている計算になります。出火原因は毎年ほぼ同じで、放火を除くと、コンロやたばこによるものが上位を占めています。これを聞くと、身近に原因があることがわかりますよね。
皆さんは、いざという時、初期消火するための消火器の使い方をご存知ですか?消火器を見たことはあっても、使ったことがある人は少ないですよね。そこで今回は、セコムの研修センターで、実際に火を使った消火体験をしてきました。セコムの研修部主任の箕輪健司氏と山田大助氏に、消火器の使い方を一から教わってきたので、皆さんにもご紹介しますね。
"燃焼"の3要素と火災の種類を知っておこう

火災と消火器の種類について解説する
セコム(株)研修部の箕輪健司氏
まず、なぜ火事が起こるのかという基本的なことから教えてもらいました。ものが燃えるには、「熱源」「可燃物」「酸素」という3つの要素が必要で、この3つが揃い、火事が起きます。逆にいうと、どれか一つをなくすことで、消火できるそうです。
たとえば、てんぷら油火災の場合、水で濡らしたバスタオルで、炎の上からてんぷら鍋全体を覆えば、消火できます。これは、酸素を奪って消火したことになり、3要素の一つを取り除けた、というわけです。なお、このようにバスタオルを使って消火するときのポイントは、タオルは水が垂れない程度に絞って使うこと、そして火が消えてもすぐにタオルを取らないことです。
そして、火災の種類は3つあります。テーブルやイスなど木材や紙が燃える普通火災(A火災)、ストーブやてんぷら油から出火する油火災(B火災)、テレビやブレーカーなどの電気火災(C火災)。火災の種類によって、使う消火器も違ってくるそうです。

こちらは普通火災、油火災、電気火災に対応した消火器
ですから、消火器はどのタイプの火災に対応しているのかを確認することが大切。さきほどご紹介した火災の種類が消火器にも記されていて、どのタイプの火災を消すことができるかが分かります。一般的に私たちがよく目にする粉末や強化液タイプの消火器なら、3種類の火災すべてに対応しているそうです。
消火に挑戦!そのポイントとは?
火災と消火器の基礎知識を学び、いよいよ実際の火を使った消火を体験することに。今回は、てんぷら鍋から出火した想定で、消火器を使って消火訓練をしました。
まず、火災が発生したら消火器を準備しますが、このとき大切なのはレバーの下だけを片手で持つこと。レバーを握っていると、安全栓を抜いたときに誤って消火剤を放射してしまう可能性があります。
次に、消火するための立ち位置を確認します。必ず風上に立ち、火の高さの2〜3倍の距離を取るようにしてください。煙や炎が向ってこない方に立ち、自分の身の安全を確保することが鉄則だそうです。そして、いよいよ消火器を使います。
◆消火器の使い方手順


山田大助氏に指導を受け消火にチャレンジ!火の高さの2〜3倍の距離から消火剤を放射
この4つの手順だけですが、予想以上に、消火に時間がかかってしまいました。
まず、消火器が意外と重いことにびっくり!また、火から目を離さずにすべての動作を行うことが理想ですが、安全栓を抜くとき、ノズルを取り出すときについ手元を見てしまいます。
そして、レバーを握り、いざ消火剤を放射してみると、火元に向けているつもりでも、火元より上を狙っていたようで、なかなか消火できませんでした。しっかりと火元を狙って放射することが大切です。
消火器の種類によって多少違いはありますが、消火器が使用できるのは20秒から30秒間。それで消火できなければ、もう1つ消火器が必要になります。2つ消火器を準備している場合って、個人のご家庭だとあまりないですよね。消火器の使い方のポイントを押さえて、効率よく消火を行うことが大切です。
万が一のために、消火器を備えよう
今回はてんぷら油火災を想定しての消火体験でしたが、予想以上に炎が大きく、訓練とは言え、慌ててしまいました。私たちが消火器で消火活動ができるのは、初期の火災です。屋内の火災であれば、だいたい天井に炎が達するまでが"初期"。
火災を発見したら、すぐに消防に通報し、初期消火が難しいと判断したら、身の安全のため逃げるようにしましょう。
炎が広がる前に消火するということを考えると、キッチンの近くなど、すぐに手が届く場所に消火器を備えておくと安心ですね。集合住宅なら廊下など共用部に設置されている場合もありますが、消火器を取りに行く間に、炎が大きくなってしまう恐れもあります。集合住宅にお住まいでも、自宅に消火器を備えておくことをオススメします。
でも、消火器は以外と重く、女性が消火を行うのは大変。そこで、セコムではすべての操作を片手で行うことができる消火器「トマホークマッハⅡ」をご用意しています。万が一に備え、自分に合った消火器を自宅にも用意しておきましょう。
今回、私たちは実際に火を使って消火体験をしましたが、こうした機会はなかなかありません。いざという時のために、ご自宅に消火器を準備し、イメージトレーニングをしておきましょう。もちろん、火事にならないよう日ごろから火の元には十分注意してくださいね。
- 関連するカテゴリーを見る
- 火災