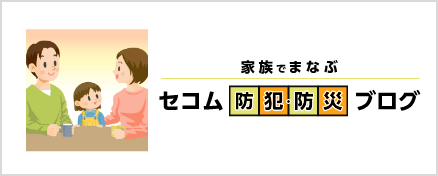自宅の地震対策
生活の基盤である自宅の部屋。お気に入りのインテリアも大切ですが、地震対策も忘れてはいけません。自分の身と財産を守るためにもしっかり自宅の地震対策をしましょう。
家具・家電を固定する
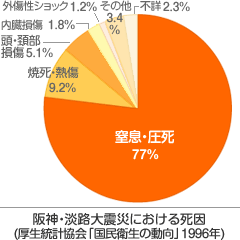
阪神・淡路大震災では、多くの方が寝ていた早朝に発生したため、亡くなられた方の死因の8割近くが「窒息・圧死」でした。このことからも、家具や家電を固定しておくことの重要性が分かります。
さまざまな耐震グッズが市販されているので、それぞれの家具や家電に合ったものを利用すると良いでしょう。
そして、窓や棚のガラス面にはガラス飛散防止フィルムをお忘れなく。
また、地震の揺れで食器棚の扉が開き、中身が飛び出してくることもあります。扉のある家具には、扉開き防止の器具を取り付けましょう。
家具・家電の固定のポイント
- 本棚
家具転倒防止グッズを取り付けましょう。
突っ張って固定するタイプや、壁に固定するタイプがあります。
- 窓ガラス
ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。
- 扉
揺れによって扉が開かないよう、扉開き防止グッズを取り付けましょう。
- テレビ・パソコンなどの家電
耐震マットや耐震クッションで固定しましょう。
- 壁掛けの時計や額
簡単にはずれないよう、しっかりと固定しましょう。

- 照明
簡単にはずれないよう、しっかりと固定しましょう。
特に吊り下げ式のものは、同色の飾りチェーンなどを使い、3または4方向に連結することをオススメします。
- ドレッサー
家具転倒防止グッズを設置しましょう。
家具の下に敷いて安定させるタイプのものなどがあります。
- 食器棚
家具転倒防止グッズを取り付けましょう。
扉がある場合は扉開き防止具を、ガラス張りであればガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。
- 冷蔵庫
家具転倒防止グッズを取り付けましょう。
突っ張って固定するタイプや、壁に固定するタイプがあります。
家具の配置を工夫する
家具や家電は、配置場所も見直してみましょう。就寝中に大きな地震が起きたとき、ベッドのそばにテレビや本棚など、重たい家具を置いていると、その下敷きになってしまう可能性もあります。
また、避難の妨げにならないよう、家具や家電の配置にも工夫しましょう。
家具・家電の配置、ココに注意!
- 部屋の出入り口付近や玄関までの通路には、背の高い家具や重たい家具を置かない
- 家具や家電はベッド・布団から離して設置する
- 重いものは低い位置に置く(ピアノは戸建て住宅の1階に。電子レンジやプリンターなどの家電を高い場所に置かない。)
火災を防ぐ〜電気・ガス・石油機器〜
地震が起こったときは、火災を起こさないよう気をつけなければなりません。
生活に欠かせない電気製品やガス、石油機器が出火の原因になる可能性もあります。
ガスコンロは、大きな地震のときには安全装置が作動し、ガスが遮断されます。揺れが続いている間は身の安全を確保するのが第一ですが、お料理や暖房などで火を使っている場合、揺れが収まったら火を消してガスの元栓を閉じ、電気のブレーカーを落とすようにしましょう。
そして、日ごろから火災のリスクを避けることも大切です。インテリアの配置や暖房器具の扱い方についてもチェックしてみましょう。
特に普段から10年を越えるような古い電気製品の使用やたこ足配線には気をつけましょう。
日ごろの備えで火災を防ぐ!
- 家電のそばには花瓶やアロマポットなど、水気のあるものを置かない
- ガスコンロの周辺にキッチンクロスなど、燃えやすいものを置かない
- 暖房器具のそばには洗濯物やカーテンなど燃えやすいものを置かない
- 石油ストーブへの給油時に灯油をこぼさない
避難ルートを確認する
地震が発生したとき、自分の部屋からどのようにして脱出するか決めていますか?屋外までの避難ルートをイメージしてみましょう。
集合住宅の場合、共用部分に非常口や非常階段が設置されているはずです。また、ベランダには、隣家との仕切り板を非常時に破って避難できるようになっていたり、階下への避難はしごが設置されていたりします。
玄関とベランダなど、2つ以上の避難経路を確認しておくと良いでしょう。地震後に屋外へ避難をするときは、エレベーターを使用するのは危険です。非常階段を使ったルートをチェックしておきましょう。
そして、自宅近くの避難所や防災拠点を事前に調べておきましょう。分からないときは、お住まいの地域の自治体に問い合わせましょう。
避難ルートのチェックポイント
- 玄関やベランダへの脱出ルートに障害となるものを置かない
- 自宅から外への脱出ルートを複数考えておく(玄関ドアから、ベランダからなど)
- 集合住宅の場合、非常口・非常階段の確認
- 自宅から避難所までの避難ルートをチェック