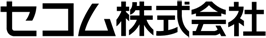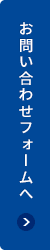開催レポート
第6回:超スマート社会のなりすまし問題
今回は、「超スマート社会のなりすまし問題」と題して、高度化するなりすましの問題と未だ伝統的な方法が多く採られている本人確認・真正確認というプロセスに焦点をあてて、プロダクトやサービスの課題を探索し、それを解決するためのアイデアディスカッションをテーマに開催しました。
「超スマート社会」とは、政府が策定した「第5期科学技術基本計画」で示されている未来の社会像です。ネットワークの高度化やビッグデータ解析技術及び人工知能(AI)などの発展により、サイバー空間と現実空間が融合し、「必要なもの・ことを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供」でき、社会の様々なニーズにきめ細やかに、かつ効率的に対応できる社会を指しています。
こうした社会においては、IoT、ビッグデータ、人工知能、ロボットの活用などが想定されていますが、インターネットを介して人とモノがつながる社会になるほど、便利になると同時に「なりすまし」も出てきます。
今回は、進行しつつある超スマート社会において、なりすましの問題に対応しつつ、ユーザーが「快適・便利」に過ごすためアイデアを出し合うワークショップを行いました。
話題提供では、認証における問題点やその解決策に関する取り組みについて、東京大学 ソーシャルICT研究センターの鈴木宏哉先生と小林良輔先生から参加者へのインプットをいただきました。ワークショップでは、フェイクフードの体験試食をはさみながら、分野・業界を越えた多様な参加者がそれぞれの視座から、「フェイク・なりすましに関して、どんな問題を抱えているか」「どうすれば安全性と利便性を保った認証ができるか」などについて議論を交わしアイデア創造を進めました。多くの切り口から未来の社会を見つめ、課題を共有しつつ、気づきを得る場として盛会に開催することができました。
開催日時
2017年5月25日(木) 17:00〜20:00
話題提供者
-

東京大学 ソーシャルICT研究センター
鈴木 宏哉、小林 良輔・鈴木 宏哉(写真上)
東京大学 大学院情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター 次世代個人認証技術講座/学術支援専門職員。
慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。IT会社勤務。システム構築からストレージの技術研修業務に携わる。2014年より東京大学ソーシャルICT研究センターにて、個人認証技術の研究に従事する。・小林 良輔(写真下)
東京大学 大学院情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター 次世代個人認証技術講座/学術支援専門職員。
東京大学工学部計数工学科卒業。SIer会社にて損害保険業務システムの開発を担当。2015年より東京大学ソーシャルICT研究センターにて、主に電波情報やアプリ利用履歴情報を活用した個人認証技術の研究に従事する。 -

総合ファシリテーター
セコムオープンイノベーション推進事務局
沙魚川 久史セコムオープンラボ総合ファシリテーター。東京理科大学 総合研究院 客員准教授、国研 科学技術振興機構 専門委員、ものこと双発協議会 事務局長。
セコムの研究開発部門を経てセコム科学技術振興財団事業部長として研究助成プログラムを推進した後、セコム本社企画部主任にてセコムのオープンイノベーションを推進。東京大学イノベーションマネジメントスクール修了、東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科修了、東京理科大学大学院イノベーション研究科修了。専門領域は技術経営で、大学や国立研究開発法人、産学官コンソーシアムなどでも活動しながらサービス創造の視座より産学官の連携を推進している。近著は「Changes in Business Fields and Technological Fields along with the Advancement of IoT」(特許庁・みずほ情報総研,2017年)。
当日の模様
セコムオープンラボの冒頭では、アイスブレイクとして、セコムより、5月11日に発表した「セコムグループ2030年ビジョン」をご紹介しました。セコムがあんしんプラットフォームの構築を目指していることや、共感を大事に、想いを共にするパートナーと一緒に取り組むための「“共想”戦略」を掲げていること、そしてセコムオープンラボも“共想”の場つくりの一つであることをご案内いたしました。
話題提供では、社会やネット上でのなりすましの実態や、これまでと今後の認証方法やトレンドの変遷などをご紹介いただいた上で、「ユーザーに使ってもらうためには、安全性と利便性の両立が重要」といった観点をインプットいただきました。また、次世代の認証手段の一つとして、ユーザーの行動履歴や位置情報といった行動認証要素を組み合わせた「ライフスタイル認証」の研究成果や、ライフスタイル認証を含めた複数の認証手段を組み合わせて行う「多要素認証」などの紹介がありました。


また、今回の開催ではテーマが「なりすまし」ということもあって、軽食として「見た目はたこ焼き、中身は甘味」というフェイクフードを用意しました。視覚と味覚が一致しないという不思議体験にびっくりする方もいらっしゃいましたが、これも一つの題材にしながら、未来の超スマート社会における認証手段について、各グループで賑やかに議論しました。
休憩を挟んだ後のワークショップ後半では、ディスカッションで出てきた課題を踏まえ、グループごとに「解決アイデア(真正確認のソリューション)」の探索を行いました。今回も様々な分野の参加者が集まったこともあり、各グループからユニークなアイデアや尖ったアイデアが次々と生まれました。

- あえて認証情報を多く開示する世界感として、組み合わせなどで認証を複雑化してそれによって安全性を高める「情報のオープン化」
- 自分で情報を管理し切るのは難しいため、一元管理を委託する「情報ガードマン」
- 日頃の行いを見て、誠実さ正しさなどを数値化し、善い行いをすると税など社会コストが下がるようなインセンティブを用意する「信用通貨」
- 認証の安全性とそのための手間や利便性を秤にかけて自分でセキュリティ度合を決める「あんしーそー」
- 複雑になる認証プロセスのなかでパーソナルアシスタントが、自分が誰か/相手が誰か/自己紹介など必要なレベルの情報を交換してくれる「肩乗りロボット」
最後に、各テーブルでの議論の成果を参加者全員にシェアした結果、参加者からもっとも評価されたテーブルのメンバーそれぞれに「セコムの食」を副賞としてお贈りしました。
今回のオープンラボでも数多くのユニークで独創的なアイデアが集まりました。今回出てきたアイデアは、参加者それぞれが持ち帰り、各々の視座から新たな“気づき・きっかけ”として活用いただけることと思います。来たる超スマート社会に向けて、多様な視点から議論が交わされる刺激的な場になりました。