|
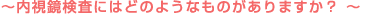
 内視鏡検査は検査する部位により、種類が分かれます。胃を中心に見る場合は「胃内視鏡」と呼びますが、食道、胃、十二指腸はまとめて上部消化管と呼ばれますので、上部消化管全体を観察する場合は「上部消化管内視鏡」となります。 内視鏡検査は検査する部位により、種類が分かれます。胃を中心に見る場合は「胃内視鏡」と呼びますが、食道、胃、十二指腸はまとめて上部消化管と呼ばれますので、上部消化管全体を観察する場合は「上部消化管内視鏡」となります。
折角の検査なので、胃だけを観察するよりも、食道、胃、十二指腸を含めて観察することが一般的です。なお通常は口から内視鏡を挿入し観察しますが、最近は、鼻腔から入れられる細い内視鏡もあります。
これについては次の「
鼻から入れる内視鏡」の説明をご覧ください。大腸を調べる場合は、肛門から挿入して、直腸を含む大腸全体の検査を「大腸内視鏡」にて行います。なおこの検査を、上部と対比して、「下部消化管内視鏡」と呼ぶ場合もあります。
さらに、胆嚢、胆管、膵管を調べる「
ERCP(内視鏡的胆管膵管造影)」という検査と、内視鏡の先端に超音波装置を装着し、あるいは、内視鏡のチャンネルに細い超音波の装置を通して、消化器の超音波検査を行う「
超音波内視鏡検査」については、それぞれの説明をご覧ください。
「腹腔鏡」「胸腔鏡」という内視鏡もありますが、これはそれぞれ腹部や胸部を覗く内視鏡で、最近は治療目的に応用されて使われることが多くなっており、
腹腔鏡下手術の説明をご覧ください。 消化器以外では、婦人科で行う「子宮鏡」、泌尿器科で行なう「膀胱鏡」、気管支を調べる「気管支鏡検査」があります。このほか、関節、血管の中などにも内視鏡が広く応用されるようになっています。
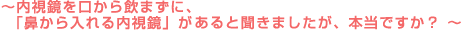
本当です。通常は、細い内視鏡を口から入れて、食道の入り口まで誘導し、患者さまに内視鏡を飲み込むようにしていただき、さらに食道へ挿入します。ところが、最近の内視鏡機器の進歩で、太さが直径6mm程度の内視鏡が実用化されたため、鼻腔に入れられる機種が登場するようになりました。
細いことで画質や操作性に多少の制約はあるものの、通常の検診などには実用上は支障ないレベルの内視鏡です。問題点としては、鼻を局所麻酔しますが、鼻腔が狭い方では痛かったり、鼻血を出すことがあります。長所としては、検査中の吐き気がやや軽減することが期待されています。
検診の目的で行う場合は、患者さまにどちらがよいかを決めていただくことができます。ただし、治療処置を伴う内視鏡検査の場合は、細すぎる内視鏡では難しいことが多いため、通常通り口から内視鏡を挿入して行います。
|
|
口腔から挿入
|
鼻腔から挿入
|
○
長所
|
|
・
|
内視鏡検査、処置全般に対応可能
|
|
・
|
鼻の通りが悪くても可能
|
|
|
×
短所
|
|
・
|
口の中で嘔吐反射を誘発しやすい
|
|
・
|
マウスピースをくわえる必要あり
|
|
|
・
|
通常の内視鏡は鼻腔に挿入不能
|
|
・
|
鼻の痛みや鼻出血がおこることがある
|
|
|
|