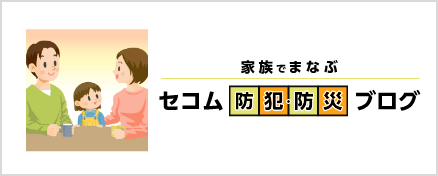第436回 ピンクリボン月間に考える「乳がんの基礎知識と検診の大切さ」
10月は「ピンクリボン月間」。
乳がんの正しい知識と早期発見の大切さを広める活動が世界中でおこなわれています。
乳がんは女性にもっとも多いがんで、「9人に1人が生涯で発症する」といわれるほど。
近年は20代・30代で発症するケースも増えており、「自分には関係ない」とはいえません。
四谷メディカルキューブの乳腺専門医 林 光博先生に「乳がんの基礎知識とセルフチェック・検査のポイント」について聞きました。

- プロフィール
-
林 光博先生
四谷メディカルキューブ 乳腺外科 部長
乳腺専門医
乳がんとはどんな病気?早期発見が大切な理由

- 乳がんとは、どのような病気なのでしょうか?

-
林医師:

乳がんは、乳房にある「乳腺(母乳をつくる組織)」にできる悪性の腫瘍です。
女性のがんでもっとも多く、日本人女性では9人に1人が乳がんを発症するといわれています。
子宮頸がんは80人に1人、子宮体がんが48人に1人といわれていますから、乳がんは女性にとって身近な病気のひとつといえるでしょう。
乳がんにもさまざまなタイプがあり、がんの種類によって、進行のスピードや転移のしやすさが大きく異なります。
たとえば、1センチ程度の小さなしこりでもすぐにリンパ節へ転移するタイプもあれば、4~5センチになっても転移しにくいタイプもあります。 
- 若い世代でも乳がんになることはありますか?

- 林医師:
若い世代でも乳がんになることはあります。
自治体の乳がん検診は40歳以上を対象としていますが、実際には30代から増え始め、20代で見つかる方も珍しくありません。
当院でも、30代の患者さんが年々増えています。
若い方の場合、心の準備ができていなかったり、正しい知識を得る機会が限られていたりすることもあり、「もっと早く情報が欲しかった」という声もよく耳にします。
乳がんは「若いからまだ大丈夫」とはいえない病気です。
一般的に20代~40代は仕事や子育てに忙しいとき。ご自身の健康と大切な家族の未来を守るためにも、乳がんについて正しい知識を持ってほしいですね。 
- 乳がんを早期発見できれば、治る可能性は高いですか?

- 林医師:
早期なら手術の負担も少なく、完治を目指せる可能性が高くなります。
近年は手術方法もずいぶん進歩し、見た目への影響や体への負担なども、昔の乳がん治療とくらべてずいぶん軽減されています。
ただ、進行してしまうと大きな手術や長期治療が必要になる可能性は否定できません。
だからこそ早期発見がとても重要です。
治療法の選択肢を広げるためにも、「定期的な検診」と「日常的なセルフチェック」がとても大切なのです。
セルフチェックと定期検診で「自分の体」を守る

- セルフチェックはいつ、どのようにおこなえば良いでしょうか?

-
林医師:
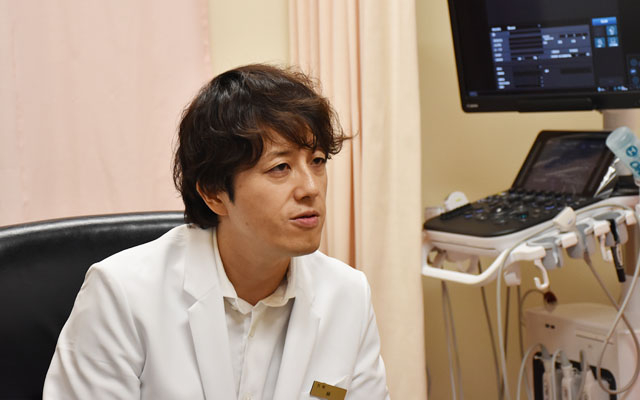
まずは「普段の自分の乳房の状態を知る」ことからはじめましょう。
乳房は月経周期などによって、かたさや張りが変わります。
「自分にとっての通常」は人それぞれです。
「自分の乳房」を知ることが早期発見の第一歩になります。
入浴や着替え、寝る前などのタイミングで、鏡で見て、手で触って、違和感がないかを意識するだけでも構いません。
月経前後や毎月決まった週にセルフチェックができれば理想です。
習慣化が難しければ、乳がんの話題を耳にした際にチェックするなど、きっかけを決めておくと良いでしょう。
最近は「ブレスト・アウェアネス(乳房への気づき)」という考え方が注目されています。
これは、日常のなかで自然に自分の乳房を意識し、いつもと違う変化に気づいたらすぐ医師に相談するという発想です。 
- セルフチェックで注意が必要な「変化」はありますか?

- 林医師:
・乳房の「しこり」
・痛みや違和感
・皮膚のつっぱりや赤み
・乳頭からの分泌(特に血が混じる場合)
などがあげられます。
ただし「しこり」がかたいから乳がん、柔らかいから大丈夫、という単純なものではありません。
乳房の状態は人それぞれで、もともと「しこり」のようなかたい部分がある方もいます。
逆に柔らかい乳がんや、「しこり」のないタイプの乳がんもあります。
「痛みはないけれど何となく違和感がある」
「言葉にできないけど気になる」
そんな感覚も早期発見のきっかけになります。
なかには、腕を伸ばしたときの「何となくいつもと違う感覚」から乳がんを見つけた方もいます。
ストレッチ中、寝る前やリラックス中など、何気ないときに違和感に気づく方もいます。
「いつもと違う」に敏感になることが、セルフチェックで大切なことです。
違和感があるときは、定期検診を待たずに、すぐ医療機関を受診してください。
乳がん検診のタイミングと検査の選び方

- 乳がんの検査にはどのような種類がありますか?

-
林医師:

乳がん検診でおこなわれる代表的な検査は「マンモグラフィ」と「超音波検査(エコー)」です。
必要に応じて「MRI」でさらに詳しく調べる場合もあります。
それぞれ得意分野が異なるため、検査を組み合わせることで精度が向上します。
【乳がん検診の「用語解説」】
・マンモグラフィとは:
乳房をはさんで撮影するX線検査。
乳房を圧迫するために痛みを感じる場合もあります。
石灰化(初期乳がんのサイン)を見つけやすいのが特徴。
・超音波検査(エコー)とは:
高周波音を使って乳房内部を調べる検査。
放射線被ばくがなく、妊娠中でも受けられます。
乳腺が発達している若い方や「高濃度乳腺(*)」の方でも「しこり」を見つけやすく、痛みも少ない検査です。
(*)高濃度乳腺
乳腺組織が発達していて、マンモグラフィで乳房が白く写るタイプの乳房のこと。
・MRIとは:
「しこり」のかたちや広がりを立体的に見ることができ、精度が高いのが特徴です。
放射線被ばくがなく、造影剤なしで受けられる痛みのないMRI検査もあります。 
- 乳がん検診では「マンモグラフィ」と「超音波(エコー)」、どちらかを選べるようになっていることがありますが...

- 林医師:
向いている検査は体質によっても異なります。
たとえば、高濃度乳腺の方は、マンモグラフィでは見えにくい場合があるので、超音波検査のほうがおすすめです。
一方で、マンモグラフィでしか見えない「石灰化型乳がん」もあるため、どちらか一方に決めるのではなく、マンモグラフィとエコーを両方受ける、あるいは交互に受けるのも良いでしょう。
乳がんの家族歴がある方などリスクが高い方は、自費(自由診療)にはなりますが、定期的にMRI検査を受けることも検討してみてください。 
- 乳がん検診はいつから、どのくらいの頻度で受ければいいですか?また検診に適したタイミングはありますか?

- 林医師:
自治体による乳がん検診は40歳から、2年に1回ですので、乳がんの若年化には対応できていないのが現状です。
早期発見のためにも、25歳を過ぎたら一度は検診を受けておくことをおすすめします。
良性腫瘍や症状がなければ、以後は1~3年おき、そして35歳以降は毎年検査を受けておくと安心です。乳がんの家族歴がある方や高濃度乳腺などリスクが高い方は、年齢にかかわらず年に1度は検診を受けておきましょう。
乳がん検診は生理中、妊娠中でも受けることができますが、生理前の張りやすい時期を避けると検査時の痛みの緩和に良いかもしれません。
妊娠中の場合は、エコー検査が良いと思います。
授乳中の方も母乳の影響でマンモグラフィが見えづらいこともあるため、エコーやMRIを中心に選ぶと良いでしょう。
- 関連するカテゴリーを見る
- 健康