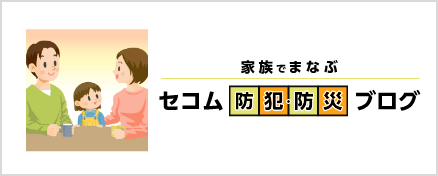第409回 夏のキャンプで気を付けたい食中毒対策

夏のアクティビティとしても人気の「デイキャンプ」を安全に楽しむポイントを紹介しています。
2回目のテーマは、食材管理や調理の安全ポイントについて。
自然のなかでの食事はひときわおいしく感じられますが、真夏の屋外調理には食中毒のリスクが潜んでいます。
前回に引き続き、安全に「キャンプ飯」を楽しむポイントをセコム医療システム株式会社の管理栄養士に聞きました。

- プロフィール
-
(左)セコム医療システム株式会社 健康サービス部長 兼 健康経営推進室長 布尾 啓明
2007年9月に入社。診療所の開設・運営支援、薬剤事業、病院経営情報分析システムの営業を担当。2019年10月より現職。(中央)セコム医療システム株式会社 健康サービス部 管理栄養士 佐藤 麻理花
2016年4月に入社。特定保健指導、働く人のための健康増進事業企画を担当。(右)セコム医療システム株式会社 健康サービス部 管理栄養士 平岡 小町
2024年4月に入社。特定保健指導、働く人のための健康増進事業企画を担当。
夏の「キャンプ飯」に潜む食中毒のリスク

- 夏は食材が傷みやすい季節ですが、キャンプ場ではどんなリスクがあるのでしょうか?

- 佐藤: 夏場の調理で特に注意が必要なのは「細菌性食中毒」です。
食材だけではなく、調理器具の衛生管理が不十分だった場合にも、細菌が原因となる食中毒を引き起こすリスクがあります。
食中毒の原因として広く知られている腸管出血性大腸菌「O157」は、生肉や生野菜をはじめ、加熱調理済み食品の二次汚染から感染します。
ほかにも鶏肉や飲料水から感染する「カンピロバクター」、同じく鶏肉や卵など十分に加熱されていない食材から感染する「サルモネラ菌」なども夏場の食中毒の原因となります。
また、「黄色ブドウ球菌」は人間の皮膚にも生息している菌のひとつで、手指に傷・化膿創のある方が素手で調理をしたり、手洗いが不十分なまま食材に触れたりすると食中毒を引き起こす可能性があります。
細菌は、涼しい季節にも存在していますが、高温多湿な6~9月に増殖しやすく、気温30℃~40℃の環境で特に活発化します。
夏場の屋外に食材を放置していたら、あっという間に細菌が増殖してしまう可能性があります。
食材が傷んでいないように見えても細菌が付着していることがありますので、キャンプ場やバーベキューなど屋外調理では注意が必要です。

- 人里離れたキャンプ場で食中毒になってしまったら...と考えると怖いですね。

-
平岡: 食中毒の主な症状として、腹痛や下痢、嘔吐や発熱などがあげられます。

我慢できるレベルをはるかに超えている場合や意識障害が出ているような場合は、すぐに医療機関に行くか救急車を要請してください。
「ちょっとおなかが痛い」とか「なんとなく吐き気がする」といった程度だと、キャンプを切り上げたほうが良いのか、すぐ病院に行ったほうが良いのか判断に迷いますよね。
心配な場合は救急安心センター事業「#7119」に電話をかけて、指示をあおいでください。
医師や看護師などの専門家が症状を把握して、適切な対応を案内してくれます。 
- 佐藤: 夏場は熱中症も心配な季節。食中毒の症状と、熱中症の症状が似ていることもあり、自己判断では適切な対処が難しいものですし、食中毒によって腹痛や下痢の症状が出た場合に安易に薬を飲んでしまうと病原菌が腸内に長くとどまって悪化することも考えられます。
無理をせず、早めに医療機関に相談してください。
夏のデイキャンプで食中毒を防ぐには?

- 食中毒を防ぐ方法を教えてください。

-
佐藤: 食中毒予防の原則として、細菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」の3つがあげられます。

【食中毒予防の3大原則】
① つけない
細菌を食材につけないためには、「手洗い」が非常に重要です。
アウトドアでは植物や生物に触れることが多く、思っている以上に細菌が手に付着しています。
調理の前はもちろん、食べる前にも手洗いを徹底してください。
川の水はきれいに見えても細菌が生息しています。
手洗いは、水道水でせっけんも使ってください。
トングやお箸などは、調理用と取り分け用を使い分けることが大切です。
調理前の生肉や魚介類などに生息している細菌が、調理器具を介してほかの食材についてしまう可能性があります。
トングや調理用のお箸は複数持って行って、「食材を焼く前に使うもの」と「焼いたあとに使うもの」は別にしましょう。
事前にシールなどを貼って分かりやすくしておくのがおすすめです。
② 増やさない
食中毒の原因菌は高温多湿な環境で増殖しますので、クーラーボックスと保冷剤を使って冷蔵環境をしっかり確保することが非常に重要です。
調理する直前までクーラーボックスに食材を入れておき、出したらすぐ調理する。
夏場は極力、食材を外気にさらさないよう意識していただきたいと思います。
また細菌を増やさないためには、調理したらすぐに食べることも大切です。
カレーやシチューなど煮込み系の料理に発生しやすい「ウェルシュ菌」は、加熱しても不活化せず、鍋底のような酸素の少ない環境で増えやすくなります。
キャンプでは大量に料理をつくることもあると思うのですが、「残ったからあとでまた食べよう」と時間をおくと危険。調理したらすぐに食べきることがポイントです。
③ やっつける
ウェルシュ菌のような一部の菌を除き、食中毒を引き起こす細菌のほとんどは十分に加熱することで死滅します。
細菌を増やさないためにクーラーボックスから出してすぐ調理する必要がありますが、食材が冷えていると表面は焼けていても中心部まで火が通っていないことがあるので、時間をかけてしっかり火を通すことが重要です。
ステーキなどレアな焼き加減がおいしい食材もありますが、夏のキャンプ場では食中毒のリスクがあるので中心まで灰褐色になるくらいちゃんと火を通してくださいね。
ウインナーなどの加工肉も、表面だけあぶるのではなく、じっくり中心までしっかり火を通すこと。
魚介類も食中毒リスクがあります。
「新鮮だからちょっとあぶるだけ」「貝が開いたらすぐ食べる」といった食べ方ではなく、しっかり加熱してから召し上がってください。

- キャンプでは生食は避けたほうが良いですね。トマトやキュウリなど生野菜はどうでしょうか?

- 平岡: 生野菜は水道水でよく洗うことで食中毒のリスクを軽減できますが、なかには水洗いでは落ちない細菌も存在します。
真夏のキャンプ場のような環境では、口に入る前に細菌が付着したり増殖したりする可能性もありますので、焼き野菜などしっかり加熱調理した野菜のほうが安心です。
食中毒を防ぐ「クーラーボックス」の工夫

- 細菌を増やさないために食材の冷蔵環境が大切とのことですが、クーラーボックスは普段から使い慣れないと管理が難しそうです。

- 佐藤: クーラーボックス内は低温に保つことが大切ですが、そのまま保冷剤と食材を同時に入れても、保冷効果があまりありません。
使用する3時間くらい前から保冷剤で庫内をしっかり冷やしておき、直前に冷蔵庫から出してすぐ食材を入れましょう。
保冷剤はたくさん必要ですが、けっこうスペースを取るので、ペットボトルの飲み物を凍らせておいて保冷剤と一緒に使うと良いと思います。 
-
布尾: 頻繁にクーラーボックスを開閉すると、すぐに庫内の温度があがってしまいます。

食材を取り出す順番を考えながら詰め方も工夫して、開閉する回数はなるべく減らしたほうが良いです。
人数が多いキャンプだと飲み物を出すためにクーラーボックスを開ける機会が増えるので、食材と飲み物は別のクーラーボックスにすると良いかもしれません。
庫内の保冷効果を継続させる工夫として、上部にアルミシートなど断熱性の高いものを乗せておくのがおすすめです。
アルミシートを半分に切っておいて、取り出したいものがあるほうだけ開けられるようにしておくと、さらに保冷効果が長持ちしますよ。

- クーラーボックスの温度管理は、キャンプに行く前からはじまっているのですね。キャンプ場に行ってから気を付けることはありますか?

- 布尾: キャンプ場に行くまでの道中、車のなかでも温度管理に気を配ってください。
クーラーボックスに直射日光があたれば温度が上昇してしまいます。
移動時間が長いとキャンプ場に着くころに庫内が温かくなっていた...ということもあるので注意が必要です。
私がキャンプに行くときは、途中のコンビニでロックアイスなどを購入してクーラーボックスに追加して保冷効果をキープする工夫をしています。
また目的地についてからもクーラーボックスを直接、地面に置くことはおすすめできません。
真夏は照り返しで地面の温度が非常に高くなるので、炎天下では、太陽の熱と地面からの熱で庫内の温度がどんどん上昇してしまいます。
できればクーラーボックスを置くための台などを用意しておき、地面に直接置かないほうが良いですね。
キャンプ場でもなるべく日陰に置くようにして、炎天下に放置することも避けてください。
* * * * * * * * *
自身もキャンパーだという布尾さん。
なるべく調理に手間をかけないこともキャンプを楽しむコツのひとつだそうです。
「レトルト食品や缶詰などもよく利用します。乾麺のパスタを茹でてレトルトのパスタソースと和えただけでも、立派なキャンプ飯。自然のなかで食べるとそれだけで十分にごちそうですよ」とのこと。
食中毒が心配な夏のキャンプでは、ゼロからの調理にこだわりすぎなくても良いのかもしれませんね。がんばりすぎず、安全に夏のデイキャンプを楽しんでくださいね!
* * * * * * * * *
<お知らせ>
企業、学校などに向けた「女性のための防犯セミナー」を無料で開催しています!
女性がねらわれやすい犯罪の対策やSNS利用時の注意点などを、セコムの女性社員がレクチャーします。
= 詳しくはこちら =
- 関連するカテゴリーを見る
- 健康