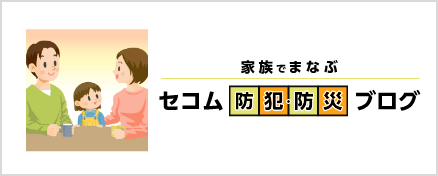第424回 SNSの「誹謗中傷」に注意!

SNSは、誰もが自由に意見し、情報を共有できる便利なツール。
一方で、「誹謗中傷」が大きな社会問題になっていることも事実です。
悪意がなくても投稿によって誰かを傷つけたり、法的責任を問われたりするケースもあります。
また、誰でも被害者になり得ることも忘れてはいけません。
もし自分が誹謗中傷の被害にあったら、どのように対応すればいいのでしょうか。
SNSを安心して利用するために、誹謗中傷をしない・されないためのポイントを押さえておきましょう。
「誹謗中傷」とは?事例で確認
SNSでは誤りを指摘しただけのつもりでも、誹謗中傷とみなされることがあります。
「誹謗中傷」とは具体的に何を指すのか、正しく理解しておきましょう。
・誹謗中傷とは
悪口や根拠のない嘘などを言って、他人を傷つけたりする行為です。
「悪意の有無」や「事実と異なるかどうか」といった点が大きなポイントですが、
「悪意のない指摘は問題ない」「事実だから誹謗中傷にはあたらない」と考えるのではなく、相手を尊重しながら投稿することが大切です。
具体的にどのような投稿が誹謗中傷にあたるのか、いくつかの例をあげます。
・著名人やテレビ出演者への誹謗中傷:悪口や根拠ない嘘など相手を傷つける書き込み。
・事件と無関係な人物への誹謗中傷:事件の加害者とは関係のない人を関係者だと決めつけたり、類似性があると決めつけたりする。
・デマの拡散:根拠のない噂を拡散し、特定の個人や団体を傷つける。
自ら投稿していなくても、再投稿やシェアで拡散させた場合も同様とみなされる場合があります。
十分に注意しましょう。
誹謗中傷をおこなうリスク
SNS投稿は、多くの人の目に触れ、瞬く間に拡散される可能性があります。
「冗談のつもり」「指摘したつもり」の投稿が思わぬトラブルにつながりかねません。
誹謗中傷にあたる投稿には、次のようなリスクが考えられます。
・法的責任を問われる
悪口や根拠のない嘘などを投稿したことで、相手を傷つけたりすると、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などに問われることがあります。
2022年7月には、特に悪質な侮辱に対処するための法改正がおこなわれ、厳しい処罰が科されるようになりました。
たとえ軽い気持ちで行った投稿でも、刑事罰や高額な損害賠償請求を受けるリスクがあることを理解しておきましょう。
・投稿を削除しても、完全に消せるわけではない
一度インターネット上に公開された情報は、スクリーンショットや転載によって拡散された場合、あとから投稿を削除しただけでは対処できません。
自分の意図に反して、半永久的にインターネット上に残り続け、いわゆる「デジタルタトゥー」になってしまう可能性があります。
・企業や学校、将来のキャリアに影響することも
SNSでの問題発言が原因で、学校や職場から処分を受けることも考えられます。
匿名で投稿しても、発信者が特定されるケースは少なくありません。
誹謗中傷をしないための心得
SNSで誹謗中傷にあたる投稿をしないためには、以下のポイントを意識しましょう。
(1)相手の人格を否定しない
相手の気持ちを考えず自分が思うままに投稿してしまうと、相手を傷つけたり、誤解を生んでしまったりする可能性があります。
誰もが自分と同じ考えでいるとは限りません。
投稿する前に冷静な判断を心がけましょう。
(2)他人の投稿を鵜呑みにせず、安易に拡散しない
SNSではデマ情報が拡散しやすく、知らずに誹謗中傷の拡散に加担してしまうこともあります。
必ず一次情報を確認すること。
情報の出どころを確認し、軽率な再投稿やシェアは避けましょう。
(3)匿名でも特定される可能性があると認識する
インターネット上では匿名での投稿が可能ですが、発信者の特定は可能です。
悪質な誹謗中傷に対して、事業者が被害者からの情報開示請求に応じるケースもあります。
「バレないから大丈夫」ということはありません。責任を持って行動しましょう。
(4)投稿する前に、一度時間を置いて見直す
感情的になって投稿してしまうと、あとになって後悔するかもしれません。
投稿する前に一度冷静になり、時間を置いて内容を見直す習慣をつけましょう。
もしも「誹謗中傷」の被害にあったら?
SNS上で誹謗中傷の被害を受けたとき、感情的に反応すると状況が悪化することがあります。
冷静に対応するために、次のような対処法を覚えておきましょう。
(1)ミュート・ブロック機能を活用する
誹謗中傷の投稿を見ないようにするため、SNSの「ミュート」や「ブロック」機能を活用しましょう。
コメント制限を設定することで、不快な投稿を防ぐこともできます。
(2)SNS事業者へ投稿削除を依頼する
SNSの運営会社へ報告・削除依頼をおこなうことで、誹謗中傷の投稿を削除することができる可能性があります。
各SNSには通報機能があるので、適切に活用しましょう。
あわせて、表示画面をスクリーンショットなどで撮り、どんな内容だったのか、だれがいつ投稿したのかなど記録を残しておくことも重要です。
(3)発信者の特定と法的措置
削除依頼だけでは解決しない場合、発信者を特定し損害賠償請求などの法的措置をとることも可能です。
2022年10月から、発信者情報の開示手続きが簡易・迅速化されました。
法的な対応を検討する場合は、弁護士や専門機関に相談しましょう。
(4)公的な相談窓口に相談する
ひとりで抱え込まず、総務省や警察などの公的な相談窓口を活用しましょう。
・総務省「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口」
・警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応
* * * * * * * * *
SNSの使い方を誤ると大きなトラブルに発展することがあります。
誹謗中傷をしない・されないために、正しい知識を持ち、思いやりをもって利用しましょう。
【あわせて読みたい!関連コラム】
・第324回 あなたの書き込みは大丈夫?SNS上の「人権侵害」に注意
* * * * * * * * *
<お知らせ>
企業、学校などに向けた「女性のための防犯セミナー」を無料で開催しています!
女性がねらわれやすい犯罪の対策やSNS利用時の注意点などを、セコムの女性社員がレクチャーします。
= 詳しくはこちら =
- 関連するカテゴリーを見る
- SNSマナー