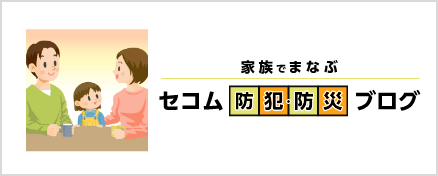第51回 【体験レポート】「池袋防災館」で地震と火災について学ぶ<3>

今年の夏は、節電対策のため夏季休暇を分散させる会社が多いようです。そうなると、行楽地も空いているのでは?空くというところまでいかないにしても、ピークを避けられれば、いつもよりゆったりと休暇を楽しめそうですね。節電のうれしい効果かも。
でも、節電により夜の街はいつもより暗いはず。それに、初めて訪れる場所では危険が潜んでいる所を知らないことも。楽しい休暇を過ごすためにも、防犯対策は忘れないでくださいね。
2011.7.4更新
第45回と第46回のコラムでご紹介した、東京消防庁が設置する都民防災教育センター「池袋防災館」(東京都豊島区)の体験レポート。その第3弾の今回は、「救急コーナー」での体験についてお届けします。
いざというとき、私たちにできること
救急コーナーでは、人工呼吸や胸骨圧迫法(心臓マッサージ)などの応急処置を体験できます。
「皆さんは、日常生活の中で突然倒れている人を発見したら、適切な対応ができますか?」と、話すのはインストラクターの宮川さん。メンバー全員、一度はCPR(心肺蘇生法)を練習したことはあったのですが、自信を持って「できます!」とは言えませんでした。
「倒れている人を見つけてから救急車が到着するまでの時間に、皆さんにもできることがあります。一人でも多くの命を救えるよう、今日練習して、いざという時に役立ててください」という宮川さんの言葉に、身が引き締まりました。
傷病者を発見してから取るべき行動は、次の通りです。
- 1.119番通報をする
- 2.AED(自動体外式除細動器)の用意を近くの人にお願いする
- 3.CPR(心肺蘇生法)を行う
「救急コーナー」では、CPRとAEDの使い方について体験しました。
命を救う応急手当・・・CPR(心肺蘇生法)
「CPRについてはなんとなく知っているけれど、実際に行えるかどうか不安」という方も多いと思います。自分の家族や友人の身に何かあったら・・・と考えると、一度は体験しておきたいものです。
宮川さんも「いざというときのために、日頃の練習が大切なんです」と、熱心に説明してくださいました。
CPR訓練用の人形を使って、実際にCPRを体験しました。主な手順は次の通りです。
 |
|
人口呼吸の様子。大きく空気を送り込まないと、 |
 |
|
心臓マッサージは、しっかりと力が伝わるよう |
 |
|
AEDの使用方法を |
- 1)意識を確認する
(傷病者に声をかけ、反応をみる) - 2)気道を確保する
- 3)呼吸を確認する
- 4)傷病者の鼻をつまみ、人工呼吸を2回行う
- 5)胸骨圧迫を30回行う
「人工呼吸を行うときは、傷病者の鼻をしっかりつまんで、鼻から空気が漏れないようにしてください」「胸骨圧迫のペースは、毎分100回です。早すぎると押しが浅くなって心臓マッサージになりません」と、宮川さん。そのほかにも、CPRの細かいポイントを教えていただきました。
実際は、4)人工呼吸と5)胸骨圧迫法を救急車が到着するまで繰り返し行うことになります。今回は、体験ということで、人工呼吸2回、胸骨圧迫30回を3セット行いましたが、たったこれだけでも、かなりの体力を消耗しました。救急車が現場に到着するのに、平成21年においては6分18秒(東京消防庁統計)、地域によってはもっと時間がかかるところもあるそうです。続けることの大変さを実感。
ですから、周りの人と協力し合って、命を救うことが大切になります。
「倒れている人が女性の場合、女性に助けてもらう方が抵抗がないのではないかと思いますよ。ぜひ、覚えてください」と宮川さんはおっしゃいます。確かに、自分が患者であれば、そう思うだろうと納得しました。
*上記は、取材時の心肺蘇生法(CPR)の手順です。2012年1月から、消防署では改正された「ガイドライン2010」に沿った手順で講習を行っていますので、こちらでご確認ください。
意外に簡単!AEDの使い方
AEDとは、Automated External Defibrillator(自動体外式除細動器)の略です。心臓突然死の原因になる、心室細動(心筋の動きがバラバラになり、心臓のポンプ機能が失われること)が起きてしまった際、AEDが自動的に解析を行い、必要に応じて電気的なショックを与え、心臓の動きを正常に戻す医療機器です。
最近では、公共の施設や学校、オフィスビルなど、多くの場所に設置されるようになったAED。見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は、AEDの使い方も体験。メーカーによって多少AEDの仕様は違いますが、基本操作は同じです。
まずはAEDのふたを開け、電源を入れます。次に、電極パッドを2枚、胸に貼るのですが、貼る位置もパッドにイラストで描かれているので、確認しながら適切な位置に貼ることができます。注意点は、汗などで濡れている場合は、体を拭いてからパッドを貼ること。その後、電気ショックが必要かどうかは、すべてAEDが判断してくれます。電極パッドを貼っても、電気ショックが必要ない場合は作動しないので安心です。
使い方は、AEDから流れる音声指示どおりに操作するだけ。いざというときに誰でも使うことができるものだということを実感しました。百聞は一見にしかずですね。
「皆さんにもできることがあります。一人でも多くの命を救ってください」という宮川さんの言葉が印象的だった「救急コーナー」での体験。池袋防災館さんで学んだことを、いざという時に役立てたいと思います。
◆【体験レポート】「池袋防災館」で地震と火災について学ぶ
過去2回の体験レポートはこちらから
第1回「地震コーナー」:地震発生・・・そのときとるべき行動は?
第2回「煙・消火コーナー」:火災発生!そのときの初動が生死を分ける