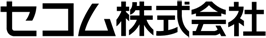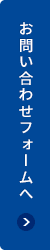開催レポート
番外編:「開校2年目の『神山まるごと高専』学生にむけて『高専OB/OG Day by SECOM』を開催」
「神山まるごと高専」は、徳島県神山町に2023年4月に開校した5年制の私立高等専門学校で、「テクノロジー×デザインで人間の未来を変える学校」をコンセプトに、社会に変化を与える人材の輩出を目指しています。
セコムは、同校において、奨学金基金を拠出するスカラーシップパートナーの一社として、次世代の起業家を目指す同校学生たちがビジネスの在り方を体系的に学べるよう、外部との戦略的な協働を担う「セコム オープンイノベーション推進担当」がプログラムを担い、アントレプレナーシップに関する月例カリキュラムなどを実施しながら高専およびセコム奨学生をサポートしています。
今回は、セコムの行うアントレプレナーシップ講座の特別回として、セコム奨学生を含む同校学生にむけて、高専を卒業して活躍している方々によるキャリアトークイベント「高専OB/OG Day by SECOM」を開催しました。開校2年目で二学年までしかいない出来立ての高専で、日々ルールメイクしながら次世代の活動をつくっている学生にとって将来のキャリアの示唆や選択肢を考える機会にしてもらうことが目的です。
セコムのオープンイノベーションチームが日ごろ懇意にしている外部エグゼクティブの方々やセコムグループ内の高専卒業者による、高専時代の話題から卒業後の現在に至るまでのざっくばらんなキャリア談義や、フロアの学生もまじえた高専特有の世界感から生まれるカジュアルなトークなど、高専生以外にとってもたいへん示唆深いディスカッション機会となりました。みなさま是非ご覧ください。
開催日時
2024年11月18日(月) 15:00~17:00
開催場所
「神山まるごと高専」大講義室(徳島県神山町)
登壇者
-

株式会社セブン銀行 代表取締役社長
松橋 正明氏
出身高専は釧路高専。2003年セブン銀行入社(当時アイワイバンク銀行)。2009年にATMソリューション部長となり、その後、常務執行役員、専務執行役員などを経て、2022年6月に代表取締役社長に就任。セブン銀行にイノベーション文化を根づかせるべく、2016年に設立したセブン・ラボの初期メンバー。「セコムオープンラボ」にも初期より参加。
-

事業構想大学院大学 特任教授
関 孝則氏
出身高専は仙台電波高専。日本アイ・ビー・エムにてテクニカルセールス本部 ディレクター/技術理事、セールスフォース・ドットコムにて先進技術ソリューション本部 常務執行役員、Slack Japanにてエグゼクティブ・パートナーを経て現職。東京理科大学大学院にて経営学研究科技術経営専攻(MOT)教授も務めた。新しいIT技術にかかわる新規事業開発やスタートアップ、テクニカルセールスの統括、技術経営(MOT)の社会人教育などで、30年以上の経験を持つ。「セコムオープンラボ」にも初期より参加。
-

セコム株式会社 技術開発本部 クラウドエンジニアリンググループ マネージャー
田中 拓朗
出身高専は徳山高専。山口県出身。セコム入社後、大阪での警備員勤務を経て技術開発本部へ異動。大型施設向け警備システムの開発を担当したのち、2014年から1年間、グループ会社である韓国エスワンへ出向。帰国後、Tokyo2020オリンピック関連の業務を担当したのち、現在はクラウド活用推進組織のグループリーダーとして活動中。
-

セコム株式会社 技術開発本部 サービスロボット開発1グループ
谷口 太一
出身高専は大阪府立大高専。1998年生まれ。高専本科(5年)の後、同高専専攻科(2年)で学ぶ。その後、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科へ進学。セコムドローンやセキュリティロボットcocoboに惹かれて、2023年にセコム入社。現在サービスロボット開発1グループにて開発業務に従事。
-

セコム株式会社 IS研究所 研究企画推進部 主務
小松原 康弘
出身高専は明石高専。高専・大学・大学院においてレジリエンス・防災関連を研究。2009年にセコム入社。警備員勤務を経て、技術支援部門や本社企画部門の業務に携わった後、経済産業省へ出向。2022年から現職。現在はレジリエンス分野を中心に中長期を見据えた研究企画を担当。京都大学大学院情報学研究科修士課程修了。グロービス経営大学院修士課程修了(MBA)。
-

セコムトラストシステムズ株式会社 サイバーセキュリティ2部
市橋 明莉
出身高専は東京工業高専。2022年にセコムトラストシステムズ入社。セキュリティエンジニアとして、大学等での講師活動やセコムグループ全体に向けたレポート発行などの啓発/技術広報活動を担当。最近では、サイバーセキュリティ関連の新規サービスの企画・運用にも携わる。
モデレーター
-

セコム株式会社 本社オープンイノベーション推進担当
出口 宙伯
出身高専は長岡高専。1980年生まれ。長岡技術科学大学大学院 電気・電子システム工学専攻 修了後、セコムトラストシステムズに入社。法人向けSaaS「セコム安否確認サービス」や大規模災害対策サービスの開発・企画業務を経て、現在サイバー攻撃対策サービスの新規事業立ち上げに従事。2024年よりセコム本社のオープンイノベーションチームを兼任。
1.イントロダクション
セコムの月例アントレプレナーシップ講座の特別回として同校学生に向けて開催された「高専OB/OG Day by SECOM」。会場となった大講義室には同校1、2年生とスタッフらが参集しました。はじめに、本イベント開催の背景をセコムオープンイノベーションチームの代表沙魚川からご案内し、イベントの開始となりました。
沙魚川
「神山まるごと高専」、卒業生はもちろんおらず、まだ2学年しかないなかで、今後のキャリアを考えるときの悩みもあると思います。今回お呼びした高専経験者のみなさまのキャリアを聞くことで、さまざまなケースを知ってもらいたいと思い企画しました。
ケースや定石を知ることは、悩んだときの選択肢を増やすことにつながるんですね。一つひとつのケースをコピーして欲しいわけではなくて、自分のキャリアに悩んだ時や決断が必要な時に、ケースを何も知らないと何をどう考えたらいいか分からない。ケースを知っていれば悩んだときに選択肢が増える。そう役立ててもらえたらと思い開催させていただきます。
2.自己紹介
続いて、登壇者の自己紹介です。今回は、セコムのオープンイノベーションチームが日ごろ懇意にしている外部エグゼクティブのお二人と、セコムグループ内の高専卒業者数名をお呼びしました。
出口 宙伯(以下、出口)
モデレーターを務めます、セコムオープンイノベーションチームの出口です。名前に「宙」の文字に縁を感じ、宇宙産業に関わりたいと思い、また、大学受験がなく研究に集中できることも魅力で高専へ入学しました。よろしくお願いします。資料も準備いただいていますので、松橋さんから自己紹介お願いします。
松橋 正明(以下、松橋さん)
高専の機械科を出て、メーカーに勤務していました。IT化されていない産業を機械化・IT化するということをやっていましたが、イノベーションに取り組みたいと思ったところから、沙魚川さんとの関係があって、今日ここにいます。
また、社長と紹介いただきましたが、私の本業はビデオ編集です(笑)。(自己紹介の中で、自作の動画を投影)最初は趣味でビデオ編集をしていたのですが、これが意外にも本業にも活きているんです。編集中に、このエフェクトが良いと感じたら、自社のATM画面に組み込んでみたりすることもあります。
今日はよろしくお願いします。
関 孝則(以下、関さん)
就職はIBMで最後は技術担当の理事をしていました。その後、Salesforceで役員をしたときに、日本の教育に携わりたいと思って東京理科大で教鞭をふるっていたのですが、どうもやり残したことがあると思って、みなさんも使っているSlackにjoinする、というキャリアを歩んできました。沙魚川さんとも古くからサービスのイノベーション話をする間柄で。現在は、平均年齢30代後半の方々が通う事業構想大学院大学で特任教授をしています。よろしくお願いします。

田中 拓朗(以下、田中)
徳山高専を卒業してセコムに入社し、警備の現場を経て開発部門へ移動し大型施設向けシステムの開発に従事していました。その後、韓国でサムスングループとセコムで設立したグループ企業エスワンに出向し、帰国してからは飛行船などイベント系システムの開発に携わってきました。
はじめての徳島で、みなさんに会えるのを楽しみにしていました。
谷口 太一(以下、谷口)
入社2年目でかなりぴちぴちです!大阪に住んでいたので大阪で進学してきたのですが、ロボットをやりたいという想いから高専を選びました。セコムに入社してからは、希望していた開発部門で、「セコムドローンXX」の開発に従事しています。よろしくお願いします。
市橋 明莉(以下、市橋)
私は高専に行く前に普通高校に入学していて、卒業後に東京高専の情報科に編入しました。セキュリティエンジニアとして、講師活動やセコムグループ全体に向けたレポートの執筆などを行っています。よろしくお願いします。
小松原 康弘(以下、小松原)
セコムの研究所で企画担当をしています。主に研究所の研究内容と事業部門の課題とのマッチング・コーディネートを進めています。「神山まるごと高専」には、個人的にも注目していて、今回来ることをとても楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。
3.パネルディスカッション
パネルディスカッションは、登壇者らのディスカッションと並行して、Slidoサービスを使用してフロア参加者のスマホからも質問・相談を受けつける形で進行。序盤から次々と質問が投げ掛けられ、カジュアルに議論が進みました。
出口
プロフィールについて、もう少しお伺いさせていただければと思ったのですが、松橋さん、高専は機械専攻ですが仕事ではUXまで手掛けていますよね。UXデザインを志したキッカケについてお伺いしてもいいですか?
松橋さん
高専では、機械工学専攻だったのですが、ソフトウェアがやりたくてメーカーのNECに行きました。結果的には、最初はソフトでなく機械設計をやって、そこからやりたいことを企画していって転職もしたのですが、とにかくやりたいことに対して、まずは関連技術を身に着けるようにしていました。UXもその流れです。今思うとすごく自由にさせてもらってたと思います。
出口
なるほど、まずは技術で語ろうと。そこに高専経験が活きているわけですね。
みなさんはどうですか?
田中
普通の高校のように、2年後にまた受験というのはどうだろうという思いで高専を選びました。今思うと、在学中は好きなことに打ち込めたかというとそうではないのですが、一方で幅広く技術的な素養は全部舐めさせてくれたので、その知識と経験は仕事で大いに役立っていると感じています。
谷口
研究では、今思うとまだまだだったなと思うのですが、サービス提供するロボットに必要そうな技術を詰め込んだロボットを作るというのはやっていました。骨格検出させてその人を追従させたり、顔認識させて特定の人に挨拶をさせるとか、やっていました。

市橋
編入した年がコロナだったので、編入したはいいけどずっと家に居る…みたいなそんな生活でしたね。みなさんのようにやりたいことをやったかというとそうではなくて、高専では3年生までに高校三年間と大学一年生までの学習内容が終わっているので、授業についていくのがやっとという状況でした。
小松原
高専は大学入試が無かったというのもあって、野球部の活動など、とても自由に楽しくやっていました。一方で非常に自律を求められたなというのは今でも感じています。進級ハードルが高く、5年間を通して学年の半分程度しかストレートに卒業できなかったりしました。同級生で留年する人もいれば、上の先輩で留年してくる人もいたりしました。
関さん
私の高専は当時、仙台電波高専。電波通信と言えば船舶、卒業したら「船乗りになりなさい」と言われるような船乗り養成学校でした。そんなところにコンピューターが一台置かれたんですね。当時は貴重なものだったので、必要な試験をクリアした人だけが使える免許制でした。そんなコンピューターが面白かったので、コンピューター部を作りました。文化祭では、何をやろうかとなった時、乱数にハマっていたんですよね。そして、乱数をつかって占いをやったところ、行列が出来て大盛況でした。そこで、コンピューター×コミュニケーションを掛け合わせると、こんなことができるのかと思い、コンピューターがコミュニケーションに大きな影響を与えることに気付き、興味を持って行ったというのがありました。
出口
関さんのSalesforceやSlackなどデジタルコミュニケーションへの志向は高専時代の経験に端を発しているんですね。
会場からも既にたくさん質問いただいています。
「高専卒の後のキャリアを意識したのはいつぐらいからですか?」

小松原
私の場合は、高専になぜ入ったのかと思うと、阪神大震災で被災して何かできないかと思い、高専がレジリエンス・防災など専門分野が早くから勉強できる場所だったから。今でも継続してレジリエンス・防災関係の仕事に取り組んでいます。キャリアというのは、いつからというよりはさまざまな経験を通して自然と変わっていくものでもあるのかなと思っていて、それも大切なのかなと思いますね。
出口
市橋さんがサイバーセキュリティをやりたいと思ったのはいつごろだったんですか?
市橋
みなさんはホワイトハッカーって知ってますか?私は中学2年生の時なりたいと思ったのですが、そのまま普通高校に入学したんですね。で、なりたいと思う気持ちとは裏腹に何を学べばいいかわからずに時間だけが過ぎていって、知識を付けるために高専編入の道を選びました。高専卒業の進路相談で、改めて先生に相談したら、学生ではなくて早く現場に出る方が良いというアドバイスをもらって、セコムグループに就職しました。
谷口
元々、漫画/アニメのロボットが好きで、ドラえもんや攻殻機動隊のタチコマが作りたいなと思っていたんですね。高専を卒業するタイミングで、タチコマのようなAIを実装したロボットはまだないなと思って、それを勉強できる大学院に進学しました。大学院を卒業するとき、工場の製造ラインロボットのような産業用ロボットではなくて、前述の通り、人とコミュニケーションを取れるサービスロボットをやりたいと思っていたので、セコムを選びました。
出口
他にも質問が来ていますね。
「仕事においてやりたいことを進めると、社内の抵抗も相応にあると思います。それらの抵抗をどのように乗り越えてきましたか。」
松橋さん
UXという概念がない状況で、UXの説明は理解されないので、黙ってやっちゃってましたね(笑)。そういうとちょっとずるく聞こえるかもしれませんが、開発側の有利な点はモノを作れることです。作ってしまえばその重要性を説明できるんですよね。
あとは、高専時代はすぐに謝ってましたね。逃げることも大事ですね。
関さん
私は結構好きなことで、好奇心が湧くことに仕事をずらしていくようにしていました。IBMにいると、一年目から社長になりたいという人が居たのですが、別に私は社長になりたいわけではないし、好奇心を満たしたい、それをコミュニケーションに使いたいし、コンピューターで変えたら面白いよねとかばかり考えていましたね。
最近は企業のなかで手を挙げて部門を移るって増えましたよね。キャリアを自分から申告するようになっています。今後もこの流れは続くと思いますね。
松橋さん
キャリア構築のスキルは興味があったら勉強してもいいと思う。キャリアセレクタビリティと言って、キャリアを自分でつくる力。
関さん
キャリアを自分で作っていくという流れはどんどん強まっていっている。エネルギーが出る仕事というのが、自分にとって力も出せるし、スキルもつくし、一番良いんじゃないかなと思います。
そういった仕事が社内にあるのであれば、そこを目指すと良いと思いますし、無いのであれば転職すればいいと思う。

出口
関さんにちょうど質問がきていますのでお聞きしますね。
「高専の学びや知識、経験は米国でも活きましたか?」
関さん
知識というより、勉強の仕方は通用しましたね。私の時代はコンピューターがどう動いているかというのは教えてくれなかったんですね。先生に聞くと、メーカーの作るマニュアルを渡されてこれでも読んでみなよと言われ、何度も何度も読んで、試行錯誤しながら理解していきました。
で、大人になってみると仕事のやり方に正解はないので、この試行錯誤しながら理解する経験が、仕事をしている中で非常に活きましたね。
普通の高校ではこんなやり方しないでしょうし、時間をかけて何度も何度も読んだこのやり方を経験させてくれた高専には本当に感謝していますね。
出口
関さんからの外資つながりで言うと、韓国のエスワンはどうだったんですか?
田中
向こうでは研究所に所属していました。サムスンとの合弁会社で、優秀な方も多くて、出入りも激しかったですね。同じグループの方々は38度線の警備システムの開発を担当していました。現場を飛び回っていて、みんな集まって歓迎会を開いていただいたのは、5か月後とかでしたし。いろんな環境でも馴染むことができたのは高専の経験があったからかもしれません。
戻ってきてからはイベント関連のシステム開発に携わり、現在はクラウド活用推進を担当しています。セコムは自前でサーバーを立てて管理するオンプレミスの手法を多く取っていましたが、拡張性や運用コストなど様々な課題があります。クラウド活用による課題解決とサービスの進化を図るため、仲間を集めて勉強し徐々に社内でも利用できるようになってきました。
出口
いっぱい質問来ているので、どんどん行きますね!
「新しい学生に役割を引き継ぐのはとても時間と労力がかかり苦手なのですが、会社内で引き継ぐのってどうやられていますか?」
谷口
私もつい最近一つ上の先輩が異動になって引き継がれる側をやったばかりなのですが、とても苦労しました。やった作業や手順をまとめる際に資料を作っていれば理解も深まるので、引継ぎの資料・手順書を残すというのはとても大切なことなんだなと思って、私は新しいことをやるときは特に資料を残すようにしていますね。
出口
プログラミングもそうですよね、コードを作りつつ、思想の部分をどう考えてやっているのかというのを残すのは大切ですよね。
松橋さん
私もかつて一匹狼でしたが、持続的に成長をさせるためには、チームでやっていることが大切なんですよね。チームでやるってことはチームメンバーが理解しなければいけなくて、それを伝える過程で思想ややり方を伝える必要があるんですよね。地域の活動なんかも持続させるためにはチームでやることが大切なんですよね。
あと、単純に複数人でやれるようになればアウトプットも何倍にもなるしね。

フロアの学生
私が立ち上げた部活では、やりたいと手を挙げた人のところに人が集まって活動が始まるんだけど、熱のある人が居なくなっちゃうと活動が無くなって、その部活が形成しているコミュニティも無くなってしまうんですよね。それが難しくて。
関さん
想いを繋ぐという話なのかな?そうでないのであれば、その前から人と人を繋げていくというのが良いかもしれないね。みんなの共感を生むというのかな。
想いを継ぐという点で言うと、仕事の話だけれど、普通だったら1年かけて引き継ぐような仕事を二週間で引き継げということがありました。これは大変だったね。そこで何をしたかというと、とにかく質問したおした。相手も言語化が上手い方だったのと、お互い引継ぎ時間が限られていて必死だからとにかく質問して答えてということをしていた。
質問するって言うのは、自分がこれを分かっていないということを相手に示す行為で、それが無いと相手は私がそれを知らないことが分からないんですよね。これでもうめちゃくちゃ質問しまくって引継ぎやりきったということがありましたね。
で、これからの時代というのは、この質問する力が大切なんです。なぜかというと、今の時代はAIが答えを出してくれるので、うまい質問ができるかが求められるようになっていくんです。
出口
面白い質問が来ていますね。
「神山はまだ1-2年生しかいません。5年生までが同居するようになったらどんな感じですか?」
関さん
5年も同じ暮らしをしたら、お互いの弱みも強みも知る、心許せる仲になりますよね。と今では言えますけど、当時は本当に最悪でしたね(笑)。縦社会で(笑)。でもほんと5年間の寮生活というのは本当に貴重な経験が出来てよかったなと思いますね。

小松原
うちも、今思えばなかなかひどいところだったんだろうと思いますね。同じく縦社会で(笑)。で、さっき言ったようにうちの学校は成績に厳しくて5年間を通して半分留年するという話をしたと思いますが、あるときから寮で麻雀が流行ったんですね。ちゃんとルールを決めて守ってやらないと、高専って自由すぎて堕落してしまうので、麻雀には気を付けて下さい(笑)。ちなみにうちのクラスもそれで大勢留年しました。
関さん
アメリカの会社でもそういう上下関係はある程度あるわけですよ。人事を握られているし、上下ですから。でも、面白いのはレクリエーションとかになると、友達というわけではないですけれど、急に対等になるんですよ。組織は組織、オフはオフでとても社会として成熟していてかっこいいなと思いましたね。
田中
学生として1-5年生の幅の人と同じ学校にいて、同じ部活をして、同じ寮で暮らしてというのは本当に貴重な経験でしたね。だって15歳で入学した瞬間に20歳以上のおっさんがいるわけですよ(笑)。さらに「神山まるごと高専」は自由に設計されていて、さらに社会の人と関わる機会も環境もあるというのは、素直にとてもうらやましいと思います。
出口
話は変わるんですが、私マクドナルドでアルバイトしていたことがあるんですが、聞いたところによると、松橋さんもマクドナルドでのアルバイト経験があるとお伺いしたのですが。
松橋さん
そうです。私、マクドナルドでバイトしていて、ほぼマネージャーでした(笑)。あったら絶対にやった方が良いですよ。グローバルなマニュアルと接客を学ぶことができるから。学生のときにやったアルバイトで一番いいものだったと思ってますよ。
関さん
日本のマクドナルドの人事トップと話したときに、役員クラスが入ってくると、身分を隠して半年ほど現場で働く。すごくフラットな対等な関係でノウハウを継承していくという文化があって、とても良い文化だなと思ったことがありました。
松橋さん
私も、セブン銀行に来た時にセブンイレブンで研修を2週間受けましたよ。身分は隠してなかったんですけど、アルバイトの先輩に「あら、新人さん?よろしくね」って言われながら学びましたね。
関さん
バイトで言うと、神山のみなさんはプログラミングができるなら、フリーランスのサイトとかでいくらでもできるんじゃないですか?私も学生時代プログラミングでバイトして、当時は1行いくらの時代で、プロの人が自分たちよりも10円高くて、社長に直談判しに行ってレベル変わらないんだからと給料上げてもらったなって記憶がありますね。そういうところまで含めて良い経験できたなと思いますね。
出口
もしみなさんが「神山まるごと高専」の学生だったら?どうしたいとかありますか。
谷口
自分の場合、ロボットの部活に入らず、バレーボールの部活に入ってしまったのは今でも思うことがあるので、やっぱりロボットの部活に入って、もっと思いっきりロボットに打ち込みしてみたいなと思いますね。
市橋
私の場合通学だったので、寮生活やってみたいなと思いますね。部屋が繋がってて何人かで生活しているというのを聞いてすごく楽しそうでうらやましいなと思っていますね。
田中
打ち込めることが見つけられなかったので、もう一度高専に行けたら、特に「神山まるごと高専」なら、きっと、もっといろんなことにチャレンジして、何か見つかるんじゃないかなと思いますね。
松橋さん
私はDCON(高専ディープラーニングコンテスト)ですね。テレビを見ているといつも楽しそうだなと思うので、出てみたいですね。あと、当時に戻れるなら動体視力を使って、APEX(ゲーム)で世界ランキングに挑戦したいですね。最近はやっぱり駄目ですね(笑)。
関さん
プロジェクト系は素直にうらやましいですよね。私は色々こっそりやるということばっかりやっていたので、「神山まるごと高専」ならこっそりやる必要もないし、自由にみんなと一緒にやれるのはうらやましいですよね。学生時代にそういう環境でやれていたら、もう一皮むけていたのかなと思いますね。
出口
学生さんから直接聞きたいということなどあればいかがですか?
フロアの学生
僕がもし企業に勤めていたら、海外の企業と一緒に海外で働きたいなと思います。MBAも会社のお金で取れたら嬉しいななんて思っていますね。
関さん
会社員時代に社内のMBA募集に落ちてしまったという経験があって、今はMBAで教える側やってるんですけどね(笑)。
最近は、技術部門の最高責任者は、MITを出ているけど途中でハーバードのMBAも取ってましたなんて人がそこかしこにいるんですよ。こりゃ敵わんなと思いもっと勉強しなければと思いますね。ダブルメジャーという二つの専門を持ち、両方を極めるような人がすごく求められていますし、日本の人にもっとそうなって欲しいなと思いますね。
出口
名残惜しいですが、お時間もそろそろなので、最後に沙魚川さんからお願いできますでしょうか。
沙魚川
冒頭にもお伝えしたんですが、ケースというのは当時のその人の話ではあるけれど、その話を知っておくと、自分がいざ同じようなシチュエーションを迫られたときに選択肢が増えるんですね。
関さんも今ダブルメジャーについてお話をされていたけど、そもそもイノベーションというのは何かと何かの掛け合わせですよね。人の成長やキャリアについても同じで、みんなも何か一つ好きなことを突き詰めて、それプラスもう一つ組み合わせたら面白いかもというサブとなる専門性を身に着けると、ユニークな人になれると思っています。ユニークな人っていうのは、絶対に一生価値があるから、自分の一本柱の専門とサブとなる専門というのを意識していくといいのかなと思います。
「神山まるごと高専」は素敵なところだけれど、自分の参考になる先輩がいないというのはハンディキャップだとも思うので、今回こういう企画を用意させていただきました。
また、違う形になるかもしれないですが、今後もこういった機会を提供していけたらと思っていますので、楽しみにしていて下さい。
4.アフターセッション
終了後も学生との対話が続き、登壇者全員で学生と食事を取りながらコミュニケーションをしていました。
今回の企画が、参加した学生への新しい刺激になることを期待しています。
終了後に参加者で記念写真
セッション後も、遅くまで学生が登壇者とキャリアや人生について話し込んでいた
神山の宵闇に浮かぶ高専キャンパス
終了後、学生とともに「神山まるごと高専」の地産地食の給食を食べながら懇談が続いた