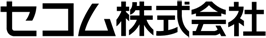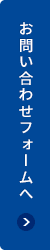今回は、「すべてはつながるその先は ライフとビジネスのアップデート」をテーマに、「すべてがつながる」社会に向けた期待や希望、価値観についてデザインワークショップ形式でディスカッションを開催しました。大企業やスタートアップ、行政機関など産業界の参加者に加え、セコムが支援しながら全寮5年制で起業家精神を学ぶ「神山まるごと高専」の学生たちも参加し、世代を超えて「つながるの先」にある暮らしやビジネスのアップデートを探ります。
2025年、20年代も折り返しです。Society5.0の拡がりとIoTの伸長、デバイスとサービスの高度化によって、さまざまなモノやコト、ヒト、社会がつながってきました。 20年代後半にむけて勢いは加速し、すべてがつながる世界観が拡がっていきそうです。 モノや人のコミュニケーションだけでなく、AIによる適切な情報提供、人間拡張による人の可能性のひろがり、グリーン化による環境配慮など、暮らしやビジネスはどのように変化するのでしょうか。
話題提供では、IoTのプラットフォームを提供する㈱ソラコムのCEO of Japan齋藤洋徳様より、SORACOMのサービス立ち上げ秘話、Society5.0に近しい事例やパートナー同士のつながりから生まれた化学反応などをインプットいただきました。
続くワークショップでは、世代や背景、価値観や視点が異なる多種多様な参加者が、それぞれの視点から「つながるの先」について互いの価値観を共有しながら分野横断的に対話を深めました。「つながる」による光と陰など、体験やベネフィットあるいは技術的な課題を紐解きながら、未来の社会に繋がるアイデアに議論を展開しました。
今回は、「すべてはつながるその先は ライフとビジネスのアップデート」と題して、大企業やスタートアップ、行政機関産業界の参加者に加え、起業家予備軍としてセコムが支援しながら全寮5年制で起業家精神を学ぶ「神山まるごと高専」の学生たちも参加。100名超のデザインワークショップ形式でアイデアディスカッションを開催しました。
2025年、20年代も折り返しです。これまでさまざまなモノやコト、ヒト、社会がつながってきました。20年代後半にむけて勢いは加速し、すべてがつながる世界観が拡がっていきそうです。
みなさんは、何と何をつなげたいですか?そのベネフィット・体験に何を期待しますか?
「すべてがつながる」社会に向けた期待や希望、価値観の拡がりを確認しながら、「つながるの先」にある暮らしやビジネスのアップデートを探るのが今回の目的です。
冒頭、イントロダクションでは、多様な視座による価値観の探索とコミュニケーションを重視した「セコムの“共想”」と、セコムオープンラボが持つ意味、オープンイノベーションによって結実した新たなサービスなどをご紹介。今回のテーマに込めた背景について共有しながら、議論のトーンを整えていきました。
今回は、「すべてはつながるその先は ライフとビジネスのアップデート」というテーマにあわせ、IoTのプラットフォームを提供する㈱ソラコムのCEO of Japanを務める齋藤洋徳様より話題提供をいただきました。SORACOMのサービス立ち上げ秘話をはじめ、SORACOM が実現したSociety5.0に近しい事例を紹介しながらさまざまなニーズやご経験を踏まえた話題をインプット。フロアからの質疑も多数いただき、参加者全員で理解を深めました。
続くワークショップでは、62企業/官庁などからの100名超の参加者が14グループに分かれてそれぞれの視座からディスカッション。ワークタイムを細かく区切り、議題を変えながら、一人ひとり異なる「つながる」の体感値や今後の期待について、様々な視座・価値観・専門性より議論が展開されていました。「つながる」による光と陰などの体験やベネフィットから生まれる感情の変化を可視化しつつ、発散と収束を繰り返しながら、新たなニーズをアイデア提案へと昇華させるアプローチです。
ワークショップの前半戦は、「つながる」の現状に纏わる課題探索の時間帯です。一人ひとりの事例を交えて課題を掘り下げ、発散させながら議論を進めます。
「つながる」ことで得られる体験やそれにより出てくる課題感もあれば、「つながらない」ことによる不便や利点もあります。背景にある感情や日ごろ感じるもやもや感などの非言語的メッセージを、多彩な切り口から可視化していきました。
今回の軽食には、テーマである「つながる」というキーワードにあわせて、“つなぐ・むすぶ・フュージョン”をコンセプトに“縁をむすぶ”「おすしおむすび」や“フュージョンな”「フルーツサンドイッチ」などのフード、「新感覚むぎ茶」や「ミックスフルーツジュース」などのケータリングを用意。コミュニケーションが進む議論の場を演出しました。
途中、コーヒーブレイクタイムには、参加者が大きく移動して他グループと交流し、更なる多様性を取り込みながら、マッシュアップを進めました。
コーヒーブレイクを挟んだ後のワークショップ後半戦では、前半で出てきた「つながる」の現状を参考にしながら、グループ毎に「つながる」先の未来や新しい当たり前につながるニーズ・アイデアを提案。時代観をとりこんだベネフィット検討や、影の部分を解消する仕組みなど、価値観や課題、その裏にある感情を丁寧に紐解きながら、未来の社会に繋がる議論が展開されました。
ここで出てきた、幾つかの興味深いアイデアを簡単にご紹介します。
- 若者は常につながりを求められているが、SNS疲れや自己肯定感の低下という課題も存在。一方で、高齢者はネットにつながらないと生活必需品や行政サービスにアクセスしにくくなっている。同世代がつながることの課題を、異世代がつながることで回復していく共助ソリューション。
- 現代人は繋がることが当たり前になり、それが生活しにくさも生んでいるが、非常時/慣れない場所/困っている時に周囲から助けがあるのは有難い。そういう状態を認識して、つながる範囲や情報量を拡張制御する仕組みを提案。
- つながりたい(管理したい)人と、つながりたくない(管理されたくない)人の間に非接続ユートピアというクラウドを用意し、スマホなどの機器からつながる際にユートピアモードを選択することで、「つながることの安心」と「つながらないことの心の平穏」のどちらも実現する仕組み。
- 動物の脳波を解析し、ソラコムの通信デバイスを使い、動物と意思疎通して共生。人手不足の解消、新たな多様性、温かみを訴求。
- 自身のプライバシー(仕事帰りに飲みに行く、サウナにいくなどのリフレッシュ)は確保しつつ、自身のアバターがSNS上で適切な会話でコミュニケーションしてくれるサービス「プライバシーオンデマンド」。自分がつながることによる無駄な消費時間はアバターが代わりに対応してくれるので解消、SNSに縛られ踊らされることは回避できる。つながりながらつながっていない、つながりたいときはつながる、という世界感。
- 亡くなった人とも繋がりたいが、繋がりすぎずという距離感が重要。いつでもどこでも繋がると価値がない。たまに会うくらいがちょうどいい。年1回の再開の場など。
ワークショップ後には、大判のアイデア整理シートに各テーブル内での議論と提案アイデアをまとめ、その成果を発表して参加者全員でシェア。
参加者全員による投票を行い、もっとも多く共感を集めたグループを「最優秀共感賞」、次点を「優秀共感賞」として表彰しました。賞に選ばれたグループには、今回開催日である2月26日「つつむの日」にちなんだ「焼売セット」を副賞としてメンバーみなさまにお贈りしました。
今回のセコムオープンラボは、20年代後半にむけて加速する「すべてがつながる」世界観をキーワードに、ニーズや普段感じている課題感、違和感などの非言語化メッセージを可視化し、共有することで、対話を深めていきました。全く異なる視座・価値観を持つ者同士の意見が交差することで、数多くの興味深いアイデアが次々と生み出され、参加者間で多くの気づきと新しい交流が生まれる場となりました。
ここで議論されたアイデアや、多種多様な視座からの未来像や課題感は、セコムを含め、参加者それぞれが持ち帰り、各々の視点から新たな“気づき・きっかけ”として活用いただけることと思います。この場を起点に、みなさまの想いが更に高まり、新たな創発が起きていくことを期待しています。