|

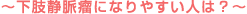
比較的女性に多い病気で、出産などを契機に20代後半ごろからでき始めることが多く、成人女性の実に45%に認められるとの報告もあります。
また、家族(母娘、姉妹など)に静脈瘤のある方も静脈瘤になりやすい事がわかっています。
男性では、調理師などの立ち仕事の方によく見られます。
特殊なものでは前出の脚の深部静脈が詰まる病気(深部静脈血栓症といいます)になった後に、二次性の下肢静脈瘤になりやすくなります。
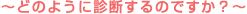
血管が浮き出ている方は、見ただけで「下肢静脈瘤」という診断はすぐにつきます。
しかし、血管が浮き出る以外の症状が前面に出ている方や、適した治療法を選択するためには、逆流を起こしている「表在静脈」や「交通枝」を確認する必要があります。
以前は脚の血管に直接造影剤を入れてレントゲンを撮影する「下肢静脈造影検査」という検査が主流でしたが、造影剤アレルギーや、造影剤が漏れた際の痛みなどの問題もありました。
現在は体の外から血流を確認する「ドップラー検査」「超音波検査」により、体に負担なく静脈瘤の診断や逆流部位の診断が可能となりました。
さらに3D-CT検査の出現により、おおまかですが一度に「交通枝」の場所を確認することが可能になっています。
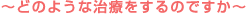
治療は静脈瘤の種類と逆流の場所、さらには患者さんの生活様式・希望によって変わってきます。
大きく分けて4種類の治療が存在します。
逆流を起こしている静脈を引き抜いてしまう「ストリッピング手術」、逆流を起こしている部位を縛ってしまう「結紮術」、逆流を起こしている静脈内に特殊な薬を入れ、静脈の内腔を閉鎖してしまう「硬化療法」、静脈瘤を弾性ストッキングなどで機械的に圧迫する「圧迫療法」などがあります。
実際にはこれらを組み合わせて、治療を進めていきます。
|