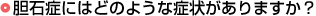 |
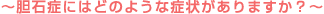
 胆嚢結石があるからといって、必ずしも症状があるわけではありません。 胆嚢結石があるからといって、必ずしも症状があるわけではありません。
胆嚢結石をもっている人の23%は無症状といわれていますが、ひょっとするともっと多いかもしれません。
症状には自分でわかる「自覚症状」と検査などで分かる「他覚症状」があります。
胆嚢結石症の自覚症状のNo.1は右季肋部痛(みぎきろくぶつう)です。右の肋骨の下あたり(右肋弓下)に差し込むような痛みを感じます。背中に抜けるような痛み(放散痛)を伴うこともあります。
胆石の痛みは決まったところだけが痛むのではなく、人によっては、みぞおちが痛かったり(心窩部痛)、おへその上のほうが痛かったり、右の肩甲骨(けんこうこつ)の下の方が痛かったり、腰が痛かったり・・・といろいろです。
「右肩こり」と表現する人もいます。
痛みの種類も鋭く差し込むような痛み(疝痛、せんつう)や鈍い重苦しい痛み、肩こりのように張った感じ、など一様ではありません。
痛みのほかにしばしば認められる症状は「発熱」です。
これは胆嚢内の胆汁がとどこおって細菌感染をおこすことによっておこります。悪化すると急性胆嚢炎という状態になり、腹痛とともに38度以上の熱がでることもあります(急性胆嚢炎の話はまた後ほどします)。
痛みがはっきりしなくて、熱だけがでるような場合は診断が難しいので、胆嚢結石による発熱を「風邪」として治療して症状が増悪することもあります。
右の肋骨の下の方のおなかを触ると他の部分よりおなかが硬く感じたり、押すことによって痛く感じたり(圧痛)することによって診断される事もありますが、自覚する腹痛がないとなかなか気づきにくい(診断されにくい)ので、困ります。さらに、結石が胆道にはまり込んだり、胆嚢が炎症を起こして腫れあがったりすると、胆汁の流れが悪くなって黄疸(おうだん)や肝機能異常を起こすことがあります。
肝機能異常は採血をして、肝逸脱酵素(GOT/GPTまたはAST/ALT)を測定すればわかります。
黄疸は胆汁の色素であるビリルビンによってひき起こされます。
採血でビリルビンを測定すれば分かりますが、黄疸が進行すれば眼球結膜(白眼、しろめ)や皮膚が黄色くなるので、自分でも分かります(みかんの食べすぎによって黄色くなるのは黄疸ではありません)。胆嚢結石をもっている人は、発熱やお腹の痛みを感じたら「胆石のせいかも?」と、担当の医師にお話したほうがいいと思います。
「おなかのかぜ」と胆嚢炎の区別は難しいことが時々ありますからね。
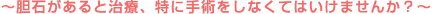
おなかが痛んだり、発熱があったりする胆嚢結石症は手術をしたほうがいいでしょう。
無症状の場合は基本的に手術適応ではありません。
ただし胆管結石は無症状でも治療が必要です。肝内結石はその状態によりますので、今は省きます。胆嚢結石症の症状は、結石そのものの機械的な刺激(胆嚢の中で動いたり、はまり込んだりすること)や結石があることによって2次的に引き起こされる胆汁のうっ滞(よどみ)や細菌感染によって引き起こされます。
そして、痛みの発作は1回生じると何度も繰り返すことが多いです。
治療は、結石ができる場所つまり胆嚢をまるごと切除してしまう必要があります。
「えっ?悪いのは胆石で、胆石を取り出すだけではだめなの?!」と質問されます
が・・・とらなくてはいけません。
なぜならば、一度胆石ができた胆嚢は結石ができやすい環境になっているからです。
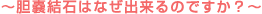
胆嚢結石ができる原因はいくつかあり、この原因によってできる胆石の種類も異なります。最も多いのはコレステロール結石といわれるものです。
コレステロール結石の成因と考えられていることを説明します。
肝臓の働きのひとつにコレステロールの代謝があります。
コレステロールは水に溶けないので一部は胆汁の中に溶け込ませて肝臓外に排出します。
胆汁の中には、コレステロールや胆汁酸といわれる脂質、リン脂質が含まれています。
この中のコレステロールと胆汁酸のバランスが崩れると、コレステロールが結晶化して石のもとになります。
胆嚢粘膜から分泌されるムチンというたんぱく質によってコレステロールの結晶がくっつきあって結石になっていきます。
これがコレステロール結石です。
結石ができるその他の原因としては、大腸菌の感染(ビリルビンカルシウム石)、溶血性疾患(黒色石)などが挙げられます。 |
|