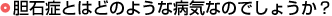
|
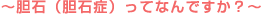
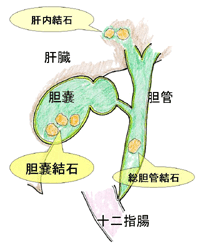 胆石(たんせき)とは肝臓(かんぞう)や胆嚢(たんのう)、胆管(たんかん)にできる結石です。結石(石)がどこにあるかによって、肝内結石、胆嚢結石、胆管結石(総胆管結石)という名称がついています。ほかにからだにできる石としては、尿の通り道にできる尿管結石、膀胱結石、腎臓でできる腎結石などがあります。 胆石(たんせき)とは肝臓(かんぞう)や胆嚢(たんのう)、胆管(たんかん)にできる結石です。結石(石)がどこにあるかによって、肝内結石、胆嚢結石、胆管結石(総胆管結石)という名称がついています。ほかにからだにできる石としては、尿の通り道にできる尿管結石、膀胱結石、腎臓でできる腎結石などがあります。
ほかにもすい臓、胃、腸、唾液腺などにも石ができることがあります。
「この前腎結石の治療をしたのに、今度は胆嚢に石ができた・・・!?」ということがあると、前の治療が悪かったから?と心配する人がいますが、そうではありません。
それぞれ石のできる仕組みが違うので、前回の治療とは全く無関係とご理解ください。さて、胆石に話を戻しましょう。
日本の統計では、最も多いのが胆嚢結石で78%、次いで総胆管結石が21%、肝内結石は1.3%でした。
それぞれの名前の後ろに「症」をつけて、胆嚢結石症、総胆管結石症、肝内結石症というと、病気の状態を表します。
一般的に胆石症というと最も多い胆嚢結石症をさしますが、そのほかにもいろいろな胆石症があることが分かります。
このように胆石といっても、できる場所によって原因も治療方法も異なりますので、治療する場合には正しい診断が必要です。
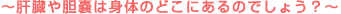
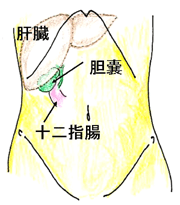 肝臓は右手を右の肋骨に当てて、ちょうど小指が肋骨の下(肋弓といいます)のあたるようにしたときに、その手のひらの奥のほうにあります。 肝臓は右手を右の肋骨に当てて、ちょうど小指が肋骨の下(肋弓といいます)のあたるようにしたときに、その手のひらの奥のほうにあります。
重さは、男性で1,000~1,300g、女性で900~1,000gで、なんと体重の約50分の1にあたります。重い臓器ですね。
肝臓では消化液である胆汁が作られます。肝臓でできた胆汁は、胆管という直径約0.8cmの管を通って肝臓の外にでて十二指腸に流れ込みます。
皆さんの「うんち」は黄色っぽいでしょう。
便の黄色は胆汁の中の「ビリルビン」という成分の色です。ですから、何らかの理由で胆汁が十二指腸に流れてこなくなると、便の色が白くなってしまうのです。
さて、胆汁は一日に600~1000ml排出されるのですが、これが直接十二指腸に流れ込むわけではなく、一時的に胆管の途中に枝分れして存在する胆嚢に貯蔵されます。
胆嚢は、握りこぶしぐらいの大きさ(長さ約8cm)のナスのような形の袋で、胆管から枝分かれをして存在し、一部は肝臓にくっついて固定されています(おなかの中でブラブラしているとねじれてしまいます)。
胆嚢の働きは複雑で、一時的に胆汁を貯蔵している間に胆汁内の水分や電解質を吸収し、濃い胆汁を作ります。
また、油脂の多い食事をしたり、生卵(特に卵黄)を食べると、胆嚢が収縮して胆汁を十二指腸に送り出して、油脂の分解を助けます。
胆嚢の位置は、みぞおちと右のわき腹を結んだ線の真ん中あたりの奥のほうにあります。
|
|