ほっとひと息 健康らんど
Vol.8 薬について
3.子供に上手に薬を飲ませるには?-② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
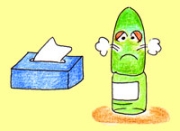 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
3.子供に上手に薬を飲ませるには?-② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
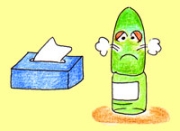 |
|
|
 |
 |
|
|
 |