 |
| |
ホルモンバランスの乱れによって心身に変調をもたらす更年期障害、なんだか辛そうで、考えると気が滅入りそうですね。
今回は、医療法人社団 あんしん会 四谷メディカルキューブウィメンズセンターの山本享子先生に、「更年期とどう向き合えばよいか」というテーマでお話をうかがいました。
|
| |
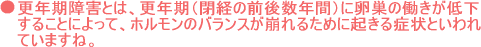 |
| |
「医学大辞典」では、「更年期に現れる多種多様な症候群で、器質的変化に相応しない、自律神経失調症を中心とした不定愁訴を主訴とする症候群」と定義されています。
この記述の中で重要なのは「器質的変化に相応しない」という部分です。身体に何か疾患があって症状が現れるものではない、つまり更年期障害は臓器の形態的な異常の病気ではないということは強調したい点ですね。
ただし、さまざまな症状が更年期障害ではなく、何かの疾患によるものかもしれないという疑いがある場合もあり、一人合点せず内科や婦人科などで調べる必要があります。
|
| |
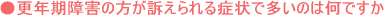 |
| |
「腰痛・背部痛」と「のぼせ感・汗」が多く、その他は、「頻尿・尿失禁」「肩こり」 「手足のしびれ」「めまい」「膣違和感・帯下」「頭痛」「不眠」「倦怠感」などがあります。全身にわたってさまざまな症状が現れるのが、更年期障害の特徴といえます。 「手足のしびれ」「めまい」「膣違和感・帯下」「頭痛」「不眠」「倦怠感」などがあります。全身にわたってさまざまな症状が現れるのが、更年期障害の特徴といえます。
|
| |
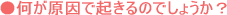 |
| |
一つは加齢。子どもには起きません。
それから、心理的要因と環境の変化も原因となります。更年期症状が現れ始めると、「老い」や「女性でなくなる」ことへの不安から、気持ちが沈んでいく症状が重くなる人がいます。また、子どもの教育や親の介護の問題など家庭環境の変化や仕事をしている女性であれば職場環境が変わることからくるストレスが原因で、症状が悪化する人がいます。
しかし、原因で一番わかりやすいのは、女性ホルモンの変化です。
下の図をご覧下さい。これは「女性ホルモンと卵胞数の編移」を表したものです。卵胞と卵子が入っている部屋のことで、その数が37歳前後を境に急激に減ることによって胎内のホルモンバランスが変わり、それが自律神経を乱して心身にトラブルを引き起こします。
|
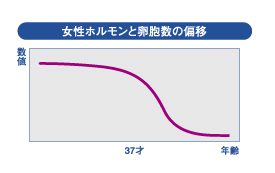 |
| |
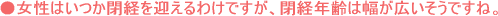 |
| |
早い人では30代で閉経を迎える人もいますし、60歳近くの人もいます。また、閉経にいたる経緯もいろいろで、大きく分けて3つのタイプがあります。
一つは標準型。これは、登山にたとえると、つづら折の道を時間をかけて登っていくような感じで、体が少しずつ慣れていくので更年期の症状が軽いのが特徴です。
二つ目は、早発閉経。これは、麓(ふもと)から頂上(閉経)へまっすぐ至近距離で登っていくようなもので、体がなれるゆとりも無く、症状が標準型より強いです。
三つ目は、人工閉経。これは、ヘリコプターで一気に山頂に降り立ち、突然の高山の環境になれることができないような状況で、症状がひどくなることもあります。
|
| |
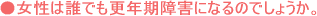 |
| |
全員というわけではなく、ならない人もいますし、なっても辛さを感じない人もいます。
疫学調査では、女性の50~80%が更年期障害になります。そのうち加療している人は20%です。注目していただきたいのは、加療している人の65%が1年くらい症状が続き、20%が5年以上続くということです。これは見方を変えれば幸いだといえます。辛く不快な時期はこれくらいで終わり、死ぬまで続くわけではないからです。
ちなみに、アジアの女性は欧米の女性に比べて症状が軽く、症状が現れる人の率も低いというデータがあります。この違いは女性ホルモンの低下に関係する食生活の違いだといわれています。
|
| |
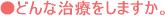 |
| |
お話を聴いた上で、お一人お一人の症状にあわせて治療します。心の悩みを解消する カウンセリングをしたり、食事や運動などの生活改善の指導をしたり、薬物治療としてホルモン補充療法や漢方薬療法を行います。ホルモン補充療法は効く場合と効かない場合があります。 カウンセリングをしたり、食事や運動などの生活改善の指導をしたり、薬物治療としてホルモン補充療法や漢方薬療法を行います。ホルモン補充療法は効く場合と効かない場合があります。
ホルモン補充療法は、20年以上前にアメリカで副作用が問題となり、一時期使用が禁止されたことがあります。しかし、現在は、日本婦人科学会でも、医師と相談しながら必要な時期、必要な量を使用するのであれば、危険性は少ないというコンセンサスが得られつつあります。ホルモンのアンバランスが原因で症状がひどいときにホルモン補充療法を行うと、不快な症状がだいぶ解消されます。
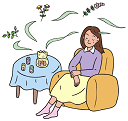 このほか、マッサージ、リラクゼーション、アロマテラピー、旅行、運動などの代替療法も、更年期障害の治療法として有効です。
このほか、マッサージ、リラクゼーション、アロマテラピー、旅行、運動などの代替療法も、更年期障害の治療法として有効です。
|
| |