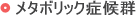 |
| |

|
まず自分の内臓脂肪の蓄積がどういう状態か、毎日どのくらい食べてどのくらい使っているかを知ることが大事です。その上で1日の摂取エネルギーが消費エネルギーを上回らないようにする。つまり食べ過ぎない、飲み過ぎないようにする。食事のエネルギー設定は糖尿病の患者さん向けの食事療法で使われる簡易法を参考にされるといいでしょう。
私は企業で働いている人の健康管理、いわゆる産業保健分野での活動が多いので、サラリーマンのライフスタイルを分析していますが、健康を損なう原因の多くは働き方と関係があるようです。特に多くのライフスタイルの乱れに関わるのは、夕食が遅くなると食べてすぐ寝ることになり、朝食も欠食しがち、運動不足でストレス過多になります。ですから、残業をするときは早目に夕食を食べ、それから仕事をして、夜食は食べない、朝食はきちんと食べる、よく咀嚼するようにとお話しています。太らない生活習慣は健康な生活習慣とイコールなのです。
|
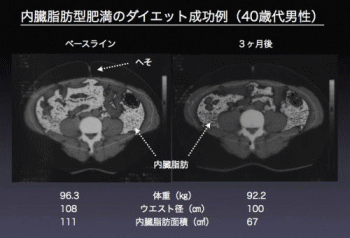
|
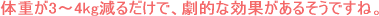
|
|
内臓脂肪を減らすのはいわば肥満対策なので、体重を減らせばいいわけですが、肥満が引き起こす疾病にも、脂肪組織が物理的に増えることで起きるものと、脂肪細胞の機能異常で起きるものがあります。前者は、睡眠時無呼吸症候群や腰痛などで、これは脂肪の物理的な重さや量が原因なので、体重を10kgくらい落とさないと効果が現れません。糖尿病やメタボリック症候群は後者で、激ヤセしなくても、体重を3~4kg減らせば機能異常は改善します。たった3~4kgと思われるでしょうが、我々の経験では、その程度の減量で、内臓脂肪面積も30cm² 程度、劇的に減少しています。
|
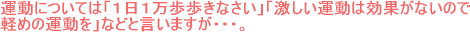
|
 目安として、有酸素運動を1回10~30分、週3~5日行うと脂肪燃焼に効果があるとされていますが、5分でも10分でもOKです。通勤時に1駅前でなく2駅前で降りて歩きなさいと言いますが、1駅でもいい。激しい運動は内臓脂肪を消費しないので効果がないと言いますが、筋力トレーニングも基礎代謝をあげますので決して無意味ではありません。米国の糖尿病予備群を対象とした大規模調査では、週合計150分の運動で3年後の糖尿病発病が半分になるというデータがあります。多くの人がほとんど体を動かしていない状況でありますので、私は「やれることなら何でもいいです。大事なのは始められること」とお話しています。
目安として、有酸素運動を1回10~30分、週3~5日行うと脂肪燃焼に効果があるとされていますが、5分でも10分でもOKです。通勤時に1駅前でなく2駅前で降りて歩きなさいと言いますが、1駅でもいい。激しい運動は内臓脂肪を消費しないので効果がないと言いますが、筋力トレーニングも基礎代謝をあげますので決して無意味ではありません。米国の糖尿病予備群を対象とした大規模調査では、週合計150分の運動で3年後の糖尿病発病が半分になるというデータがあります。多くの人がほとんど体を動かしていない状況でありますので、私は「やれることなら何でもいいです。大事なのは始められること」とお話しています。
|
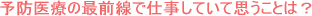
|
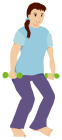 メタボリック症候群のおかげで生活習慣病の予防にスポットが当たっているのはうれしいのですが、頭では予防の大切さを分かっていてもアクションを起こす人が少ないのが現状です。やはり「わかっちゃいるけど、変えられない」、最初の一歩を踏み出せるかが難しいところです。重要なのは「ハードルを下げる」こと。メタボリック症候群の考え方を摂り入れることで「まず3kg減らそう」と目標を定められれば、ずいぶん取り組みやすくなります。もう一つ重要なのは「自分を知る、自分で決める」こと。働き盛り世代は、多くの生活の課題やストレスと闘っています。ちょっと健診で引っかかったときに「で、どうされますか?」という問いかけが大事です。
メタボリック症候群のおかげで生活習慣病の予防にスポットが当たっているのはうれしいのですが、頭では予防の大切さを分かっていてもアクションを起こす人が少ないのが現状です。やはり「わかっちゃいるけど、変えられない」、最初の一歩を踏み出せるかが難しいところです。重要なのは「ハードルを下げる」こと。メタボリック症候群の考え方を摂り入れることで「まず3kg減らそう」と目標を定められれば、ずいぶん取り組みやすくなります。もう一つ重要なのは「自分を知る、自分で決める」こと。働き盛り世代は、多くの生活の課題やストレスと闘っています。ちょっと健診で引っかかったときに「で、どうされますか?」という問いかけが大事です。
最後に、予防の対象になる人が非常に多いので、医師、保健師、栄養士、トレーナーなど多くの職種が連携してサポートするしくみをつくることが大事だと思っています。
|