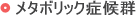 |
| |
|
メタボリック症候群がおおきな話題となっていますが、「言葉が目新しいだけで生活習慣病となんら変わらないのでは?」といった声も聞かれます。そこで、順天堂大学医学部総合診療科の准教授で産業医でもある福田洋先生に、メタボリック症候群の診断基準、発症のメカニズムと予防策、意義などについてお話をうかがいました。
|
|
|
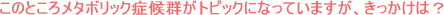
|
|
2005年4月に内科系8学会が合同で、メタボリック症候群の診断基準をまとめました。腹囲(へそ周囲)が男性は85cm以上、女性は90cm以上で、糖尿病、高脂血症(脂質異常症)、高血圧のうち二つ以上該当する人はメタボリック症候群が強く疑われる、一つ該当する人は予備群であるという基準を示したわけですが、それが一般に知られるようになったのが最初です。次いで、その基準をもとに厚生労働省が「国民健康・栄養調査」でメタボリック症候群に該当する人がどのくらいいるかを調べたところ、40~74歳の男性の2人に1人、女性の5人に1人、約1960万人が該当者または予備群であることが分かり、そのデータを2006年5月に新聞各紙が一斉に報道。それで一気に広まったのです。
|
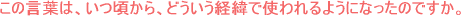
|
 昔から、糖尿病や高脂血症、高血圧などの生活習慣病の個々について恐いとか危険であると言ってきたわけです。ところが、1980年代の後半になると、動脈硬化に関係のあるそれらの病気が二つ、三つ、四つと重なると、非常に危険であると言われるようになり、「内臓脂肪症候群」「死の四重奏」「インスリン抵抗性症候群」などと命名されました。
昔から、糖尿病や高脂血症、高血圧などの生活習慣病の個々について恐いとか危険であると言ってきたわけです。ところが、1980年代の後半になると、動脈硬化に関係のあるそれらの病気が二つ、三つ、四つと重なると、非常に危険であると言われるようになり、「内臓脂肪症候群」「死の四重奏」「インスリン抵抗性症候群」などと命名されました。
それらの病気がたまたま重複するのか、それとも何か一緒に起きる根本的な要因があるのか研究が進められ、内臓にたまっている脂肪が引き金であることが突き止められたのです。むろん、遺伝や環境要因もあるので、100%内臓脂肪が要因であるとは言えませんが、少なくとも内臓脂肪が悪さをすること、つまり内臓脂肪の蓄積によって糖や脂質の代謝に異常をきたすことが分かりました。そこで、WHOが1999年、それまでバラバラだった呼称を統一して、メタボリック症候群と呼ぶことにしたのです。ちなみに、肥満や糖尿病、高脂血症、高血圧を三つか四つ重ねて持っている人は、それらの危険因子を全く持たない人に比べて冠動脈疾患の発症リスクが30倍以上になることが、わが国の大規模な統計調査研究で明らかになっています。
|
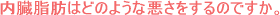
|
メタボリック症候群を川の流れにたとえると、最上流に生活習慣、過食と運動不足が位置します。これが内臓脂肪の蓄積を引き起こします。この脂肪からは遊離脂肪酸が放出され、高脂血症の原因になります。また、アディポサイトカインと呼ばれる生理活性物質が放出され、インスリン抵抗性を引き起こして糖尿病の発症や悪化、末梢血管を収縮させて高血圧の発症や悪化の原因となります。このほか、アディポサイトカインには血液を固まりやすくするものもあり、これらによって動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞を発症します。
近年は、メタボリックドミノという概念も提唱されています。これは、生活習慣から動脈硬化に至るまでの流れは同じですが、最下流には、いま社会問題になっている認知症や寝たきりなども位置づけられています。
|
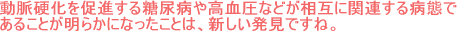
|
 メタボリック症候群の画期的な点は、内臓脂肪の蓄積によって多くの生活習慣病が引き起こされることと、個々の生活習慣病をバラバラではなく同時に、より原因に近いところで効率よく予防できることの可能性を示したことにあります。
メタボリック症候群の画期的な点は、内臓脂肪の蓄積によって多くの生活習慣病が引き起こされることと、個々の生活習慣病をバラバラではなく同時に、より原因に近いところで効率よく予防できることの可能性を示したことにあります。
|