健康・医療用語辞典 ~た行~
糖質
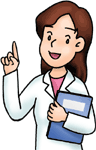 直接のエネルギー源となり、特に脳のエネルギー源はブドウ糖だけというように生体維持にとても大切ですが、エネルギーをあまり使わない人が摂り過ぎると、生活習慣病の原因となります。
直接のエネルギー源となり、特に脳のエネルギー源はブドウ糖だけというように生体維持にとても大切ですが、エネルギーをあまり使わない人が摂り過ぎると、生活習慣病の原因となります。
糖質は単糖の数でブドウ糖、果糖などの単糖類、蔗糖や麦芽糖などの少糖類、でんぷんに代表される多糖類があります。摂取された糖質は主にエネルギー源となり、残りは体脂肪へと変換されます。糖質が吸収・代謝される過程でエネルギーを産生し、肝臓に入ったブドウ糖はそのほとんどがグリコーゲンとして蓄積され、残りは血液中に放出されたり、脂肪酸やアミノ酸に転換されます。体内に蓄積できる糖質には限りがあるため、エネルギーを供給し人体の機能を正常に保つためにはこまめに補給しなければなりません。糖質の摂り過ぎはエネルギー過剰になり体脂肪の蓄積、肥満やその他の生活習慣病の原因となります。特に蔗糖はインスリンの分泌を刺激するので過剰摂取が続くと糖尿病、肥満、高脂血症などのリスクが増します。また、脳は通常ブドウ糖のみをエネルギー源としていて、血糖値が下がり過ぎると意識障害を起こすこともあるので、その意味でも糖質のコンスタントな補給は重要です。