健康・医療用語辞典 ~さ行~
脂質
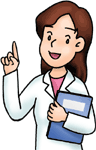 脂質は広い意味では体を守る働きを持っていますが、摂り過ぎは動脈硬化や肥満のもとになるため、総摂取カロリーの25%以下に抑えたほうがよいでしょう。
脂質は広い意味では体を守る働きを持っていますが、摂り過ぎは動脈硬化や肥満のもとになるため、総摂取カロリーの25%以下に抑えたほうがよいでしょう。
脂質というと生活習慣病の元凶としてのイメージが強いものですが、摂取量が適性である限り必要不可欠の栄養素であることに変わりはありません。脂質は最大のエネルギー貯蔵庫として、エネルギー不足の際にはすかさずエネルギーを供給して人体の機能や生命維持に働き、細胞膜を構成する成分として細胞膜の機能にも深く関与し、蓄積された体脂肪は保温や外部からの力に対する防御の役割も果たし、味覚の上では美味しさのカギともなっています。適性摂取量は1日の総摂取エネルギー比の20〜25%といわれていますが、動脈硬化症や肥満が懸念される場合は20%程度に抑えたほうがよいでしょう。摂り過ぎるとエネルギー過剰となり肥満、それに伴う生活習慣病のリスクが増し、コレステロールの摂取が多いと動脈硬化の原因ともなります。よほど栄養不足が続かない限り脂質不足の状態にはなりませんが、ビタミンA、D、E、Kなどの脂溶性ビタミンの吸収のためには経口的に摂取する必要があります。