健康・医療用語辞典 ~か行~
カルシウム
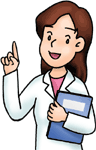 骨と歯のもととなり、鉄の代謝や神経系の伝達を促進する働きがあります。乳製品、大豆、緑黄色野菜などに多く含まれます。
骨と歯のもととなり、鉄の代謝や神経系の伝達を促進する働きがあります。乳製品、大豆、緑黄色野菜などに多く含まれます。
人体内にあるカルシウムの量はほかのどのミネラルより多く、そのほとんどは骨と歯の中にあり、成人の骨に含まれているカルシウムの20%は毎年新しく吸収されたものと置きかえられています(古い骨の細胞が壊されて新しい細胞が作られる)。また、カルシウムはリンと一緒に働いて健康な骨と歯を作り、マグネシウムと一緒に働いて心臓と血管の健康を保つとともに、体内での鉄の代謝や神経系の伝達を促進します。カルシウムは牛乳や乳製品、大豆やイワシ、緑黄色野菜などに多く含まれ、所要量は15〜17歳の男性で800mg、女性で700mg、成人男性で600〜700mg、女性で600mgとされ、許容上限摂取量は成人で2,500mgとなっています。欠乏するとくる病や骨軟化症、骨粗しょう症が、過剰に摂取すると泌尿器系結石、カルシウム過剰血症、便秘などが現れます。