健康・医療用語辞典 ~は行~
ビタミンD(V.D)
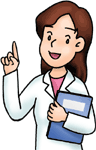 カルシウムの吸収を促進するため、骨粗しょう症の予防に重要な役割を果たします。魚、乳製品、干しシイタケなどに多く含まれます。
カルシウムの吸収を促進するため、骨粗しょう症の予防に重要な役割を果たします。魚、乳製品、干しシイタケなどに多く含まれます。
骨と歯に必要なカルシウムとリンの代謝に関わる脂溶性ビタミンで、食品から摂れるほか、紫外線が皮膚の脂肪に作用して作られ体に吸収されますが、あまりに日焼けし過ぎてしまうと皮膚を通してのビタミンDの生成は止まります。またビタミンA、Cと一緒に摂取すると風邪の予防にも効果があるといわれています。魚の肝油やイワシ、ニシン、サケ、マグロや乳製品などにたくさん含まれ、所要量は15〜17歳および成人の男女で100IU、許容上限摂取量は2.000IUとされています。過剰に摂取すると高カルシウム血症や腎機能障害、軟組織の石灰化などが起こり、逆に欠乏すると幼児期ではくる病、成人では骨軟化症や骨粗しょう症の誘因となります。さらに、ビタミンDの効果はビタミンA、C、コリン、カルシウム、リンと一緒の時に最大になるといわれています。