健康・医療用語辞典 ~は行~
ビタミンB6 (V.B6)
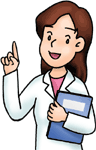 神経や皮膚の障害を予防し、自然の利尿剤としての働きもあります。玄米やビール酵母、大豆などに多く含まれます。
神経や皮膚の障害を予防し、自然の利尿剤としての働きもあります。玄米やビール酵母、大豆などに多く含まれます。
ピリドキシンともいわれる水溶性のビタミンで摂取後8時間以内に排泄されるため、ほかのB群のビタミン同様コンスタントに補充しなければなりません。たんぱく質と脂肪の吸収やトリプトファンがビタミンB3に転換することを助け、神経や皮膚の障害を予防し、筋肉の痙攣や脚の引きつり、手のしびれなどを緩和し、自然の利尿剤としても働きます。レバーや小麦胚芽、玄米、ビール酵母、大豆、タマゴなどに多く含まれ、所要量は15〜17歳および成人の男性で1.6mg、女性で1.2mg、許容上限摂取量は15〜17歳の男女で90mg、成人男女で100mgとなっています。ビタミンB6が欠乏すると皮膚炎が現れることがありますが、通常の食生活ではまず問題ありません。逆に過剰に摂取すると末梢性感覚性神経症、知覚神経障害などの誘因となる可能性があります。