健康・医療用語辞典 ~は行~
ビオチン(V.H)
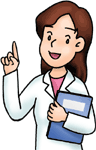 脂肪やたんぱく質の代謝に不可欠で、白髪や抜け毛の予防、皮膚炎の緩和などの働きがあります。大豆、ビール酵母、牛乳などに多く含まれます。
脂肪やたんぱく質の代謝に不可欠で、白髪や抜け毛の予防、皮膚炎の緩和などの働きがあります。大豆、ビール酵母、牛乳などに多く含まれます。
水溶性で硫黄を含むビタミンB群のひとつで、食品から摂取するほか腸内細菌によっても作られます。脂肪とたんぱく質の代謝に不可欠で、糖新生、脂肪酸合成、エネルギー代謝などに関連する酵素の補酵素として働きます。また、ビタミンCの合成にも必要で、ビタミンB2、B3、B6、Aとともに健康な皮膚を維持する、白髪や抜け毛を予防する、筋肉痛を和らげる、湿疹や皮膚炎を緩和するなどの働きがあります。牛のレバー、卵の黄身(白身はビオチンの吸収を妨げます)、大豆、ビール酵母、牛乳などに多く含まれ、所要量は15〜17歳の男女で26μg、成人男女で30μgとされています。欠乏すると顔や体に湿疹が出たり、激しい疲労感や脂肪の代謝低下などの症状が現れます。また、通常の食生活ではビオチンの過剰摂取が問題となるようなことはありません。