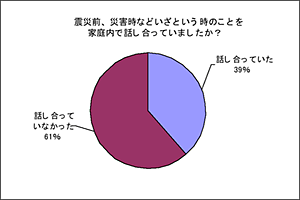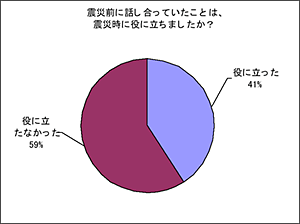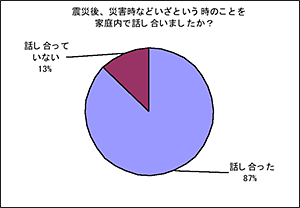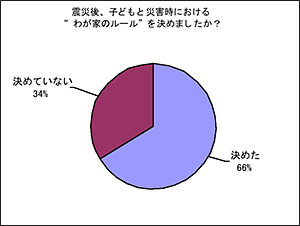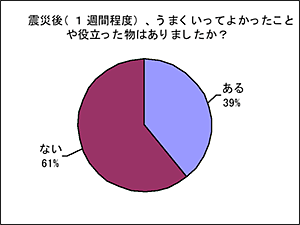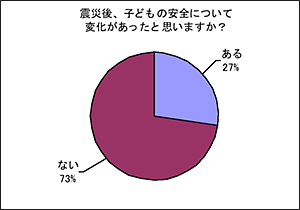「東日本大震災後の子どもを取り巻く危険の変化に関する調査」を実施
震災後、87.1%の家庭が“災害時どう行動するか”話し合い、
そのうち66.4%が“わが家のルール”を決定
セコム株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:前田修司)は、特定非営利活動法人・子どもの危険回避研究所の協力のもと、2011年3月11日時点で一都三県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)にお住まいで、その時お子さんが小学校1年生から中学校3年生までだった保護者に対し、独自に「東日本大震災後の子どもを取り巻く危険の変化に関する調査」を実施しました。
調査は、104名の保護者を対象としました。その結果、震災が起こる前、災害時にどのように行動するかについて話し合っていた家庭は39%だったのに対し、震災後は87%の家庭で、話し合いをしたことが分かりました。今回の震災が、災害が起こった際の行動について家庭内で話し合うきっかけになったことが伺える結果です。
また、震災後に話し合いを持った家庭のうち66%が“わが家のルール”として、家庭内で災害時の行動ルールを決めたことが明らかになりました。その内容は、安否確認の方法や避難場所に関するもの、学校にいる時や登下校時に関するものなど、多岐にわたります。
セコムは、2006年2月から「子どもの防犯ブログ」の運営や防犯や防災に関する絵本の監修によって、防犯・防災など広く「子どもの安全・安心」についての啓発活動を行ってきました。いつ、どこで発生するかわからない災害に備え、家庭内で子どもの安全を守るために役立つ行動やルールを決めるのは非常に大切です。9月1日の「防災の日」にあたり、また9月11日には東日本大震災から6カ月を迎えるにあたり、今回の調査が「子どもの防災」を考える一助となれば幸甚です。
●アンケート項目(実施項目より抜粋)
| 1 |
震災前、災害時などいざという時のことを家庭内で話し合っていましたか?
|
| 2 |
話し合っていたことは、震災時に役に立ちましたか?
|
| 3 |
震災後、災害時などいざという時のことを家庭内で話し合いましたか?
|
| 4 |
震災後、子どもと災害時における“わが家のルール”を決めましたか?
|
| 5 |
震災後、うまくいってよかったことや役立った物はありましたか?
|
| 6 |
地震後、子どもの安全について変化はあったと思いますか?
|
【質問1】震災前、災害時などいざという時のことを家庭内で話し合っていましたか?
| ――約61%の方が「話し合っていなかった」と回答 |
|
震災前は、6割以上のご家庭が災害時のことについて話し合っていなかったことがわかりました。災害大国と言われる日本ですが、子どもと非常時について話し合っていた家庭は多くなかったことが伺えます。
| 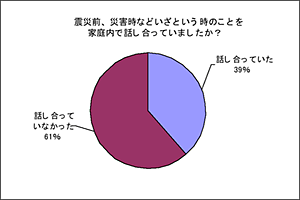
|
【質問2】震災前に話し合っていたことは、震災時に役に立ちましたか?
| ――約41%の方が「役に立った」と回答 |
非常時の行動などについて話し合っていたと回答した方のうち、それを実際の災害時に役立てられたのは4割に達しました。いかに事前の準備が防災対策にとって重要かが明らかになりました。
「役に立った」と回答された方から寄せられた、実際に役立ったこと、話し合っていて良かったことを以下にご紹介します。
| 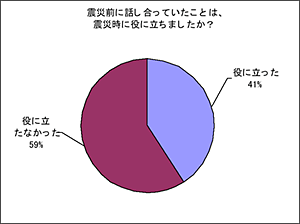
|
■外出時に関するもの
| ・ |
避難場所の確認をしておいたこと。 |
| ・ |
自宅と学校がかなり離れており、何かあっても迎えに行けない可能性もあるので、学校の近くで被災したら基本は学校に留まるか泊まるかする。 |
| ・ |
多くの知人と行動を共にするということ。その中の誰かの親と連絡を取れる確率が高いし、その親を通じて身の安全を確認できる。 |
| ・ |
登下校時の、保護者との待ち合わせ場所を決めておいたこと。 |
| ・ |
地震が来たときは、近くの大人の人から離れないで、一緒にいること。これを約束していたので、すぐに子どもを見つけることができた。 |
|
■在宅時に関するもの
| ・ |
非常用持ち出し袋を家族の人数分用意してあるので、すぐ身に着けること。揺れている間は机などの下に隠れること。 |
| ・ |
揺れが収まったあと、室内のドアや玄関のドアを開け、避難路の確保をすること。学校での避難訓練も役だっていたようだ。 |
| ・ |
おかずを冷蔵庫に常備しているので、自分で用意して食べること。 |
| ・ |
お風呂に水を汲み置きしているので、いざというときに使うこと。 |
|
【質問3】震災後、災害時などいざという時のことを家庭内で話し合いましたか?
| ――約87%の方が「話し合った」と回答 |
|
東日本大震災後、多くのご家庭で災害時など非常時について話し合いが持たれたことが分かりました。大震災の発生が、各家庭内の防災に対する意識や関心を向上させたことが読み取れます。
| 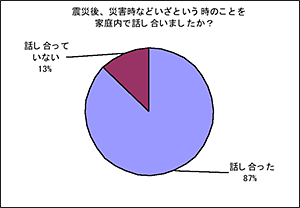
|
【質問4】震災後、子どもと災害時における“わが家のルール”を決めましたか?
| ――約66%の方が「決めた」と回答 |
家庭での話し合いの際に大切になるのが、震災時にどう行動すべきかを家族内で決めておくことです。東日本大震災発生時、公共の交通機関がストップしたり電話など通信機器がつながらなかったりし、家族の安否確認に時間がかかるなど、大きな混乱が起きました。そのためか、安否確認の方法や子どもの登下校中における注意点などの意見が多くみられました。
以下に、抜粋したものをご紹介いたします。
| 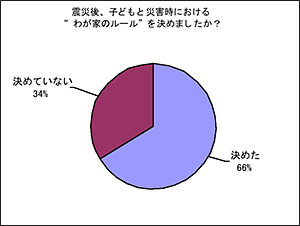
|
■ 安否確認や避難場所について
| ・ |
電話が通じない場合は災害用伝言板を利用する。 |
| ・ |
いざというときの帰宅方法や家族との連絡の取り方、親がいない時の待機場所を決めた。 |
| ・ |
連絡をとれる手段を複数決めた。 |
| ・ |
近所の一次避難場所、緊急避難場所、広域避難場所などを家族で確認した。町内会の防災訓練にも家族で参加した。 |
| ・ |
ツイッターが連絡手段として有効と聞いたので、家族間でフォローし合っている。 |
| ・ |
地震や火事の時の避難場所や、家族・親族の電話番号などを記載したものをカードにして家族全員が持つようにした。 |
|
■ 外出時(登下校含む)の行動について
| ・ |
下校中に地震にあったら、家か学校かどちらか近い方に行くこと。 |
| ・ |
通学路の狭い路地は塀が崩れるおそれがあるので、震災時には通学路ではない大きな道を使って帰宅すること。 |
| ・ |
遊びに行っている時に被災したら、近くの友達の家、あるいは大人のそばにいく。 |
| ・ |
電車の中ならば、駅員さんや大人に従い、駅のどこで待ち合わせをするか決めた。 |
| ・ |
電車が止まっている時は、学校から無理に帰宅せず、避難場所に泊まり、電車が動いてから帰ってくる。 |
|
【質問5】震災後、うまくいってよかったことや役立った物はありましたか?
| ――約39%の方が「ある」と回答 |
|
震災による、いままで誰もが経験したことのない混乱の中でも、各家庭で「これはうまくいった、役に立った」ということや物があったようです。以下に、抜粋してご紹介します。
| 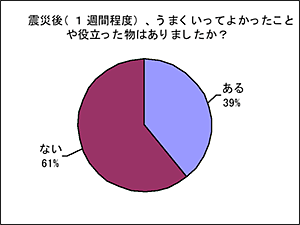
|
| ・ |
SNSや災害用伝言板が役に立った。 |
| ・ |
子どもが理科の授業で乾電池・豆電球を使っていたので、それで懐中電灯を作ってくれた。 |
| ・ |
子ども用のヘルメットが役立った。 |
| ・ |
電池式のラジオ。停電の時役立った。 |
| ・ |
ワゴン車。車内に布団を敷いておき、非常食なども積んでおいたので安心だった。 |
| ・ |
ワンセグチューナー付きのパソコン。充電しておいたので停電時でもTVが見られ、食卓の電灯代わりにもなった。 |
|
【質問6】震災後、子どもの安全について変化があったと思いますか?
| ――約27%の方が「ある」と回答 |
|
地震や津波など、震災による直接的な被害を受けていない首都圏でも、子どもの安全に関わることに変化があったようです。中でも防災意識に関する変化についての意見が多く見られました。以下に、抜粋したものをご紹介します。
| 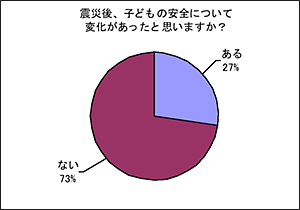
|
■ 危険になった点
|
■ 安全になった点
|
■ 防災意識に関する点
| ・ |
携帯電話や使い捨てマスク、アメなどを持ち歩くようになった。 |
| ・ |
懐中電灯を持たせるようにしている。 |
| ・ |
学校から非常時の連絡の取り方などが発信された。 |
| ・ |
防災訓練などに真剣に取り組むようになった。 |
| ・ |
塾が緊急避難場所や連絡先の再確認をしてくれた。 |
|
■ その他
|
<本報道に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。>
セコム株式会社 コーポレート広報部 堀越 TEL 03-5775-8210